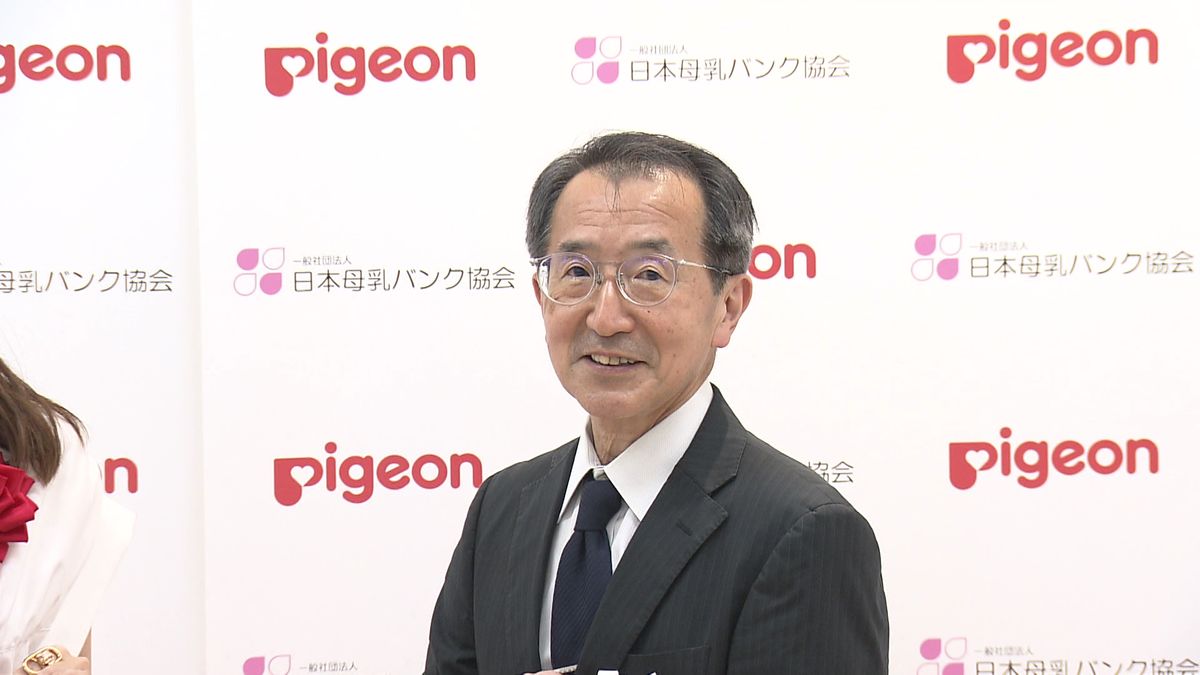小さな赤ちゃんの命を救う「ドナーミルク」 課題は? 利用者の声は?
「ドナーミルク」とは、全国の母親たちから寄付された母乳を低温殺菌処理して作られるもので、小さな体で生まれた赤ちゃんに提供され、命を救ってきた。
このドナーミルクを作っているのが「母乳バンク」で、運営を担う日本母乳バンク協会は、2024年5月27日で設立7周年を迎える。
5月13日には、この協会の「日本橋 母乳バンク」がリニューアルされた。最新の低温殺菌処理器が導入されるなど、大幅な供給量の改善が見込まれる。一方で、まだまだ課題があるという。どのような課題を抱えているのか。
■誰が必要としているのか?
ドナーミルクは、出生体重1500g未満で生まれた「極低出生体重児」と呼ばれる赤ちゃんに必要なもので、無償で提供されている。
日本では、2022年には極低出生体重児は5700人以上生まれ、2023年度にドナーミルクを使った赤ちゃんは1000人にのぼる。早産などが原因で小さく生まれた赤ちゃんは、母親のおなかの外で生活するための機能が未熟で、様々な病気(特に目と肺)にかかるリスクがある。そのため、赤ちゃんにとって「薬」ともいえる栄養満点の母乳を、出生後なるべく早く(12時間以内)から与えることが大切だという。
一方で、母親の体調が優れず母乳が出ない、薬の影響で母乳が得られないなどの場合、母乳が得られるまでのつなぎとして、ドナーミルクを使用することが有効になる。
仮に、腸が未熟な状態の赤ちゃんに、ドナーミルクではなく、牛由来の成分で作られた粉ミルクを与えた場合、消化吸収できずに腸が壊死(えし)してしまう「壊死性腸炎」を発症し、死に至る場合もある。もし助かったとしても、耳や目、身体発達などに様々な後遺症が残る可能性がある。
ドナーミルクを使用するもう一つのメリットについて、日本母乳バンク協会の代表理事である水野克己医師は「お母様にとって我が子に人工呼吸器を使ったり、中心静脈カテーテルを使うのは痛々しいもの。これらがすべて早く終わることができる。何もついていない我が子に早く向き合うことができる」とドナーミルクを使うことで、家族の心理的にも大きな安心感につながることを強調した。
■ドナーミルクの安全性は?
現在、日本で作られているドナーミルクについて、水野医師は「これまで2500人以上の赤ちゃんがドナーミルクを使用したが、誰一人として問題は起きていない」と強調した上で、「日本のドナーミルクは世界トップレベルの安全性が確保されている」とした。根拠は下記の通り。
・手術室レベルの清潔度が確保された室内で作業が行われる
・ドナーミルクの分注など、外気に触れる作業はさらに清潔度が高い「クリーンベンチ」と呼ばれる機械の中で行われる
・冷凍庫、冷蔵庫、低温殺菌処理器、全ての工程で厳重な温度管理がされている
・「ボールペンの点」ほどの大きさのゴミも見逃さないよう、各工程において目視で確認している
・ドナーミルクを作る前後で行う検査の基準は、世界で最も厳しいものを採用している
■利用者の声「1年前はこんなふうに過ごしているなんて思っていなかった」
実際にドナーミルクを使用した人の声はどうだろうか。
岡野さん(仮名)は予定より約3か月早く、678gの男の子を出産した。子どもの成長や母乳の出る量によってドナーミルクを適宜使用し、約6か月間、ドナーミルクを使用した。
岡野さんはもうすぐ1歳半になる息子を見ながら「今はもう普通の子たちと一緒に保育園に行って遊んで、帰ってくる。1年前はこんなふうに過ごしているなんて思っていなかった」と話した。
続けて「母乳が足りなかったり出なかったりしても、大丈夫なんだと思ったら、気持ちの余裕がでた」と、心理的な部分でもドナーミルクの存在は大きかったという。
水野医師は、母乳が出ないお母さんの中には、プレッシャーや自責の念など、心理的な影響から母乳が出にくい人もいたが、ドナーミルクの存在が安心につながり、母乳が出るようになったというお母さんもたくさんいたと話す。
佐藤さん(仮名)は予定より約4か月早く、400gの女の子を出産した。母乳が出るまで5日ほどドナーミルクを使用したが、「初めて娘に与えるのが自分の母乳ではないという複雑な気持ちがあった」と話した。
続けて当時の心境について、「娘が生死をさまよっている状態で、子どもにとってできることは何でもしてほしい思いがあったので、迷わずに決断することができた」と話した。
■クラウドファンディング達成で施設をリニューアル
2023年11月から約2か月間行われたクラウドファンディングでは、目標金額を上回る2400万円以上が集まり、「日本橋 母乳バンク」は下記の通り大幅にリニューアルされた。
・最新の低温殺菌処理器を購入し、処理力が約3倍に
・手術室レベルの清潔度の作業スペースが約2倍に拡大
・冷凍庫や冷蔵庫、クリーンベンチなどを増設
・蓄電池を増設し、震災などによる停電時でも対応可能
リニューアル前は9割の稼働率で、万が一機械に不具合があった場合はドナーミルクの生産が止まってしまう状態だったが、最新の低温殺菌処理器が手に入ったことでバックアップ体制が整い、需要の増加にも対応できるようになった。
■喫緊の課題は運営の資金と体制
クラウドファンディング分を除いては、日本母乳バンク協会は赤字運営。収益は病院からのドナーミルク利用料や寄付によるものが中心で、イギリスから輸入している消耗品が高騰していることが大きく影響している。
さらに、資金難の影響で運営スタッフが不足しているという。現在は常勤者2名(事務1人と低温殺菌処理を行う1人)のみ。どちらかが体調不良などで欠勤する場合、供給が止まるリスクもある。そのため最低もう1人は常勤者が必要だが、雇用する資金がないという。
ドナーミルクの利用施設数は現在、約100まで伸びている。出生体重1500g未満の赤ちゃんの中で、生後24時間以内にお母さんから母乳が出ないなどの理由で、一時的にでもドナーミルクが必要な赤ちゃんは、推定約5000人いるとされる。
水野医師は、小さく生まれてきた赤ちゃんが、他の赤ちゃんと同じように大きく元気に健康に育つためにドナーミルクは必要と説明した上で、「一人一人、大切な命。これを守るためには、母乳バンクが絶対に広がっていかないといけない」と語り、活動への理解と協力を求めた。