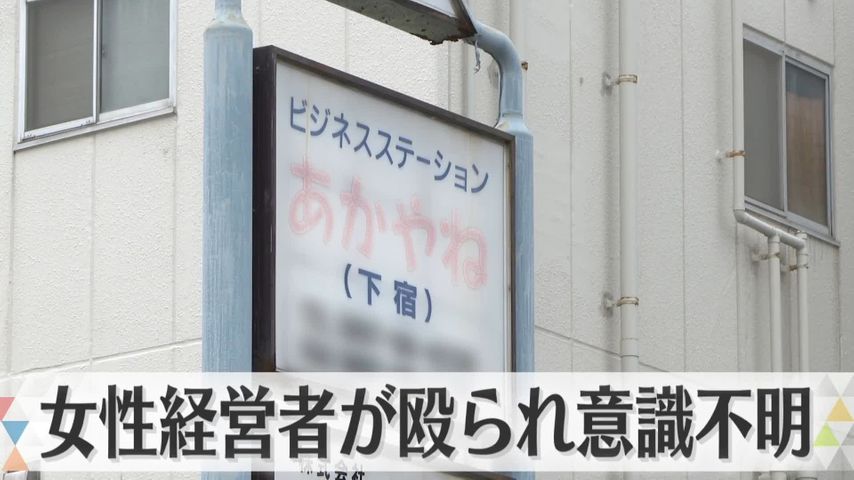「地域回復や地域再生にもつながる」伝統的林業・樵木林業復活へ美波町の男性の挑戦【徳島】
3年前に立ち上げられた「四国の右下木の会社」
真っ赤に焼けた炭。
プロの料理人などが使う「備長炭」です。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「いい炭は、生まれる瞬間からきれいなんで。窯出しの日は、いい炭出るかなって気になりますね」
美波町出身で、地域活性化を支援する会社を経営している吉田基晴さん(52歳)です。
吉田さんは、地元の伝統的な林業を復活させて新たな産業にしようと、3年前、新たに「四国の右下木の会社」を立ち上げ、木の伐採や炭づくりなどを行っています。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「徳島の県南って、すごく恵まれた炭や薪の材料があるということは私にとっても知らない事実だったし、山に手入れをすることによって環境を回復させる意味とか意義もあるので、もう1回現代でなりたつ林業、現代でなりたつ炭や薪の産業にチャレンジしてみたいと」
備長炭に適している木は、美波町など県の沿岸部に多く自生しています。
吉田さんは、町が所有する山などで「ウバメガシ」といった炭の材料となる木を伐採しています。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「この、こげ茶色の木が『ウバメガシ』ですね、あの辺全部ウバメガシです。これは、1年中葉っぱが落ちない常緑樹とか照葉樹と言われる木で、備長炭にとっては最高の木です。西日本の沿岸に多くて、昔はこれを使って薪や炭にして関西に出荷するという産業がすごく盛んだった」
美波町や、隣の牟岐町では、昭和40年代まで林業が盛んに行われていました。
旧日和佐町では1954年に木炭約90トン、薪100万束を生産し、林業の売り上げの約7割を占めていました。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「全国的に見たら、今この木は減っているのですごく価値がある。徳島の森には宝の山というか、価値のある木がたくさん残ってる。それを産業に変えていくということができればなと」
循環型の林業「樵木林業」
吉田さんが着目したのは、町で伝統的に行われていた「樵木林業」と呼ばれる循環型の林業です。
「ウバメガシ」などの木はある程度まで成長してから切ると、切り株からまた新しい芽がのびる性質があり、10年ほどで再び切ることができるそうです。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「これ、おそらく2か月ぐらい前に切ったと思いますけど、ウバメガシの特性で、切ると切り株から次の芽が生えてくるんですね。これは『萌芽更新』というんですけど、スギやヒノキは基本的に1回切ると枯れちゃう、だから再植林として次の苗木を植えるけど、こういうカシやウバメガシって、いい切り方してやるとこいつがまた育って、10年後、20年後に切れると。これが樵木林業の特性で、同じ木をずっと若返りさせながら循環林にしていく技術」
「樵木林業」は2018年、日本森林学会が認定する「林業遺産」に登録されました。
しかし、林業をする人が減り伐採をしなくなると、木が大きくなりすぎて病気になりやすくなると吉田さんは話します。
「ナラ枯れ」、そして山は不健康に
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「内側が変色してるでしょ?これまさに、ナラ枯れのナラ菌ですね。輪染みの内側がナラ菌が繁殖してて」
「ナラ菌を感染させる虫が『カシノナガキクイムシ』。略して、通称『カシナガ』。それが体につけてるナラ菌が木に繁殖して、木が内側から枯れていくと」
木が成長して直径が10cmを超えると、ナラ菌に感染しやすくなります。
今、徳島の山の多くは伐採が行われず不健康になっていると、吉田さんは危惧しています。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「僕らが切る前って、全部こんな感じですよ。真っ暗でしょ?地面見ていただくと草も生えてないし、全然健康じゃなくて、世代交代が止まっちゃってるので老木が多い」
炭窯での炭づくり
昔、この辺りで炭づくりが盛んに行われていた時の証を見せてくれました。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「これ昔の『炭窯』ですね、戦後とかまでは使ってたんでしょ。昔って重いウバメガシを機械で運ぶことができなかったので、基本的に炭って山の中で焼いて、炭で軽くして運び出す」
吉田さんは町内に新しく4つの炭窯を作り、備長炭を生産しています。
炭を作るためには、まず原木を窯の奥に入れた後、窯の入り口で火を焚いて乾燥させます。
そして、蒸し焼き状態にすると「炭化」が行われ、炭ができます。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「窯出しの瞬間は、見てて美しいので好きです」
吉田さんの窯では、原木を入れてから取り出すまで3週間ほどかかるそうです。
(四国の右下木の会社 製炭責任者 椎名洋光さん)
「一番熱いところで1000℃ぐらい。普通の炭は炭化が終わったら鎮火させて、冷ましてから取り出すのが黒炭、よくバーベキューなどで使われてる炭がそうなんですけど。備長炭は、最後このように温度を一番あげて不純物を取り除いて取り出す、そして鎮火させたものが、やっと備長炭になります」
備長炭は硬いのが特徴で、品質のいいものは叩くと金属のような高い音がします。
(四国の右下木の会社 製炭責任者 椎名洋光さん)
「これはいい炭。これは悪い炭、締まってないんですよ。ナラ枯れ被害木ですね、これはまさに」
備長炭は、高知県や和歌山県などが主な産地で、作るには職人の経験と勘が必要です。
しかし、吉田さんは、それまで大きさや形がバラバラだった窯を一定の大きさに揃えたり、窯の温度をスマートフォンで見られるようにするなど、炭作りを簡単にして作る人や生産量を増やしたいと考えています。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「美波町も徳島もどんどん人口減ってるので、全て人手頼りだったら続かない産業が多すぎると思う。私たちはこの産業をいかに未来、10年後、100年後もと考えると、人頼りだけではなくて、やっぱりいろんなツールを使って持続可能にすることをやらないと」
海外で増えているという備長炭の需要
徳島県佐那河内村にあるヨーロッパ料理の店です。
調理にはガスや電気だけでなく吉田さんの備長炭も使っていて、なくてはならないものになっています。
(ラームス 錦野真弘オーナーシェフ(30))
「シカとイノシシをミンチにして、つくねのようにしたもの。炭の場合は遠赤外線があるのでじっくりとじわじわと火が入っていきます。徳島県産のワイン用ブドウの枝を。これは電気やガスではできないですね、こういったものを入れることが。備長炭なので入れることができて、香りをつけることができます」
イタリアで修業経験があるオーナーシェフの錦野真弘さんは、今、海外で備長炭の需要が増えていると話します。
(ラームス 錦野真弘オーナーシェフ(30))
「炭に関したら今、どんどん(需要が)増えてますね。なのでイタリア人の友人から炭の使い方教えて?とか、どんな炭台がいいの?とか、けっこう聞かれますね。なので備長炭って言ったら、向こう(海外)の人にも通じます」
コンセプトは「地炎地食」
吉田さんは、地域の燃料で地域の食材を調理して味わう「地炎地食」をコンセプトに販路を広げています。
これまで、県内外の飲食店など10店舗に3トン以上を出荷してきました。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「炭は10種類以上、規格があります、長さ、太さ、形状によって。飲食店によって使いたい炭が違う。店の営業時間の長さとか、調理人の慣れによって使いたい炭が違うので」
吉田さんの会社では、1箱12kgを1万5000円から2万円で販売しています。
吉田さんは、樵木林業が復活することで森に価値を見い出し、関係人口が増えることを期待しています。
(四国の右下木の会社 吉田基晴代表取締役(52))
「森で食べられる人、森の周りで暮らせる人が増えると、少しでも県南の人口減少とかにもプラスに働くんじゃないかなというふうに思って。樵木林業の復興にかける想いというのは、地域回復とか地域再生にもつながるんじゃないかなと」
地域活性にかける男の熱い想いが、過疎の町に新たな道を切り開くかもしれません。
最終更新日:2024年6月25日 20:44