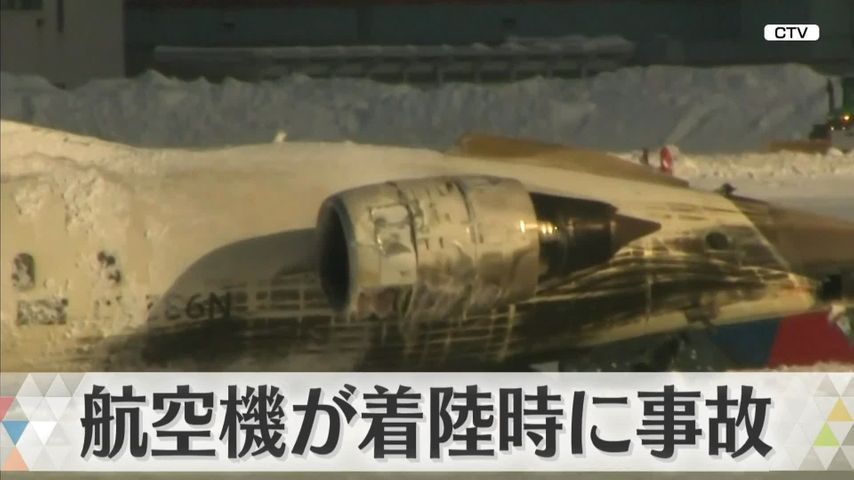津波の脅威を伝えるモノ 震災遺構・荒浜小

2011年の3月11日に起きた東日本大震災から9年。現在までにわかっている死者は、1万5899人。そして、2529人の行方が未だにわかっていない。
宮城県仙台市の荒浜小学校は、仙台駅から車で30分の場所にあり、東側およそ700メートル離れたところには、海がある。
9年前のこの日、4メートルを超える津波がこの学校を襲った。津波は2階まで押し寄せ、児童や教職員、地域の住民320人が孤立。一日かけヘリコプターで救助された。
この学校は、津波の脅威や教訓を伝えるため、震災遺構として一般公開されている。現在は、新型コロナウイルス対策のため休館となっているが、特別に許可をもらって入らせていただいた。
この学校が私たちに伝え続けることとは……。市來玲奈キャスターが現地から伝える。(上)
◇◇◇
9年前のこの日、この学校を4メートルを超える津波が襲った。津波は校舎の2階にまで押し寄せた。児童や教職員・地域住民ら320人が、3階と4階に避難。ヘリコプターで一日かけ救助され、全員無事だった。いま居る4階には、当時の避難の状況の様子が、いまも鮮明に残っている。
学校のガイドも務める、荒浜小学校・嘱託職員の鈴木憲一さんに聞く。
──実際にどのような活動を?
「仙台市の職員として、震災後、この荒浜地域を含む仙台市の沿岸地域で被災された方々の生活再建に関わってきたこともあり、いま、この施設の公開が始まって以降、施設の管理と案内業務を担当している」
──黒板に、番号と名前が書いてある。どのような状況?
「9年前のきょう、この校舎に避難してきた地域の皆さんの名前を記入したものです。もともと荒浜には当時、5つの町内会がありまして、この教室は荒浜西町内会の皆さんが避難する教室になったわけですが、もともと10班編成がされていたために、ここに、避難していた方、名前書いてね、ということで、書いたものが残っている」
──どなたが、いつ避難されたか、わかるようになっている。
「誰が避難されたか、誰がまだ来られてないか。ひと目でわかるように記録した」
──こちらの毛布は?
「あの日は、雪の舞うような非常に寒い日だったこともあって、電源がすぐ切れてしまったこともあって、16人の先生方が、なるべく避難所の方をあたためてあげたいという思いで、学校中にあったあらゆる布類を持ち出してきて、かけてあげた」
──黒いものも……
「たぶん音楽室にあったものだと思うが、遮光カーテンですよね。それと一番下の赤白は、あの日の一週間後に卒業式が予定されていましたので、そのために準備されていた紅白幕。こういったものも利用されたという」
──当時、廊下はどのような状況?
「住民の皆さんは3階と4階に分かれて避難したわけですけど、当時の71名の生徒は4階に集められたということで、夕方から屋上でヘリコプターの救出が始まるわけですけれども、その際に順番待ちをした」
隣の教室には、震災の前の町や、地震発生以降の避難と救助の状況をあらわした展示も。そして、その教室の真ん中にも、津波の脅威がわかるものが……。
「この時計は、校舎の後ろにあった体育館に展示してあった大きな時計。あの日、津波が襲ってきたことで、電源が失われてしまい、止まってしまった。これが残っていたことで、この学校を津波が襲った時刻を証明しているような時計になってしまった」
──15時55分、地震が発生した時刻ではない。
「約1時間後にこの荒浜地区を津波が襲った。それを証明しているということになると思う」
また、1階の教室には、津波の爪痕がわかる教室がある。
(「津波の爪痕残る教室」に続く)