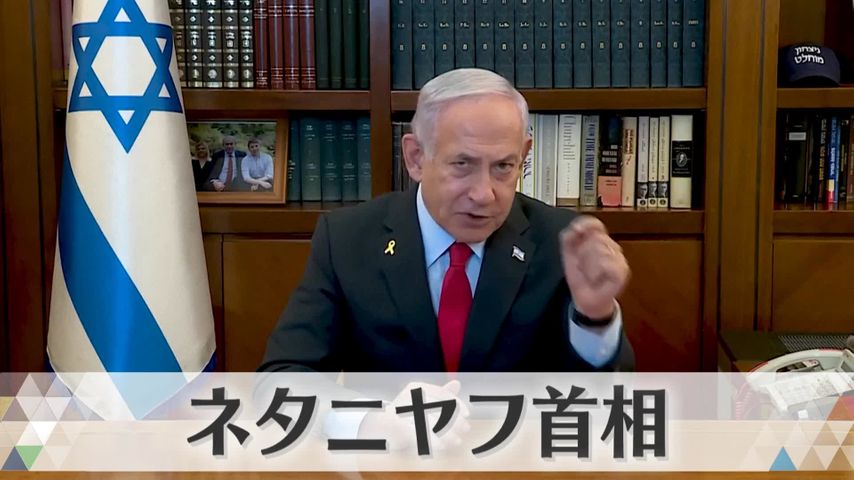【盛岡市】人工衛星使った上水道管漏水点検実証実験結果まとまる 下水道管点検にも最新技術導入へ
対策が求められる水道管です。1月28日に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故は下水道管の老朽化の問題を改めて浮き彫りにしました。その中、盛岡市では下水道ではないんですが、上水道の水漏れ、漏水のチェックを人工衛星を使って行う実証実験を昨年度から2年間行い、その結果がまとまりました。市では今回のような事故を防ぐため、今後、下水道管の点検にも最新の技術を導入する考えです。
全国的に上水道管、下水道管の老朽化が進んでいて、埼玉県八潮市の道路陥没事故のような事故は、いつどこでも起こりうるのではないかと懸念されています。
盛岡市上下水道事業管理者 長澤秀則上下水道局長
「八潮市の場合は下水道ではありますけれども、何か聞くところによると復旧にですね、3年ぐらいかかるのではないかという大変な120万人の生活に影響を及ぼすという大変な事故、いわば災害の様相を呈してきているのかなというふうに思っておりまして。従いまして、今後ですね、我々としても対岸の火事ではなくてですね、予防保全型のきちっとした普段から定期点検をしっかりして、直すところはしっかり直していくと。そういった取り組みをですね、やっていかなければならないなというふうに、改めて強く感じたところですね」
盛岡市全域の上水道は1600キロと、盛岡から九州福岡市までの距離に匹敵する配水管が伸びています。漏水・水漏れのチェックは専門の職員8人が歩いて行っていて、一回りするのに2年かかるということです。
盛岡市はおととし6月から人工知能・AIを使った調査を導入できないか実証実験を行いました。これは人工衛星から照射した電磁波の反射特性の違いを使い、水漏れの可能性がある範囲を半径100メートルまで絞り込んで特定する仕組みで、県内では初めての取り組みです。
2年がかりで行った実証実験の結果、人工衛星で漏水の恐れがあるとされた581か所について、実際に職員が従来の方法で点検したところ、48か所で漏水がありました。的中率は8.3パーセントで、目標としていた30パーセントには届きませんでした。
盛岡市水道維持課 佐藤努課長
「今回の結果はちょっと下回ったというかですね、想定よりも下回ったので、実際のどういった形でこういう現象になったのかという検証を踏まえてですね、ちょっと新たな視点で追跡調査という形で調べてみたいなとは思っています」
今回の実証実験は上水道に新たな技術を導入したものですが、盛岡市では八潮市の事故を受けて、下水道管の点検にも新たな技術を取り入れていく考えです。
盛岡市上下水道事業管理者 長澤秀則上下水道局長
「下水道の方につきましては、できれば来年度ですね、今回の事件を受けまして、水中ドローンのようなですね、機械を新たに導入して、点検というのは基本は人が下水道管の中に入って目視をするのが基本になっておりましたので、そういった最新の技術を導入をいたしまして、点検の効率化を図りたいなというふうに思っております」
上水道、下水道とも老朽化が進む中で、それを点検する人手不足は深刻です。人工衛星やAI、ドローンなどの新たな技術で調査点検を行い八潮市のような事故を防ぐことが何よりも求められています。
また、盛岡市では今回の八潮市の事故を受けて、国が5年に一度と定めている下水管の点検を前倒しして、近く緊急点検を行うことにしています。