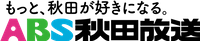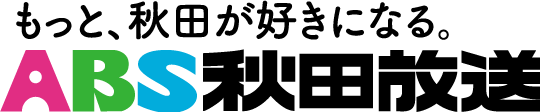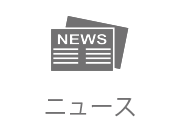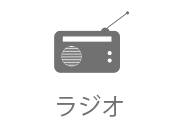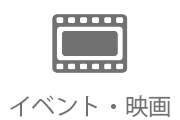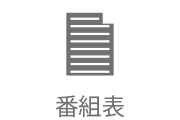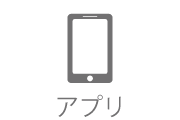秋田県立大学が東京大学と共同研究へ 多岐にわたる連携で秋田の活性化と地方の未来創造を目指す
秋田県立大学は、温室効果ガスの売買や新たな農業技術の創出について、東京大学と共同研究を進めることを決めました。
東大の持つ先端知識と、県立大学が持つ地方の知識を掛け合わせ、秋田の活性化につなげるとともに、地方の未来創造を目指します。
14日は、県立大学の福田裕穂学長と東京大学の相原博昭副学長などが出席し、連携と協力に関する包括協定を結びました。
県立大学 福田裕穂 学長
「地方を活性化することなくして、今後の日本の発展はあり得ないと考えています。まさに、地方から日本全体へと、そういう流れが本当に必要な時期に来ている」
連携するのは、森林の二酸化炭素の吸収・貯蔵の測定法を開発し、温室効果ガスの売買・カーボンクレジットの信頼性確保についての研究や、再生可能エネルギーの開発や利用の研究、それに、日本海側の気候変動を見据えた、新たな農業技術の創出など、多岐にわたります。
また、学生や教職員の交流も行う予定です。
東大の持つ先端知識と、県立大学が持つ地方の知識を掛け合わせ、秋田の活性化につなげるとともに、地方の未来創造を目指します。
東大が地方の国公立大学と共同研究を含む包括協定を結ぶのは、県立大学が初めてです。
東京大学 相原博昭 副学長
「我々としては、日本の大学をリードする立場にあると思っていますので、その課題、地方の課題に対しても、どれだけ貢献できるかというのが常に自らも問うところありまし、それから問われてきたということがあります。それを具体的に行動に起こすと」
県立大学 福田裕穂 学長
「日本の中心にいて、そういう人たちが何を考えているか、学生たちが何を考えているか、何を目指しているのか、これを知ることが、この秋田県立大学の学生にとっては、非常に大事で、そういう中で、自分たちのこれからやる、10年後20年後の将来、これをもっときちんと見つめることができるようになるのではないか」
今後は、東大の総長も参加して、地方の行方について話し合うシンポジウムの開催なども計画しているということです。
また、両大学は、学生同士が協力して、地方を舞台に、革新的なアイデアで事業を展開するスタートアップ企業の誕生にも期待を寄せていました。