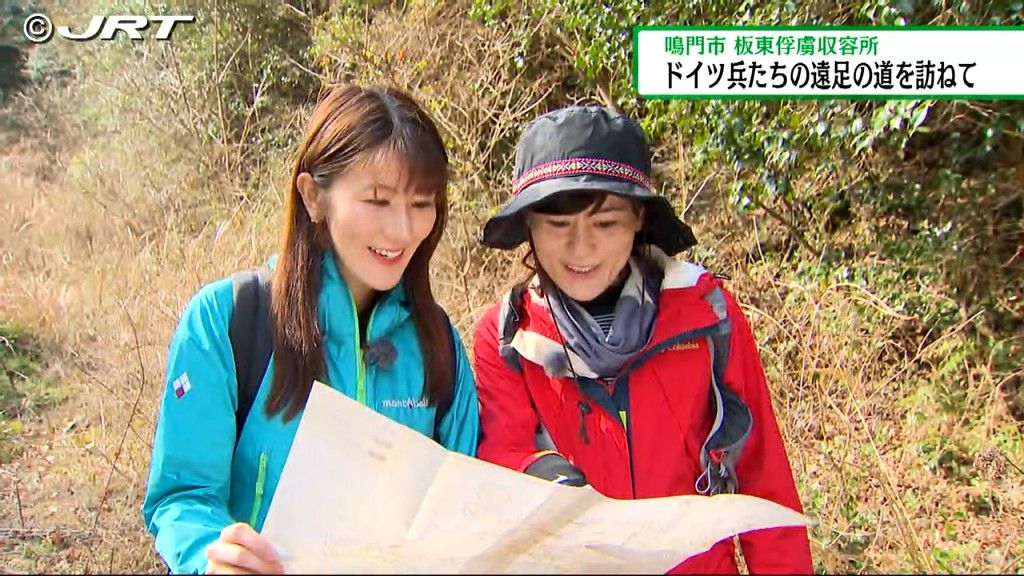鳴門市の板東俘虜収容所のドイツ兵捕虜たちが辿った遠足の道へ【徳島】
■鳴門市に約100年前に開設された板東俘虜収容所
この板東俘虜収容所で第一次世界大戦で捕虜になったドイツ兵、約1000人が3年近くを過ごしました。
捕虜たちは人道的な運営方針の元、自由で文化的な活動が許されていたため、収容所はベートーヴェンの交響曲第9番のアジア初演の地となりました。
鳴門市ドイツ館の館長森清治さんです。
森さんは当時の捕虜は収容所の外にも比較的自由に出ていたと話します。
(鳴門市ドイツ館 森清治 館長)
「この当時はまだ、日本は戦争に関係する国際条約を批准していましたので、それに基づいた捕虜の管理をしていきます。そういった中で、いろんな余暇の活動をという事で演劇であったり、スポーツであったり、遠足というものが盛んにおこなわれるんですけども」
森館長によると、当時の捕虜は自分たちドイツ人だけで『遠足』に出かけていました。
度々山を越えて鳴門市北灘町の海岸を目指していたそうです。
時には「汚れた足を洗う」と言いながら海岸で海水浴を楽しんでいたんだとか。
記録に残っている遠足の回数はというと…。
(鳴門市ドイツ館 森清治 館長)
「遠足は85回ほど、1週間にひどかったら4回くらい行っているので」
(野口七海アナウンサー)
「こちらは約100年前にドイツ兵捕虜が作った地図です。よく見てみると、堀江や撫養などローマ字で地名が書かれています」
(鳴門市ドイツ館 森清治 館長)
「中にピンクで書いている地名がいくつか見えると思います」
(野口七海アナウンサー)
「でもこれは日本語じゃないので読めないですね」
(鳴門市ドイツ館 森清治 館長)
「ドイツ兵たちがそのエリアエリアで、自分たちでつけた名前というものをここで表現しています。彼らが行っていたルートを見ると、ここに『炭焼き魔女の谷』であったり『炭焼き魔女』っていう風に書かれているんです。何か興味わきますよね?」
(野口七海アナウンサー)
「わきます」
『炭焼き魔女』。ドイツ兵捕虜が名付けた地名の場所には何があるのか?探しに行くことにしました。
■さっそく遠足へ… 『炭焼き魔女』とはいったい
(野口七海アナウンサー)
「という事で、今から約100年前にドイツ兵捕虜が遠足で出かけていた所にこの地図をもって行ってみたいと思います。行きましょう!」
案内をしてくれるのは、森館長と学芸員の長谷川純子さん。
長谷川さんは西洋美術史が専門で2016年からドイツ館で資料の研究をしています。
(学芸員 長谷川純子さん)
「板ヶ谷にという集落が昔あったので、少し先に行くとその集落跡が残っているのが見えるかなと思います」
長谷川さんたちは以前から捕虜たちの『遠足』について調査していて、『炭焼き魔女』には2年前に1度訪れています。
道はまるで魔女が行く手を阻むかのように草が生い茂り、至る所で途切れていました。
遠足が行われていた当時の道は、鳴門市大麻町から北灘町に抜ける道の一つで、人の往来が多かったものの、今では道そのものが自然に帰ろうとしているようでした。
(野口七海アナウンサー)
「うわ祠がある…」
朽ちかけた『祠』。かつてこの場所を人が通っていた証です。
捕虜たちも遠足の無事を祈ったのでしょうか。
■山道の中の人工物 かつての集落の痕跡
山道を歩くこと約1時間、人工物が見えてきました。
(野口七海アナウンサー)
「なんか石垣みたいなものがありますね。」
(学芸員 長谷川純子さん)
「この辺、昔集落があったところなんで」
森館長によると集落には1980年代頃まで人が住んでいたそうです。
(学芸員 長谷川純子さん)
「魔女の痕跡が見えてきました」
(野口七海アナウンサー)
「え、魔女の痕跡が?魔女が住んでいた場所だ」
(学芸員 長谷川純子さん)
「当時、炭を焼いていた場所」
地図の『炭焼き魔女』は、山の中に炭焼き窯が並んでいた場所だったようです。
炭はかつて炊事や暖房用に消費された家庭用燃料の代表でした。
そのため、当時は山間部などで至る所に炭焼き窯が作られ、炭が生産されていました。
(野口七海アナウンサー)
「この道を通る時に炭を焼いていたおばあさんかな、それが魔女に見えたのかな。それにしても、ドイツ兵捕虜の方ってすごく素敵な名前を付けますね。童話に出て来るみたいな」
(学芸員 長谷川純子さん)
「本当にそう思います」
地図には他にも『レンブラントの道』や『闘牛士』『水の精の谷』など少しファンタジックな地名が付けられていました。
さらに私たちは捕虜が行ったという標高300メートル地点の『海見峠』を目指しました
(学芸員 長谷川純子さん)
「こちらが海見峠」
残念ながらこの日は峠から海を見る事が出来ませんでした。
この100年間で、植物が成長し、当時と見え方が変わってしまったようです。
(野口七海アナウンサー)
「ドイツ兵捕虜も当時ここから海を見て母国を想像していたのかもしれないですね」
(学芸員 長谷川純子さん)
「場所はここではないですが、少し離れたところからの瀬戸内海の写真も残っていまして、収容所の新聞の中でも瀬戸内海だったり、そこに浮かぶ島々にすごく心を癒されたという記事も残ってます」
捕虜たちの遠足では約40キロを1日で歩いたという記録も残っています。
逃げ出してもおかしくないような自然の中の遠足、その中で一人も脱走した捕虜がいなかったというのも板東俘虜収容所の誇るべき記録なのかもしれません。