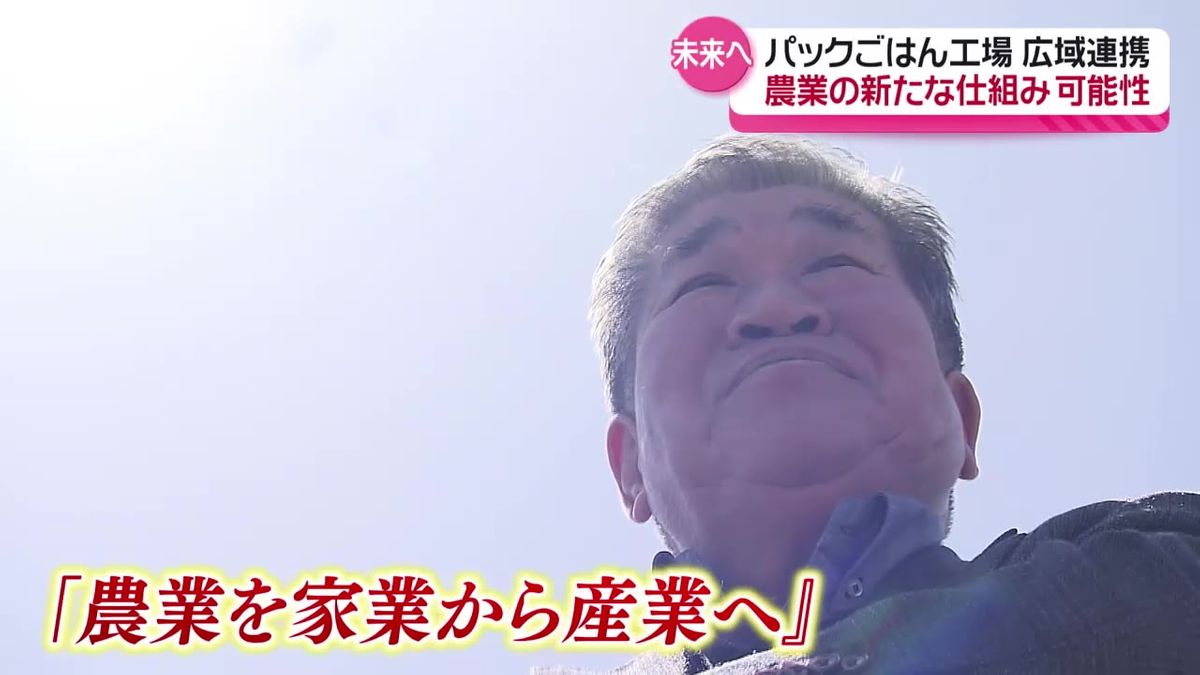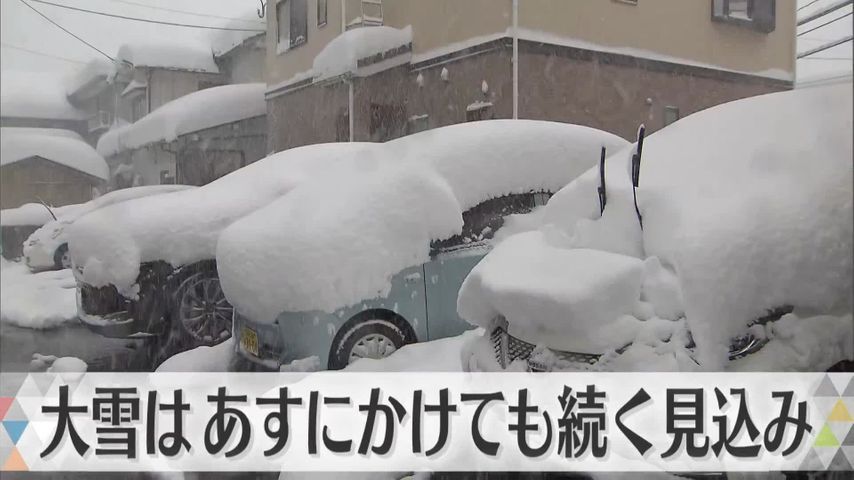【特集】続くコメ騒動 農家の現状は?今後の農業の進むべき道は?減反政策と戦い続けてきた男性を追う
日本人の主食「コメ」についての特集です。
かつて国内・そして秋田の田んぼで行われた「青刈り」。
生産調整・減反を進めるため、まだ青いうちに稲が刈り取られていました。
2018年にコメの過剰生産を抑制するための減反政策は廃止されましたが、その後も転作に補助金を出すことで、実質的なコメの生産調整は継続されてきました。
コメの価格が高止まりし、コメ離れも懸念される中、国は、備蓄米の放出を決めたほか、生産調整から増産に政策転換する方針です。
コメ作りの現場では何が起きているのか。
そして、向かうべき道とは。
減反政策と半世紀以上戦い続けてきた男性の取り組みを追いました。
■高値によるコメ離れの懸念
涌井徹さん
「全外食事業者は輸入米を入れる方向で動いています」
「で、消費者は高いからコメ離れ、めん・パンの方に移っていきます。いまの米価が今年の秋も続いていけばもう(輸入米が)オープンにどんどん入ってくる」
毎年この時期、農業従事者などを対象に開かれている研修会であいさつした、大潟村の農家・涌井徹さん。
コメの可能性を追求し続ける開拓者の一人です。
55年前に入植した大潟村で、コメの生産から加工・販売までを手がける農業法人を立ち上げたほか、いまはパックご飯の製造に力をいれています。
涌井さん
「日本の農家にとっても不幸、消費者にとっても不幸」
「いま現在はみなさんが迷惑する、困る米価である。誰も得をしていない米価だ」
高騰するコメの価格。
あきたこまち60キロの取引価格は、近年、1万3000円から1万5000円台で推移していたものの、去年の秋から急激に値を上げ、12月末時点の速報値では、前の年の同じ時期と比べて1万円あまり高い、約2万7000円でした。
コメの価格は高止まりしていて、農業の現場に大きな波紋を広げています。
JA秋田中央会 小松忠彦 会長
「いまご飯茶碗1杯のお米の価格が40~50円程度と試算されますが、この価格が果たして高いのかどうかを考えてみていただきたいのです」
高値による「コメ離れ」を懸念したJAは、生産者が置かれた状況を理解して、県産米を買ってほしいと呼びかけています。
JA秋田中央会 小松忠彦 会長
「高騰して高い。買い控えという状況にありますけども、お互いに苦しい中でも支え合うという気持ちを持っていただいて、食べていただいて(農家を)支えていくんだ」
国による備蓄米の放出は、一時的な対症療法に過ぎないと考えている、大潟村の涌井さん。
価格高騰の根本的な原因は、国が長年コメの生産を抑制してきたことによる生産力の低下だと指摘します。
涌井さん
「55年間コメの生産を抑制することが続いてきた」
「生産の現場が、親子代々、コメを作るな、コメを作ってはいけない、コメを作ればコメが安くなる、農業が継続できないと言ってきた。しかし、55年間、減反(生産調整)したけども、結局、農業が継続できなくなったわけね」
「需要と供給のバランスをとろうとした政策に、いま限界がきた」
■減反政策との戦い
コメを余分に作らせず、抑制することで、米価の安定を図ってきた日本の農政。
国策による大規模農業のモデル農村として生み出された大潟村では、反発する農家がコメの過剰作付けを行い、当時の県知事が村に乗り込んで事態の鎮圧に乗り出しました。
小畑勇二郎 知事(当時)
「まだまだ甘い考えを持っている。そんな事態でないということを私の口からはっきり言いにきたのです」
「それ(過剰作付け)は大潟村の破滅ですよ。腹の底からあなた方に言っておく」
涌井さん
「なぜ自分の田んぼで自由にコメ作りができないのか」
涌井さんは、自主自律を求めて、仲間4人とともに会社を設立。
夢と希望が持てる農業を掲げて、消費者に直接コメを送る産直を始めました。
涌井さん
「要するにこれがダメだったら農家を辞めた方がいいなっていうね。そういうつもりでいるのね」
「ここで農業をやって、そしていま一つのこの方向ではないかというのが見えてきたわけよね」
涌井さんは、「ヤミ米屋」と揶揄される中でも、日本の農業を、自立した競争力がある産業にしていかなければ、いずれ立ち行かなくなると考えていました。
農協青年部との討論(89年)
「(過剰)作付けされている皆さんは、全国の食管法を守って減反をしようとしている人たちの、不満ながらやっている部分について、秩序を乱しているということだけは認識されていただきたい」
涌井さん
「そういう秩序を正確な秩序だと思っていること自体が、あなた宮城県だったかな、非常に宮城の農民は不幸だと思いますね。本当に皆さん減反を進めていって、このままいって嫁さんが来るような農家できますか?本当にできると思いますか?それを聞きたいわ。本当に自信を持っていまの制度を続けていって、政策を続けて、素晴らしい農業きますか?」
その後も国が推し進める減反政策と戦い続けた涌井さん。
4年前には、輸出を視野に入れて、急成長を続けるパックご飯の事業に参入しました。
涌井さん
「(コメを)国内消費依存しているから、生産ができない。世界をマーケットにしたら生産いくら作っても足らない、いくら作っても」
「よく私の嫁さんに70になったら終活しろと言われるのね。で、私の終活というのはね、これなんだよ。とにかく倒れるまで走り続けてね、倒れても前に倒れる。後ろに倒れない。倒れても前に倒れる。そういうつもりでやってるのね」
涌井さんが近年力を入れて取り組んでいるのが、新たな農業経営の形。
その手本とも言える仕組みづくりの柱になるのが、各地で増えている廃校舎の活用です。
いまは男鹿市にある廃校舎を丸ごと改装して、県内2か所目となるパックご飯の工場を建設しています。
涌井さん
「農業者人口が減ることによって、どんどん面積が集まってくる。もう処理しきれない」
「しかし、農業法人が10社20社集まって連携して、地域の学校(廃校)を使って、ライスセンター・加工工場を作るとしたら、いっぱいあるわけ。チャンスは1人ではできないけど、みんなが集まればできる。農業は、一人で地域を守れないけど、みんなで守るようにするには、やっぱり産業にしなきゃいけない」
「家業という農業が日本の農業を支えてきたけど、これからは産業に切り替えなきゃいけないところにきた」
『農業を家業から産業へ』。
国の政策の転換期を迎える中、涌井さんは、安定的に国民の食糧を供給できる農業の確立を模索しています。
涌井さん
「日本農業がいま成り立たなくなろうとしているわけよね。いまこそ大量に大増産し、余計なものは輸出していく。そして、国内の需給は安定させていく」
■担当記者が解説 コメ政策の転換点
【田村修アナウンサー】
長年、涌井さんの取材を続けている、県政担当の川口大介記者です。
涌井さんもインタビューで話していましたが、コメ余りを前提にした国の政策が限界を迎えたという印象を受けました。
【川口大介 記者】
はい。コメ政策はまさにいま、転換点を迎えています。
近年、食料の安定供給を意味する「食料安全保障」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
日本人の主食のコメの不足、いわゆる「令和の米騒動」を教訓に、安定的に供給できる体制を構築する必要があります。
農林水産省によりますと、稲作の現場では、7割が、後継者がいません。
このまま廃業・引退が進めば、引き受け手がない田んぼが荒れ果てていく懸念があります。
こうした状況から、涌井さんは「この先のコメ作りはいまの延長線上にない」と考えていて、徹底的な先進技術や、収益性を高める多収穫米の導入などを提言し、すでに取り組みを始めています。
また、農林水産省は、転作を誘導する役割を果たしてきた交付金制度について見直す方針を示しました。
涌井さんはこれを「55年間続いたコメの生産調整から増産へのシフト」ととらえています。
そのうえで、担い手不足も背景に、家業として続いてきた農業を産業へと転換させ、維持させていく必要があると話しています。
涌井さんの開拓・挑戦はこれからも続きます。
この先コメをどのように安定的に生産していくのか。
そして、農村と田んぼを維持していくのか。
国の政策の動きを含めて注意してみていく必要があります。