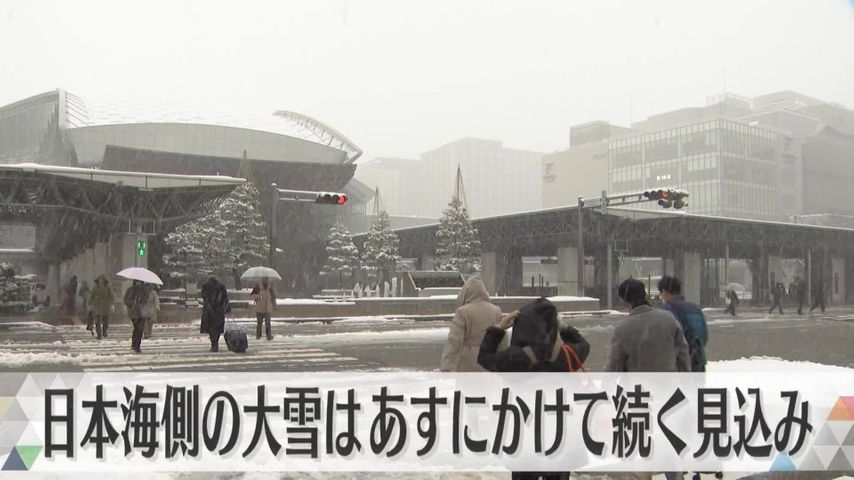特集「キャッチ」87歳の新人記者のデビューに密着 初取材の相手は75歳…どうなる 「ばあちゃん新聞」創刊半年 福岡
公民館に届けられた出来たてほやほやの新聞を、集まったおばあちゃんたちが熱心に読んでいます。そのワケは。
■寄り合いに来た人
「“むっちゃん”がいっぱい映ってる。」
寄り合い仲間の1人、“むっちゃん”が「ばあちゃん新聞」の第2号に取り上げられているからです。
■“むっちゃん”こと麻生ムツエさん(98)
「恥ずかしい。田舎もんで、あんまり人前に出てなかったから。」
御年98歳、大正最後の年に生まれた“むっちゃん”の子ども時代は、茅葺き屋根の小学校に下駄で通学。令和の今とは大きく異なる暮らしぶりでした。
一日の過ごし方についての質問には。
■“むっちゃん”こと麻生ムツエさん
「水曜日がデイサービス、木曜日は休んで、金曜日はここ(寄り合い)。」
1週間のスケジュールが流れるように出てきました。
■寄り合いに来た人
「“むっちゃん”は有名よ。」
気心知れた仲間との集まりが、元気と長生きの秘けつといいます。
去年11月に創刊され、月に1回、第6号まで発行された「ばあちゃん新聞」。作っているのは、高齢者の力を町の元気につなげる地元の会社「うきはの宝」です。
現役世代の悩みをおばあちゃんたちが一刀両断する「人生相談」に「ばあちゃんレシピ」。カラー12ページの紙面に盛りだくさんの企画が詰まっています。
■新聞の読者(55)
「人生相談コーナーを見ると、自分たちはすごく悩んでいるけど、年配者にとってはしてきた経験をスパッと言うからすごいと思う。」
■新聞の読者(21)
「ぼっとん便所の話。僕が生まれた頃はもうない。全然知らないことを、この新聞という媒体を通して知ることができるのが、すごく貴重だと思います。」
「ばあちゃん新聞」は1部330円。
その売り上げから、取材を受けてくれたお年寄りに2000円から5000円の報酬を支払っています。
創刊号の発行は1000部でしたが、今では月に3000部まで伸びました。
この日は、第3号の発行に向け、編集長の大熊充さんが取材現場に。1人のおばあちゃんが同行していました。
87歳の内藤ミヤ子さん。「うきはの宝」で食品加工の仕事をしています。
■うきはの宝 社長・編集長・大熊充さん
「僕がカメラマン、(ミヤコさんが)ライター。」
■うきはの宝 スタッフ・内藤ミヤ子さん(87)
「ライターになれるかなあ。」
実は、「ばあちゃん新聞」の記者としてデビューすることになったのです。
40代の頃、労働組合の婦人部の仲間とせっけん工房を立ち上げたことが忘れられない思い出だというミヤ子さん。現在の趣味は家族旅行です。
■ミヤ子さん
「ばっちり!」
週末には、地元の子ども食堂で腕を振るいます。
人と話すことが好きで、“おしゃべり上手”な一面もあります。そんなミヤ子さん、「ばあちゃん新聞」の取材を受け、「ばあちゃんレシピ」や「人生相談」のコーナーに登場していました。
■ミヤ子さん
「自分の得意なところはみなさんに伝えて、利用してもらえたらいいなと思います。」
それが今度は、取材を“受ける側”から、“取材する側”に。編集長の大熊さんから、“おばあちゃん記者第1号”に抜てきされました。
初めての取材相手は、ブルーベリーや柿を育てる75歳の足立善男さんです。
■ミヤ子さん
「懐かしい写真も持ってきましたよ。」
■足立善男さん(75)
「せっけん工房ですか。」
■ミヤ子さん
「せっけん工房の。ほら。」
善男さんの母親と仲が良かったことから、まずは昔話で場を和ませるミヤ子さん。
■ミヤ子さん
「ブルーベリーは、まだあの面積で作っているんですか?大変ですね、収穫が。」
■善男さん
「この前の大雨で土砂が…。」
■ミヤ子さん
「あそこの園全部ですか。」
■善男さん
「園の横の山です。」
善男さんが営む農業に話題を移しましたが、取材を意識するあまり、話をつなぐことができません。
■大熊さん
「ミヤ子さん、足立さんの今を聞いて。」
■ミヤ子さん
「今は?」
■足立善男さん
「今度15日から韓国に。ソフトテニスの親善試合。ねんりんピックやら、いろいろな大会に出ている。」
編集長の大熊さんのアドバイスを受けながら、少しずつ善男さんの魅力を引き出しました。
■ミヤ子さん
「難しかったです。初めての経験だから、どういうふうに進めていいかも、ちょっと不安だった。取材となるとなかなか難しいなと思いました。」
それでも初めての取材は、第3号と4号をまたぐ連載となりました。
「75歳の現役テニスプレイヤー」という、ミヤ子さんが引き出した情報も、ちゃんと書かれています。
■ミヤ子さん
「善男さんってこんなに幅広く活動しているんだなって、皆さんに知られたらもっとやりがいがあると思います。生きがいを感じました。少しでも役に立つことがあるかなと。」
年を重ねて見つけた新たな生きがい。“おばあちゃん記者”はきょうも現場を楽しんでいます。