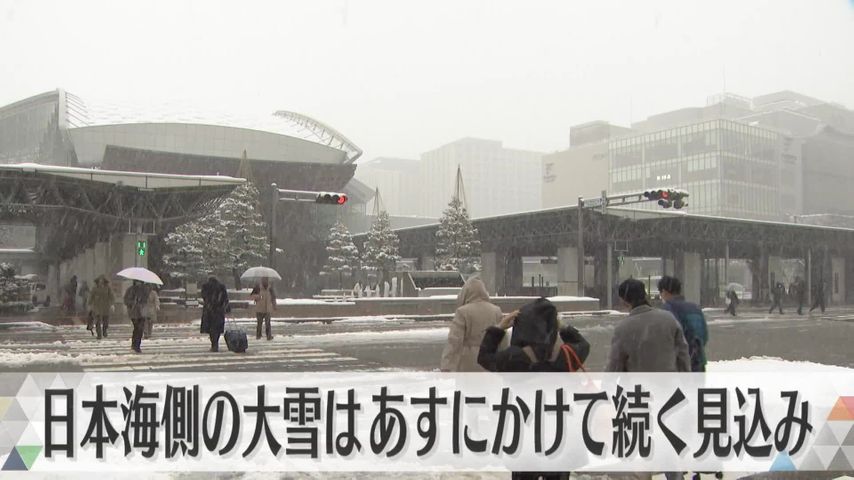原発廃炉作業はいま…3号機内部に初カメラ

東日本大震災から、来月で7年。福島第一原発では、廃炉に向けた作業が進められているが、作業はどこまで進んでいるのか。震災後、初めてカメラが福島第一原発・3号機建屋の内部へと入った。
◇
「廃炉」に向けて、いまも毎日6000人が働く福島第一原発。26日、事故後初めて、その最前線である3号機の建屋内部の取材が許された。1号機・2号機・3号機から300メートルの所まで、いまは私服で入ることができる。
放射線量が高い区域では、全身防護服に着替え、手首の隙間にもテープを巻いて厳重に防護する。徒歩で坂を下り建屋に近づく。3号機の横にある建屋は、まだ津波の跡が生々しく残っていた。
目指すのは、3号機建屋の最上階。その最上階には何があるのだろうか。
◇
7年前の2011年3月14日、3号機は激しく爆発し、屋根や壁が崩れ落ちた。原子炉から溶け落ちた燃料が固まり、その上にある燃料プールには、大量の燃料棒が残された。
事故から7年。その現場に、初めてカメラが入る。
エレベーターの手前でカメラを止めるよう言われた。テロ対策のため、原子炉建屋の出入り口は全て撮影が厳しく禁止されている。しかし、中での録音だけは許可された。聞こえてきたのは、ZARDのヒット曲『負けないで』。作業員を励ますための選曲だ。
エレベーターは、地上37メートルの屋上に到着。すぐそこは海だった。隣の4号機には、いまも水素爆発の跡が残っている。そこから外階段を上り、かまぼこ型のドームの入り口を入ると、体育館の様に広い3号機の最上階だった。
まずは、大量の燃料棒が残されたままのプールに向かう。いま、この燃料プールはほぼ28℃と、7年たってかなり冷えたが、まだ少し発熱しているという状況が続いている。
プールの縁で放射線量を測ると、約700マイクロシーベルトとかなり高く、1時間余りで一般の1年分の被ばく限度に達する強さだ。中には、566本の燃料棒が残されている。再び地震や津波が襲えば大事故につながる危険性があり、一刻も早く取り出す必要がある。
そのためには最上階のガレキの撤去や除染が不可欠だったが、高い放射線量の中での作業は困難を極めた。
◇
除染を行った東芝エネルギーシステムズ・林弘忠さん「除染はなかなか思い通りにいかない。しかも遠隔(操作)だったので、(原子炉建屋最上階で)有人作業が本当にできるのかなと」
事故翌年の2012年9月に撮影された映像で、水が見えるのが燃料プール。遠隔操作でアームをあやつり、プールの縁にひっかかった巨大な鉄骨を取り除こうとするが、滑り落ちてしまう。大量のガレキを一つ一つ、遠隔操作でつまみ上げる、気の遠くなる作業。
さらに、作業員が放射線を遮るための、鉄板で囲まれた避難所もつくられた。こうしてようやく、人が入って1~2時間程度作業できる環境が整ったのだ。
◇
最上階にそびえる巨大な装置。巨大なクレーンにぶら下がっているのは、自在に動く2本の手を持つ、特殊なマジックハンド。計画されている取り出し方法では、これでプールの中の燃料棒をつり上げ、特殊な容器に移し、その容器を別のクレーンで地上に降ろし、運び出すのだ。
周囲より放射線量が高かった場所の真下には、原子炉があり、この下には溶け落ちた核燃料が固まっている。燃料棒の取り出しが終わっても、その先にはさらなる難関が待ち構える。