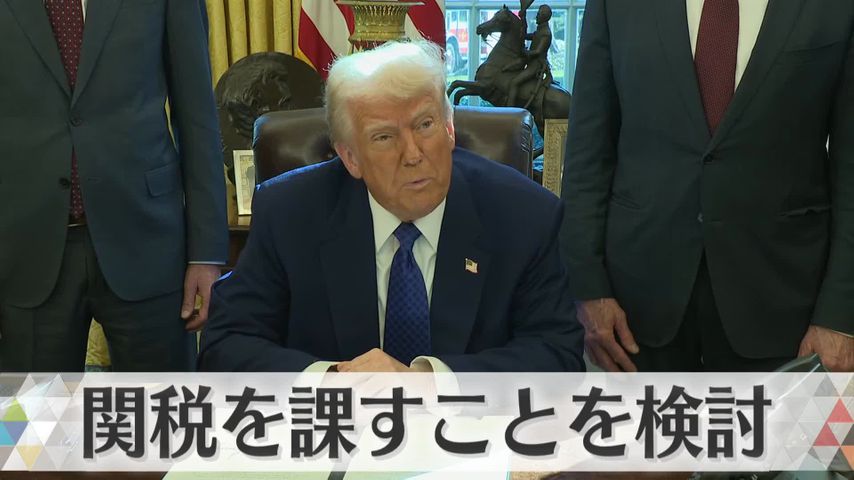「人と人とのつながりを大切に」 集団移転に向けた戸沢村蔵岡地区住民の思い
戸沢村の蔵岡地区は去年7月の大雨で集落全体が甚大な浸水被害を受けました。度重なる水害に苦しんできた蔵岡地区はいま、「集団移転」に向けた検討が続けられています。蔵岡の水害の歴史とふるさとを離れることになる住民たちの思いを取材しました。
集団移転に向けて計画が進められている戸沢村蔵岡地区。69世帯が生活していましたが、去年7月の大雨でその多くが仮設住宅などに移り、現在も地区内に暮らしているのはこれまでのおよそ3分の1の21世帯です。
除雪作業に汗を流していた小野セツ子さん(77)。被災直後は避難所で生活していましたが、現在は自宅に戻り、息子と2人で暮らしています。
小野セツ子さん「今までおはようと言ってきた人がいないからなんとなく寂しい。あそこに車来てるなと思ったら自転車で行って『何しったや?』って言う。まさかこんな。蔵岡はいい所だったお祭りからいろんなものから」
村が実施した集団移転についてのアンケートには、「賛成」と回答しましたが、複雑な思いを抱えたままです。
小野セツ子さん「一人残ったって世の中つまらないし、できればここから行きたくない気持ちは10あるうち10に近い気持ちだけどやむを得なく。これからどうなるものだか」
小野さんはいまから57年前に大蔵村から蔵岡地区に嫁いできました。蔵岡地区では水害が毎年のように起きていたと言います。
小野セツ子さん「嫁いできた翌年の昭和44年(1969年)の7月末に水害があってそのときは15センチくらい水が上がった。昔の話を聞かされると昭和19年(1944年)に河原の国道が出来る前に家があったそう。それが流されたのが一番大きかった」
1944年・昭和19年当時の水害の記録を示す文書がかつて地区の公民館に残されていました。
「七月二十一日正午浸水最も甚だしく屋内四尺餘に及びたり午後五時半頃には屋内五尺に及びたり阿鼻騒然として言語に絶するものあり七月二十三日傷病者の調査を為す三十余名の患者在り」
蔵岡公民館はこれまで、地域の行事などに利用されてきましたが、去年の大雨で浸水被害を受け、現在はほとんど使われていません。
公民館には蔵岡の水害の歴史を示す写真が残されています。
蔵岡地区会山崎昇会長「平成16年(2004年)の水害の状況です。一級河川の角間沢川から排水を行っているがなかなか追いつけず冠水している状況や住居の被害が見受けられる写真」
蔵岡地区は最上川沿いに位置する低い土地であることや大雨が降ると地区内を流れる角間沢川が増水し、いわゆる内水氾濫が起きやすいなどの地理的要因から、度重なる水害に悩まされてきました。
これは2004年の水害時のニュース映像です。この大雨で道路は冠水し、国道47号は全面通行止めに。集落の住宅およそ40戸が浸水被害を受けていました。
公民館には、昭和19年の水害を記録した文書の原本や地区のさまざまな記録が保管されていましたが、去年の大雨でその多くが浸水したため、災害ごみとして処分せざるを得なかったといいます。
蔵岡地区会 山崎昇会長「これをぶら下げてお客さんを呼び込む今まで使っていたその名残りですね」
一方、地域の祭りでかつて使われたこの道具は浸水を免れ、残されていました。
巨大な紙風船を冬の夜空に浮かべる「蔵岡紙風船まつり」。
地域住民で作る「蔵岡ふるさと塾」が2006年から20年近く続けてきたイベントです。毎年冬になると地域住民が集まって紙風船を制作してきました。ことしは大雨被害による避難生活の影響で住民が集まりづらくなり例年通りの規模ではイベントを行うことができなくなったといいます。
蔵岡地区会山崎昇会長「避難生活の中でどうしても顔を合わせる機会が少なくなってその分人間関係が希薄になりつつある」
それでも住民たちは、ことしも祭りの実施を模索しています。紙風船の代わりに花火を打ち上げるなど、例年より規模を縮小したかたちでのイベントの継続を目指しています。
蔵岡地区会山崎昇会長「小規模ながらやり切ることによって人と人とのつながりが活動を通じてつながっていく今を生きている私たちの使命ではないか」
避難生活が続く中で住民どうしのつながりをいかに守っていくか。集団移転に向けた蔵岡地区が直面する大きな課題です。