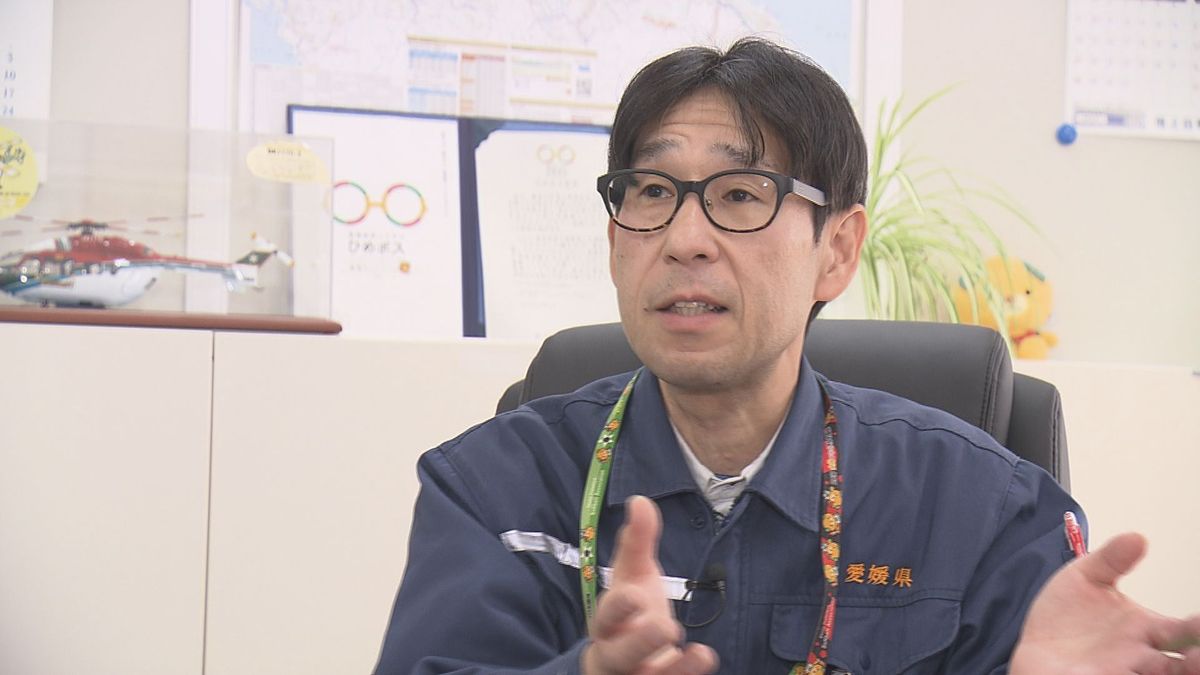能登半島から学ぶ〝次の災害から命を守る”ために応援職員が伝えたいこと

「西日本豪雨で受けたご恩を返すために」
元日に発生した能登半島地震を受け愛媛県からも2018年西日本豪雨での災害対応の経験を活かした、積極的な被災地支援が発災から1か月を過ぎた現在も行われています。
愛媛県の中村知事は「西日本豪雨で受けたご恩を返す。そして、この応援の経験は南海トラフ地震の対応にも必ず我々の役に立つ」と応援の意義を語ります。
愛媛県の第一陣として石川県珠洲市に応援で入った県職員に、能登半島で見たもの、そして次の災害で命を守るために我々が知っておきたいことを聞きました。
南海放送 解説委員 白石紘一
これが自分たちの未来の姿か 能登と南海トラフを重ねて―
石川県珠洲市の災害対策本部でのサポート業務にあたるため派遣された愛媛県防災危機管理課の佐々木一光主幹。
応援に入った時は災害の発生から間もない時期で、庁内や関係機関との連携がうまく取れていなかったことから、情報共有態勢の整備などに尽力したということです。
「南海トラフ地震で、愛媛県もこうなるんだ…」
佐々木さんは市役所に向かう道で悲惨な状況を目の当たりにし、まずこのことが脳裏をよぎったと言います。
地震の揺れと津波の被害が一度に押し寄せ、破壊された街並み。自分たちの住む街の未来の姿が想像されたのです。
想定されている未来の大規模災害からどのように命を守り、生活をつなげていくのか。能登半島地震での教訓から学びわたしたちも自分事として備えを進めていかなければなりません。
孤立した地域、でも地域力は孤立していなかった
佐々木さんは珠洲市大谷地区で、愛媛でも大切にしたい教訓を学んだと言います。
大谷地区は道路の寸断により孤立しましたが、避難所に物資を持っていくと、世話役の人が避難所以外に避難している人にも声掛けをして、食料や水、灯油を配ってくれていたということです。
そこでは行政が介入しなくても、ひとつの避難所に物資を届ければ地域の人たちが自分たちで支え合う環境が整っていたのです。
この地区では普段から住民同士のコミュニティが出来上がっているため、空間的な孤立に陥ったあとも、人々が普段通り互いに助け合っていて、人間関係はまったく孤立していなかったと言います。
一方、孤立をしていなくても人とのつながりが希薄な地域では、避難所にいない人に物資を提供するような助け合いの意識が薄く、避難者が孤立しているケースもあったと言います。
佐々木さん:「命を守るのは自助だが、自ら守った命を守り続けるには共助の力がないと、やはり一人では難しい」
普段から会話できる人が地域にいることで精神的な孤立や負担を軽減することもでき、被災後に精神面での健康状態を維持することに役立つことが考えられるため、地域のコミュニティづくりが重要だと言えます。
防災グッズは「備えているだけ」では使えない
佐々木さんは珠洲市役所に設置された簡易トイレで、ある親子の姿を見かけたと言います。
「子どもがぐずって泣いていたんです。『こんなトイレじゃできない』と」
そこに設置されていたのは和式トイレでした。母親が使い方を教えるものの、和式を利用したことのない子どもにとっては難しかったようです。
珠洲市の教育長からも「トイレの洋式化が進み、和式トイレを利用したことがない子どもが多いためトイレカーがあるなら提供してほしい」と同じような相談を受けたということです。
この相談を受け、愛媛県内で調整し、八幡浜市から珠洲市の直小学校にトイレカーが派遣されることになったと話します。
佐々木さんは、この珠洲市での状況を見て、例え防災グッズを備えていたり、行政から物資を配ったりしたとしても、普段使ったことのないものを、災害時になったからといって、いきなり使うことは難しいと指摘します。
トイレだけではありません。防災食も同じで、味が合わなかったり、アレルギーがあったりと日頃から試していないと、いざという時に食べられないという恐れもあるのです。
避難グッズを持っていても使えるかどうかは別の問題。
▼備えているものを実際に使ってみて使い方を知っておく、自分に合うかを確認しておく。
▼ローリングストックで、できるだけ日常の延長で備えを進めておく
▼平時でも災害時でも使えるフェーズフリーグッズを備えておく
避難生活で苦労しないよう、平時に行動を起こしておきたいポイントです。
「逃げる」という 何よりも大事な 命を守るための行動
佐々木さん:「能登半島地震では、思ったよりも津波の人的被害は出ていない。実際みなさんが高台に逃げているということ。逃げるという行為ほど、命を守るのに有効な避難方法はない」
「逃げる」ということは簡単なように思えますが、実際に災害時に行動するのは難しいことです。正常性バイアスなどの要因から避難をしない、ためらう人もいます。
東日本大震災でも愛媛県の第一陣として、宮城県の避難所に応援に入った佐々木さんは、「津波は何も残してくれない。思い出すらも。津波が引いても亡くなった人を探すことすらできない」と津波による死の悲惨さに触れながら、県民の避難の準備を呼び掛けます。
【日頃から津波避難で確認してほしいこと】
▼どこに逃げるのか、逃げるのにどのくらい時間がかかるのか把握する
▼土砂崩れや倒壊家屋で避難路が塞がっていることもあるため複数の避難場所を確認しておく
▼避難路を塞がないよう、自分の家も社会インフラのひとつだという意識で耐震化をしてほしい
▼避難で持っていくものや、バラバラに逃げてもどこに集合するか家族や地域で話し合っておく
▼いつどこで起こるかわからない。夜間の避難経路なども確認を
愛媛県の想定では南海トラフ巨大地震で県内では最大 約1万6000人が亡くなるとされていて、被害を少しでも減らすためには、ひとりひとりが行動に移すことが求められます。
佐々木さん:「地域がやる気になれば、自分がやる気になれば事前の準備は誰にでもできる。備えを我が事として今日から出いいので少しずつ前に進めてほしい」