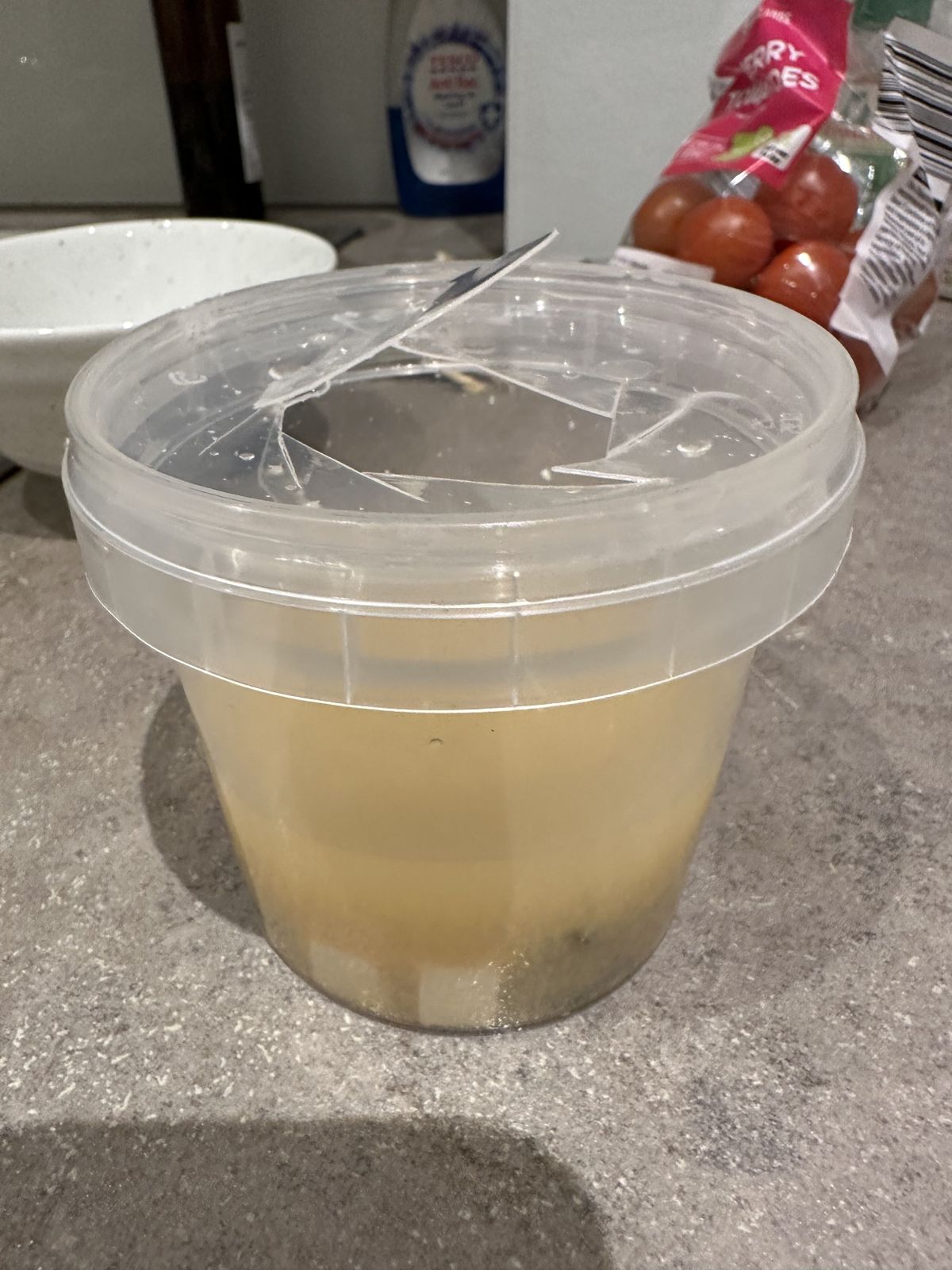【コラム】「焼き鳥とお好み焼き」のしたたか戦略と「世界一マズい!?」イギリスの食事情【ロンドン子連れ支局長つれづれ日記】

G7広島サミットもようやく終了。各国首脳の中で、一躍日本人のハートをつかんだのがスナク首相だった。最初に訪れた東京では渋谷の居酒屋で焼き鳥に舌鼓、岸田首相との夕食会では広島カープのロゴ入りの真っ赤な靴下を披露した。さらに広島名物のお好み焼きを焼くスナク首相のはじける笑顔に、「気さく」「庶民的」と日本人の好感度は一気に高まった。
ところが、スナク首相の出自をひもとくと、「庶民的」とはとても言いがたい。英オックスフォード大を卒業後米スタンフォード大で学び、投資会社でバリバリ働いたあと、富豪の娘である奥様と結婚、夫婦で莫大な資産を所有し、イギリスの長者番付にもその名を連ねている。
日本ではすっかり人気者となったスナク首相だが、国内では低支持率にあえいでいる。5月の地方議会選挙で惨敗、来年にもおこなわれる総選挙に向けて日々SNSを更新し、アピールに余念がない。「焼き鳥」と「お好み焼き」は“きらきらエリート”のイメージを覆し、庶民にアピールする格好の材料だったに違いない。人心をつかむには、まずは「胃袋」から、というところだろうか。
胃袋と言えば、支局長という職業柄、人と会食をする機会も多いのだが、「イギリスの食べものはマズい」という定説は、もはや過去のものと言っていいと思う。過去駐在された先輩方に「色々駐在したけど、イギリスは世界一マズい!」とか、「醤油の小瓶を持ち歩いて、レストランに入ったら『肉も魚も味付けはけっこう』と厳命すべし」とか、「フィッシュアンドチップスは一度食べれば二度と見たくないシロモノ」などと脅されていたため、イギリスの「食」に対して過剰な恐怖心を抱いていたのだが、もっか6割程度の勝率で「美味しい店」に出会っている気がする。
彼らも自覚していて、「モダンイギリス料理」と、「モダン」の冠をつけて、「もう昔のまっずいイギリス料理じゃないもんね!」とアピールしているところも多く、そうしたところには創意工夫と革新の風が感じられる。だが、それは「相応の金額を支払った場合」である。
個人の生活に話を移すと、シングルマザーという属性上、しかたなく息子を全寮制の学校に入れているため、学費がこの上なく高い。とにかく、高い。いまだに「February」の綴りが書けない息子に、毎学期英語の補助教師がつけられてしまう。これが授業中は35ポンド。授業外だと45ポンド。日本円にしてそれぞれ6000円強と8000円弱、である。
請求書を見てぶっ飛び、「なんとかもう少しサポート時間を減らしていただいて・・・」とおずおず頼んでみるも、「ダメです。教科書がまともに読めるようになったら考えます」とにべもない答え・・・勢い、鼻血の出そうな教育費を捻出するため、一人暮らしの母は自炊するしかない。ところが、である。スーパーに行ってみると、1か月前より物の値段が大幅に上がっている。4月の消費者物価指数によれば、食品や飲料の価格が4月までの一年間で19.1%の上昇と45年ぶりの高水準。生活に身近なもののインフレが止まらない。
そんななか、もっかイギリスの「マイベストレストラン」は家から歩いて2分のトルコ料理店である。入り口でたっぷりとひげをたくわえたおじさんが炭火でじゅーじゅーと肉を焼いていて、その香ばしい香りが道にあふれ出てくるので、前を通るたびに入りたくなる。
ちなみに息子の「マイベスト」はその向かい側にあるイスラムマーケットの店頭で焼いている丸焼きチキン、7ポンド也。鶏まるまる一羽を串に刺して、ぐるぐる回るロースターで一日中焼き続けている。20羽ほどの鶏が、焼かれた順に香ばしい色に仕上がっていくのを見るのは楽しい。そして、一日の終わりには、黒焦げになる前にちゃんと全部売り切れているから不思議だ。
こちらはもう何度も買っているので、常連になりつつある。行くたびに「今日のは、今までの中で一番美味しいよ!」と過去最高を更新してくるので、どこまで高みをめざすのか楽しみだ。
私の住んでいる地域は、日本人の不動産屋さんいわく、「日本で言えば足立区の北千住みたいなところ」とのことで、国際色豊かだ。道を歩いている6割は中東系、3割がロシア・東欧系かもしれない白人、そして1割がアフリカ系とアジア系、という割合だ。
人種が雑多で子どもも多く、幼児が操る「はじめてのキックスケーター」(もちろん電動ではない)によくぶつかる。仲良しのアルジェリア人のドライバーさんいわく、「ちょっと行ったところで、ヤクの売買とかやばい傷害事件とかがよくあったけど、今はデカいショッピングセンターができたおかげでなくなった」とのことで、まあまあ安全なエリアでもある。
アパート(こちらではフラット、と言う)がいくつも集まった集合住宅で、一応、入り口に車止めのゲートはあるのだが、左右の隙間から宅配のオートバイがゆうゆう出入りしているので、あまり意味はなさそうだ。なんせ赴任したのが12月29日でまったく不動産屋があいておらず、仕方なくインターネットで決めた物件なので、不動産屋さんとも大家さんとも、一度も顔を合わせたことがない。
入居当初からの不具合(途中の割れ目から水がじゃあじゃあ出るシャワーのホース、曲がったままトイレットペーパーが落ち続けるペーパーホルダー、4個中前列2個の火がつかないガスレンジ、一度スイッチを入れたらアパート全体のヒューズが飛ぶオーブン・・・等々)は4か月たった今も、直らないままだ。
必需品のガスレンジについては、12通もメールを書いたのだが、「そのうちに」みたいなのらりくらりした返事が返ってくるばかりなので、支局のイギリス人カメラマンに相談したところ、秘策を教えてくれた。
「だったら勝手に自分で修理工をよんで、修理費を来月の家賃から引きますけど、いいですね!」と送ってみろ、とのこと。それはちょっと強引では・・・と危ぶんだのだが、彼はその手で成功したのだそうだ。教えられた通りメールを送ってみると、「あなたには家賃を勝手に減額する権利はありません!・・・が、すぐに修理工を手配します」とのこと。
さすが郷に入っては郷に従えだ、と感心していると、翌週、修理工がやってきた。いや、正確には月曜日に約束したのが火曜日になり、水曜日になり、結果的に木曜日にやってきたのだが、数分ガス台を眺めたあと、「今日は部品も道具もないから無理!数日後に連絡する」と言って手ぶらで帰って行った。そして2週間経った今も、連絡はない・・・
ことほどさように、不便・不親切・不愉快、と「不」の連鎖が続くイギリス生活だが、それもコインの裏表、と実感する出来事があった。
「イギリスあるある」の一つに、「開けられないシリーズ」というのがある。ケチャップやジャムの瓶のふた、ボトルキャップ、恐ろしい力で締まっていて、とてもかよわい48歳女子の手には負えない。おまけにラップは、引き出した途端にとっかかりがどこかに消えてしまい、さんざん格闘した結果として全体の3分の1はゴミ箱の藻屑と消える。
ある夜、仕事帰りに疲れ切ってスーパーに寄ると、入り口にでっかく「SuperValue!」の文字。見ると、9ポンドのワインが5.95ポンドになっている。これは買うしかない!とほくほくしながらレジに運び、家に帰っていざグラスに注ごうとすると、あかない・・・日本から持ってきた奥の手、「瓶あけられます」のシリコン製アイテムを使ってもあかない・・・ボトルを両足ではさみ、両手を使って踏ん張っても、あかない・・・そのうち頭に血が上り、脳内出血を起こしかねない様相を呈してきた。
しかたがない・・・恥をしのんでアパートの管理人さん(とは名ばかりの門番さん)のところに駆け込んだ。「すみませんが、ボトル、開けていただけませんか?」と小窓からボトルを差し入れると、門番のアブドゥルさん、恐怖にゆがんだ形相で後ずさった。何か危険物と勘違いされたのだろうか、と「あ、コレ、ただのワインですよ。夕飯と一緒に飲もうと思ったらあかなくて・・・」とあわてて笑顔をつくると、「違う、ダメ・・・」と今度は泣きそうな顔になっている。あ、と思い当たった。「もしかして、宗教上の理由、とかですか?」と聞くと、「はい、私は厳格なイスラム教徒です。ですから、こうした酒類の瓶は触れません」とまじめな顔で答えが返ってきた。
「もうひとりのジェイコブさんが当番だったらな~」と内心がっかりしていると、アブドゥルさん、駐車場を指さして「あそこにいるピザの配達人に頼んでみては?」と言う。おお、それは名案。見るからに屈強そうなアフリカ系の若者である。ワインボトルなぞ、ちょちょいのちょいで開けられるに違いない。さっそく走って持って行くと、たぶん「まかせとけ!」みたいなことを言って(早口で聞き取れなかった)バイク用の手袋を脱いでさっそく取りかかった・・・が、うんともすんとも言わない。再びチャレンジ。だんだん脳内出血を起こしかねない様相に・・・そのときである。天の声が降ってきた。
「どうしたの?」あちこち見上げてサーチすると、同じアパートの5、6階あたりの窓から金髪の若い女性が顔を出している。「ボトルが開かないんです!」「上がってきなさいよ。65番の部屋、ノックして」配達人も地獄に仏とばかり、「よかったね」とボトルをさっそく手放した。アパートに走り込み、エレベーター(こちらではリフト、という)が来るのももどかしく、階段をかけ上がる。65番だから6階に違いない、とあたりをつけるが・・・ない。よく考えると私の家は71番なのに3階だ。どういう論理かよくわからないが、イギリス人が算数ができないと言われる理由はこのあたりにあるのだろうか、などと邪推しながら探し回ると、目的の家は5階にあった。71番が3階で、65番が5階。意味がわからない。
「そのボトル?ちょっと待ってて」青い目をした可愛らしい女性である。まもなく長身のブルネットの男性をともなって戻ってきた。「旦那がこういうの得意だから、待ってて!」待っている間、「日本から来た記者だ」と自己紹介すると、「私はサリー。ロンドン生まれのロンドン育ち、もっか求職中、よろしくね」と少し鼻にかかった明るい声。「新婚さんですか?」と聞くと、「まあね、そんな感じ」と照れくさそうに笑った。
やがて旦那さんが戻ってきた。「いや~、これは難しかった。キャップこわしちゃって閉められないけど」とボトルを差し出す。見ると、ペンチみたいなもので挟んだのか、ボトルキャップがべこべこにゆがんでいる。「これは今晩中に全部飲んじゃわないとね~」とサリーが冗談ぽく言うので、「半分どうですか?」と差し出すと、「あはは、それ、あたしたちも買ったから大丈夫!目の前のスーパーで特売だったやつでしょ?」と笑う。「あれは買いますよね~」「もしかしてボトルがあかないからSuperValueだったのかもね!」と一緒になって大笑いしながら、ああそうか、と腹落ちした。
「不便、不親切、不愉快」があるからこそ、一緒に笑い合う人との絆が生まれるのだ。彼らはあまり不便を気にしない。単にこの生活に慣れているのかと思っていたけれど、彼らはきっとどこかでわかっているに違いない。ちょっとくらい不便があったって、そんなものは、助けあいとユーモアで吹き飛ばせばいいんだってこと。小さな不便を嘆くのか、それとも誰かと助け合って笑い飛ばすのか・・・イギリス生活は、そんな小さくもたいせつな選択肢を日々与えてくれている気がする。
鈴木あづさ:
NNNロンドン支局長。警視庁や皇室などを取材し、社会デスクを経て中国特派員、国際部デスク。ドキュメンタリー番組のディレクター・プロデューサー、系列の新聞社で編集委員をつとめ、経済部デスク「深層ニュース」の金曜キャスターを経て現職。「水野梓」のペンネームで日曜作家としても活動中。最新作は「彼女たちのいる風景」。