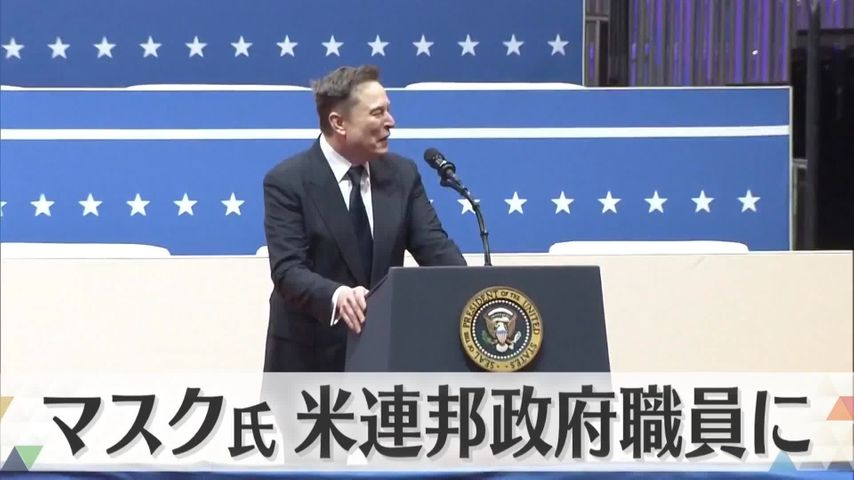「スポーツ界のパワハラ」指導される側も…
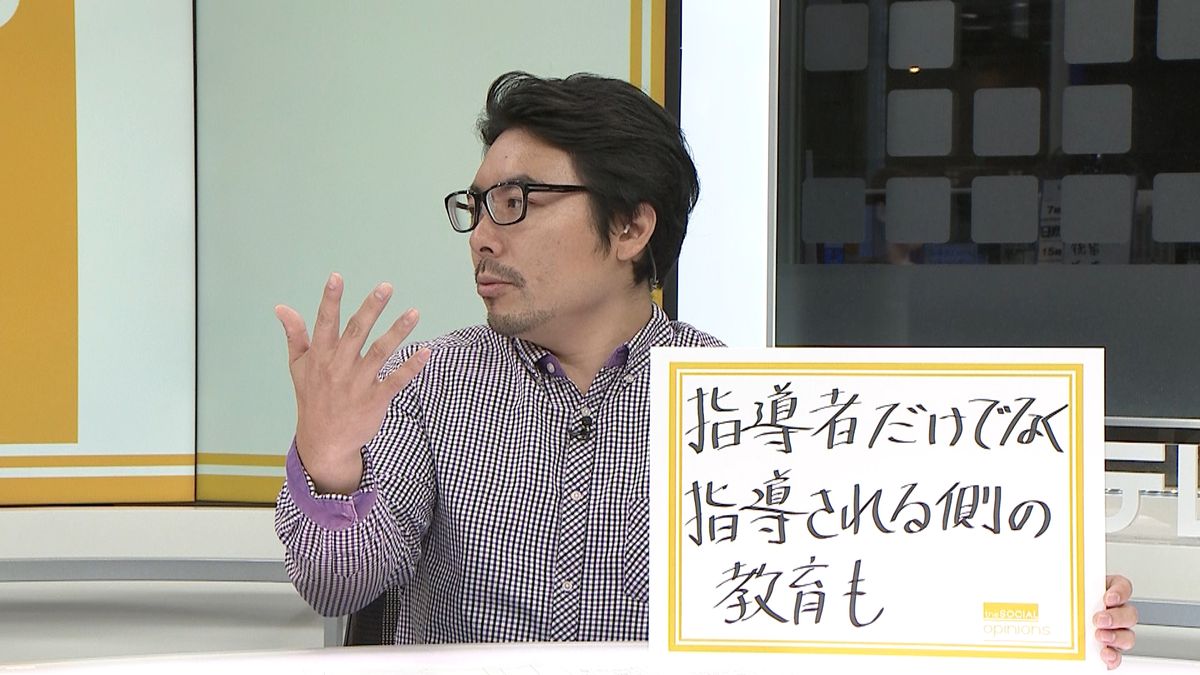
世の中で議論を呼んでいる話題について、ゲストに意見を聞く「opinions」。今回の話題は「スポーツ界のパワハラ」。NEC東京オリンピック・パラリンピック推進本部障がい攻略エキスパートの上原大祐氏に話を聞いた。
スポーツ界で相次ぐパワーハラスメントなどの不祥事について、スポーツ庁はガバナンス強化や再発防止策などについて議論を始めた。
また、超党派の国会議員でつくる「スポーツ議員連盟」は、専門家会合を立ち上げ、法改正や第三者機関の創設なども視野に11月末に意見をとりまとめ、政府に提言することにしている。
ネット上ではこんな意見が見られた。
「次々に出る不祥事に正直、辟易としている」
「ハラスメントって線引きが難しい」
「スポーツに政治や権力が介入してはダメ」
――パラ・アイスホッケーの選手として、パラリンピックに3度出場している上原さんですが、こうしたスポーツ界のパワハラ問題についてどうお考えですか。フリップに書いていただきました。
「指導者だけでなく指導される側の教育も」です。
指導者がダメだからパワハラ、パワハラということがあると思うのですが、指導される側の教育も大切かなと思っています。
心のバリアフリーという言葉を聞いたことがあると思います。これは健常者の方が障害者の方に向けてというケースを考えがちですが、実は障害のある方から健常者への接し方というのも非常に大切です。例えば、障害者が乱暴な言葉を使ってしまうことにより、距離が離れてしまうという部分もあります。
スポーツも同じで、指導者だけではなく指導される側も教育や自分を管理することなどをもっと考えていく必要があると思います。
だからといって効率の良いものというと「AI」とかで済ましてしまうことになってしまいます。やはり人と人とが接することで勝ったときにお互いに喜べたりとか、コーチがこういうことしてくれたから、すごく良かったということもあると思います。
ハードの面だけではなく心と心というハート面での指導というのもレガシーとして残ればいいと思っています。
――暴力ととるか愛情ととるかで全然変わってきますよね。でも、アスリートの方というのは強じんなパワーとメンタルが必要だと思うのですが、すぐにパワハラといわれるこの時代で上原さん自身は、どのようなことが一番大切だと思っていますか。
コーチと選手がコミュニケーションをとって、どれだけ信頼関係をつくれるかが一番重要だと思います。これはチームスポーツの選手同士も同じで、全体的にコミュニケーションをとり信頼関係をつくる、これがスポーツだとと思います。
【the SOCIAL opinionsより】