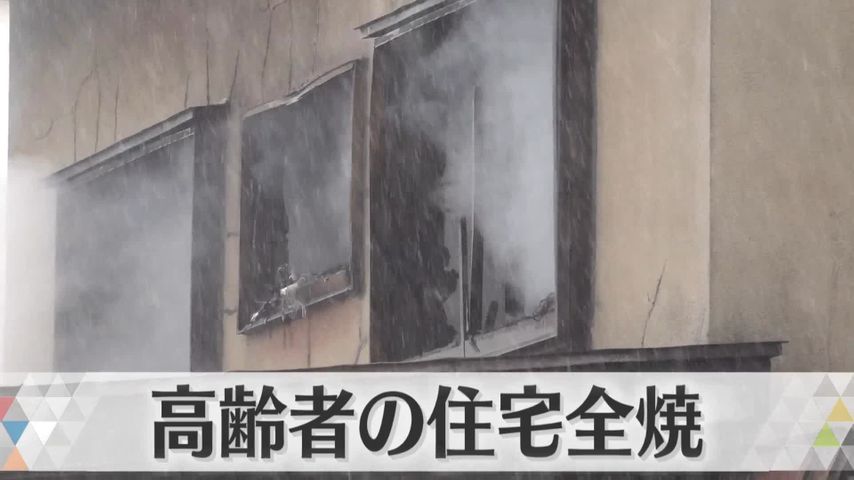精子・卵子提供で生まれた子の「出自を知る権利」保障めぐる法案提出
第三者の精子や卵子の提供での不妊治療のルールに関する法案が国会に提出されました。生まれた子どもの「出自を知る権利」を守るため、提供者の同意が得られれば提供者の情報の一部を子どもに開示することなどが盛り込まれています。
これまで法律がなかった第三者による精子提供や卵子提供で生まれた子の「出自を知る権利」の保障について触れた法案を5日、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党の4会派が参議院に提出しました。
この法案では、精子や卵子の提供者や提供を受けて生まれた子の情報を国立成育医療研究センターで100年間保存するとしています。
生まれた子が成人(18歳)に達し提供者の情報を求めた場合は、身長、血液型、年齢など、個人を特定しない範囲をセンターが開示でき、さらに、提供者が死亡した場合などには、生前に提供者の同意があれば、氏名も開示できるとしています。
さらに提供は、許可を受けたあっせん機関が行い、認定医療機関が体外受精や人工授精を行うこととされていて、代理出産は認められていません。
なお、提供やあっせんによる金銭など利益の授受を禁止し、違反した場合は2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方を科すと明記されています。
また、現行法上では事実婚や同性カップルが精子や卵子の提供を受けた場合、親子関係が認められておらず、提供者を「親」とすることも可能になってしまうため、この法案では法律婚の夫婦のみが対象となっています。
法案提出を受け、第三者の精子や卵子の提供などで子どもを生んだ当事者の団体は、「18歳になるまで提供者の情報を得られないことや、それ以降も提供者の身長、血液型、年齢しか知り得ることができない可能性があり、”出自を知る権利”が担保されているとは言えない」などと指摘しています。
今後、この法律が成立すれば、対象をひろげるために第三者からの提供による親子関係を定めた現行の生殖補助医療法の見直しや、情報開示の年齢など「出自を知る権利」の実態に即したあり方の議論を始めたい考えです。