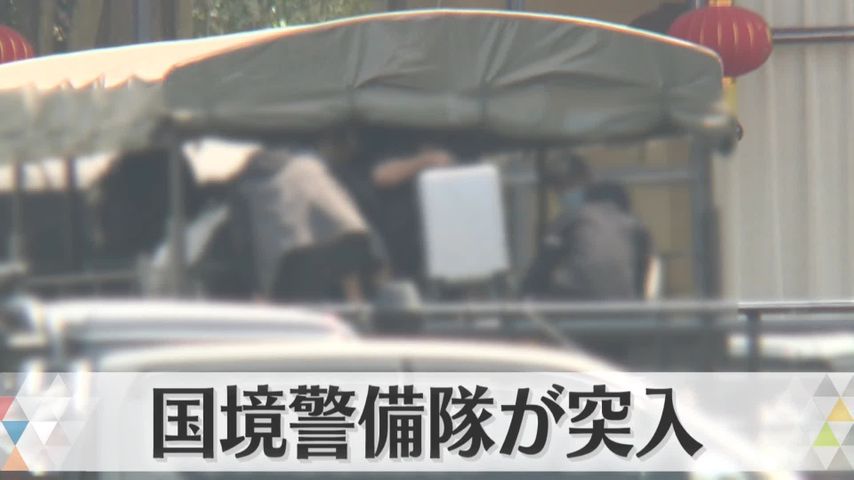【戦後80年】天竜川見下ろす断崖の鉱山…戦時中に過酷労働で命落とした外国人労働者の語られなかった記憶(浜松市)
戦時中、中国から労働者を連れてきて働かせていた鉱山が、浜松市天竜区にあります。過酷な労働で81人の中国人が命を落としましたが地元でも当時を知る人は少なくなっています。戦後80年。鉱山の記憶をたどりました。
3万人の外国人が暮らす浜松市。日本では、今、多くの外国人を受け入れ、労働者の人手不足を補っていますが、時に不安定な立場に置かれた外国人の切り捨ても問題となっています。80年前、外国人労働者を巡り語り継がれてこなかった歴史が浜松にありました。市街地から車で1時間半。その現場は天竜区の山中にありました。
(西尾 拓哉 記者)
「コンクリートの建造物のようなものが見えてきました。骨組みだけ残っているようですが、かなり立派な建物があったことがうかがえます」
天竜川を見下ろす断崖に残されているのは、天竜区龍山町にかつてあった「峰之沢鉱山」の遺構です。主に銅が採掘され、終戦から24年後に閉山となりましたが、選鉱場や鉱山で働く人が住んでいたアパートの跡は今も残っています。終戦後の1955年ごろには“宝の山”と呼ばれ、山の斜面に張り付くように住宅が立ち並び、周辺には「映画館」や「ビリヤード場」もあったといいます。しかし、戦時中中国から労働者を連れてきて働かせていた歴史は、地元でもあまり知られていません。
1月、私たちは、戦時中の鉱山を知る数少ない住民の1人から話を聞くことができました。藤下今朝男さん(87)。咽頭がんを患い、話すには補助器具が必要です。今回、近所に住む岩下勝子さん(80)とともに取材に応じてくれました。
これは、藤下さんが住む集落を上空から撮影した映像。自宅の裏…今はスギ林となっている場所に、戦時中、畑がありましたが、この畑がつぶされ、中国人を収容するための施設が建てられたといいます。当時7歳だった藤下さんは、突然、食べるものがなくなったことをよく覚えています。
(藤下 今朝男さん・87歳)
「サツマイモや麦、穀物なので、その畑をとられるというのは、これからどうすればいいんだと」「主食として食べていたので、一番で出来のいい畑をとられちゃう。余計に悲しみがあった」
収容所にいた中国人は、毎朝、ふるさとの歌を歌いながら鉱山に向かいましたが、やせ細り、いつも空腹そうに見えたといいます。
(藤下 今朝男さん・87歳)
「故郷が懐かしいんだなと思った。幼心にも」「戦争というのは、みじめなものだと、そう感じたね」
戦後、鉱山会社が国に提出した報告書には、中国人に強いた過酷な労働の実態が記されていました。人手不足の穴埋めとして、「峰之沢鉱山」に197人の中国人が連れてこられたのは1945年1月。収容所で与えられたスペースは、畳1畳にも満たない、1人あたりわずか0.56畳。劣悪な環境の中、約4割にあたる81人が病気や栄養失調で命を落としたといいます。岩下さんは、かつて、藤下さんから「山を越えて逃げ出そうとしたが捕まった中国人もいた」と聞かされたことを覚えています。
(岩下 勝子さん・80歳)
「集落の人とそんなに出会うことがないような感じ。捕虜として連れてきた、囚人みたいな扱いなので」「いつも、お腹が空いていて。何でも食べられそうなものを見つけて食べていた」
岩下さんが案内してくれたのは、戦時中、中国人の収容所があった場所です。スギに囲まれた森には、石垣やトイレとみられる跡が、わずかに残っています。50代になるまで「戦時中の鉱山の歴史」を知らなかったという岩下さん。話を聞いた後も、自ら“その記憶”を語ることは避けてきました。
(岩下 勝子さん・80歳)
「かわいそうだったという気持ちが先にたってね。口に出して、あまり食べるものも食べさせてもらえなくて、強制的に働かされて、死んでいったんだよと、そういう語り継がれ方だったので、それを、そういうことがあったよと、人には話したくなかった」「(中国人が)ここを並んで、ぞろぞろゆっくり行くような姿が目に浮かんで、人に語れるものではないなと思う」
異国の地で亡くなった中国人の慰霊を続けている人がいます。
「峰之沢鉱山」があった集落にある「妙蓮寺」の住職・松本尚仁さんです。
集落に建てられた慰霊碑に足を運び、1人でお経をあげています。“中国人の慰霊”を始めたのは先代の住職でした。
(妙蓮寺 松本 尚仁 住職・48歳)
「こちらが先代の加藤住職が遺してくれた慰霊祭の資料です」
22年前に亡くなった加藤仏心さん。シベリアへの抑留経験があった加藤さんは、帰国後、異国の地で亡くなった中国人を弔おうと、日中友好協会の地元支部と協力し慰霊碑を建立…。毎年、夏に慰霊祭が開かれ、40年ほど前には協会の関係者や在日中国人ら約200人が参列したこともあったといいます。20年前に住職となり、初めて「戦時中の鉱山の歴史」を知ったという松本さん。
(妙蓮寺 松本 尚仁 住職・48歳)
「(資料に)強制連行という言葉も出てきますし、それが、自分の近くの峰之沢鉱山で行われていたということにちょっとびっくりしました」
中国人が連れてこられたのは、雪が積もることもあった1月。わずか2か月余りで、81人が亡くなりました。悲劇の歴史を語り継いできた慰霊祭は、関係者の高齢化により、7年前を最後に開かれていません。
(妙蓮寺 松本 尚仁 住職・48歳)
「戦後80年で、その時のことを知る人も、段々、少なっていき、慰霊祭も続けられない状態になってしまいました」「当時のことを思えば、今より寒かったと思います。雪も多く降ったと思いますが、知らない土地に来て強制労働させられた」「いろいろなことを思うと切なくなりますが、その気持ちをご供養のかたちで続けているような状態です」
雪が降った1月。藤下今朝男さんが示したのは、かつて、中国人収容所があった自宅裏のスギ林です。あれから80年。時に、立場の弱い人たちが犠牲となる歴史は、繰り返されています。
(藤下 今朝男さん・87歳)
「内戦をやったり領土を取り合ったりするのかな。不思議で仕方がないよね」「戦争ほど悲惨なものはありません」
ごく一部の人にしか語り継がれなかった鉱山の悲劇。その遺構に、多くの中国人労働者が亡くなった悲劇の痕跡は残されていません。