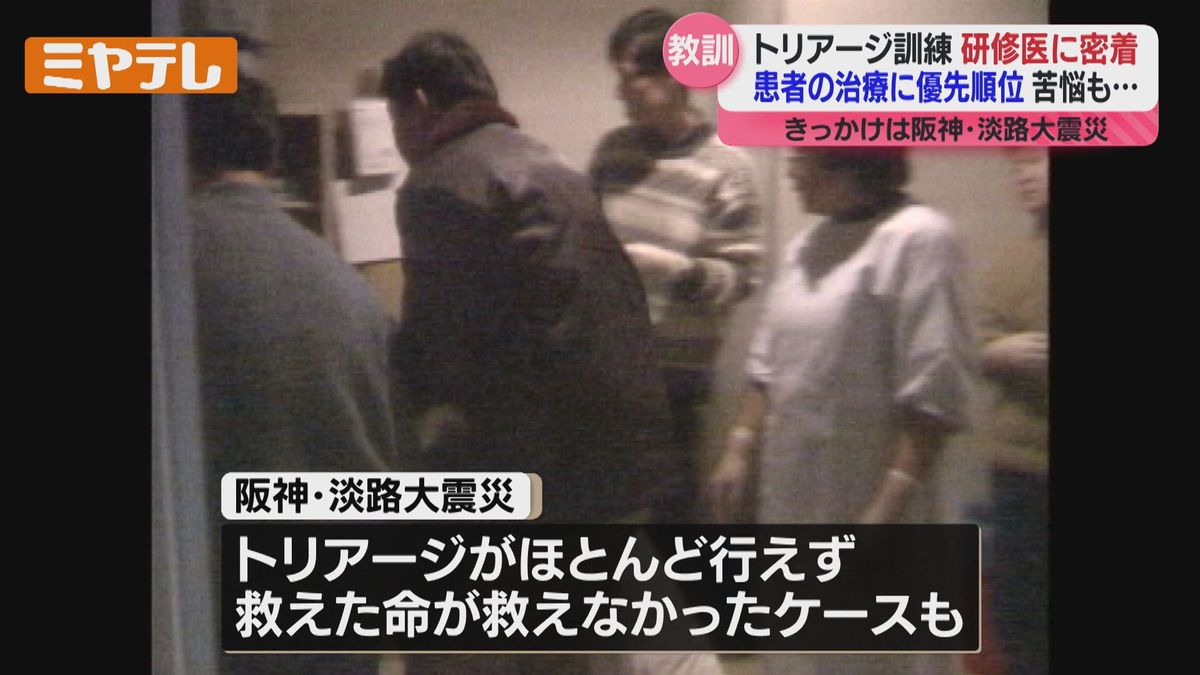【特集】研修医が挑むトリアージ訓練 阪神・淡路大震災の教訓から未来の命を救う〈仙台〉
災害発生時に患者の緊急度などに応じて治療の優先度をつける「トリアージ」は、『阪神・淡路大震災』を機に日本で普及し『東日本大震災』でも行われた。
仙台の病院で、「トリアージ」訓練に初めて参加した研修医に密着した。
訓練「ただいま大きな地震が発生しました」
この日、医師や看護師・事務スタッフら合わせて250人が参加して、災害対応訓練が行われた。
看護師「テントの中にお願いします」
訓練は、宮城県沖を震源とする震度7の地震が発生し、多数の患者が運び込まれる想定だ。
医師「手を握れますか?目を閉じてください、目を開けてください。OKなので黄色です」
最初に、患者の緊急度や症状に応じて、治療・搬送の優先度をつける「トリアージ」を行う。
先輩医師「最初は発声できるかだから、発声と呼吸と。名前しゃべってもらうのはそのあとでもいい」
水色のビブスをつけているのは、研修医。
研修医「お名前・年齢・性別お願いします。しゃべれますか?わかりますか?なしです、赤タグです」
トリアージタグは、緑は歩ける程度、黄色は意識はあるが大けが。赤は治療の緊急度の高い状態、黒は治療不能だ。
医師「時間が短い方が、トリアージとしては成功です」
「トリアージ」の必要性が認識された大きなきっかけは、1995年の『阪神・淡路大震災』だった。
当時は、病院も地震の被害を受ける中、次々と搬送される患者の「トリアージ」がほとんど行えず救えた命が救えなかったケースもあった。
2011年3月の『石巻赤十字病院』の映像。
「トリアージ」は、『阪神・淡路大震災』を教訓に『東日本大震災』の医療の現場で行われていた。
仙台医療センター・江面正幸院長
「災害時は医療資源が限られてくる中で、対応しなければいけない患者は増える。どの患者に対処するのが一番いいかというのが『トリアージ』。どの患者を重点的に対応しなければいけないという考えに、変えていかないと対処できない」
「トリアージ」の後に、患者が運ばれるのは、病院1階の待合室に並べられた簡易ベッド。