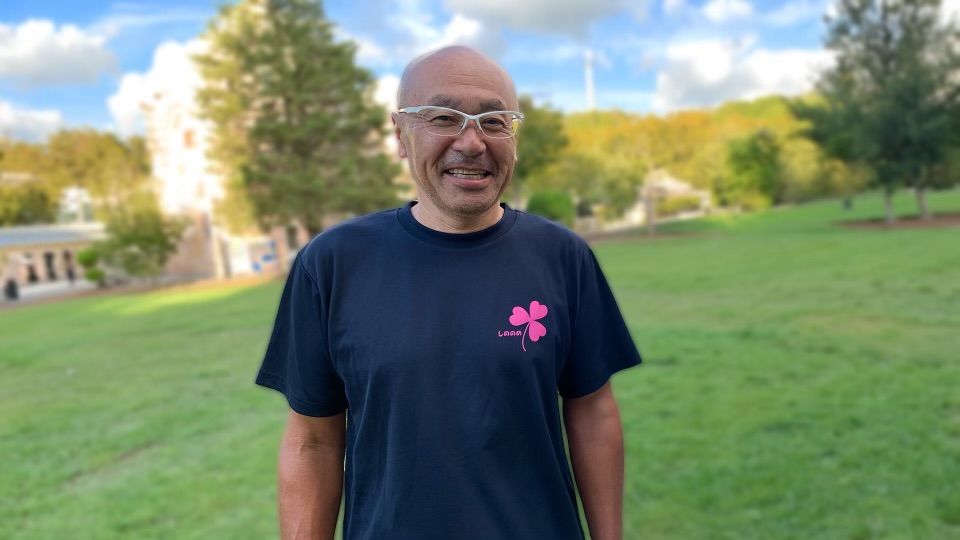「三つ子の魂百まで」ってどう解釈する?抱きグセがつくって本当なの?親世代と祖父母世代の“常識”の違いにみる子育ての今と昔
松山東雲短期大学・市河勉教授(身体的な発育発達が専門)は、「『走る、飛ぶ、しゃがむ、物を投げる、ぶら下がる』などといった基本的な動きを、5歳までに遊びの中で経験していないと、小学校や中学校のスポーツをする上で壁ができてしまう」と指摘します。
市河教授:
「今は特に、ボール投げが苦手な子どもが増えています。幼児期に『物を投げる』という経験をあまりしてこなかったと考えられます。ヒトの神経系や感覚器系は、3歳までに約60%、5歳までに約80%が成長を遂げるデータがあるように、幼い頃にいったん覚えた動きは身に付きやすいんです。今は体を動かす習慣がついている子とそうでない子の差が極端になっていると言えます」
「体を動かす習慣が無いと、転んだ時に手が出せず、顔をケガしてしまうなど、とっさの動きができなくなってしまいます。無理やり外遊びを強制するのでなく、擦りむく程度の小さなケガには大人が寛容になって、子どもが楽しく遊べる環境を作ってほしいです」
「スマホに子育てさせないで」 いつの時代も人の声やぬくもりで感性を育むことが大切
新野学園長は、女性の社会進出や技術の発達によって、子育てを取り巻く環境が変わろうとも、最も重要なのは、親との触れ合いや五感に働きかけることだといいます。
「働くお母さんが増えて大変になっているのも分かります。ただ、子どもは親の表情やボディランゲージからも多くを学んでいます。時にはスマホを置いて、子どもにたくさん話しかける。絵本を読み聞かせる。紙の質感を感じ、親の声を感じてもらう。あとは手料理。子どもを保育の施設に預けるお母さんたちの中には、ご飯を作る時間がないという方もいますが、おにぎりだけでも良いんです。炊き立てのご飯の香りをかがせてあげる。人のぬくもりで感性を動かすことが心と体の発達には不可欠です」
(取材・文 / 津野紗也佳)