【解説】「少子化対策」の裏側は? 「扶養控除」や「財源」めぐり…税と予算の闘い
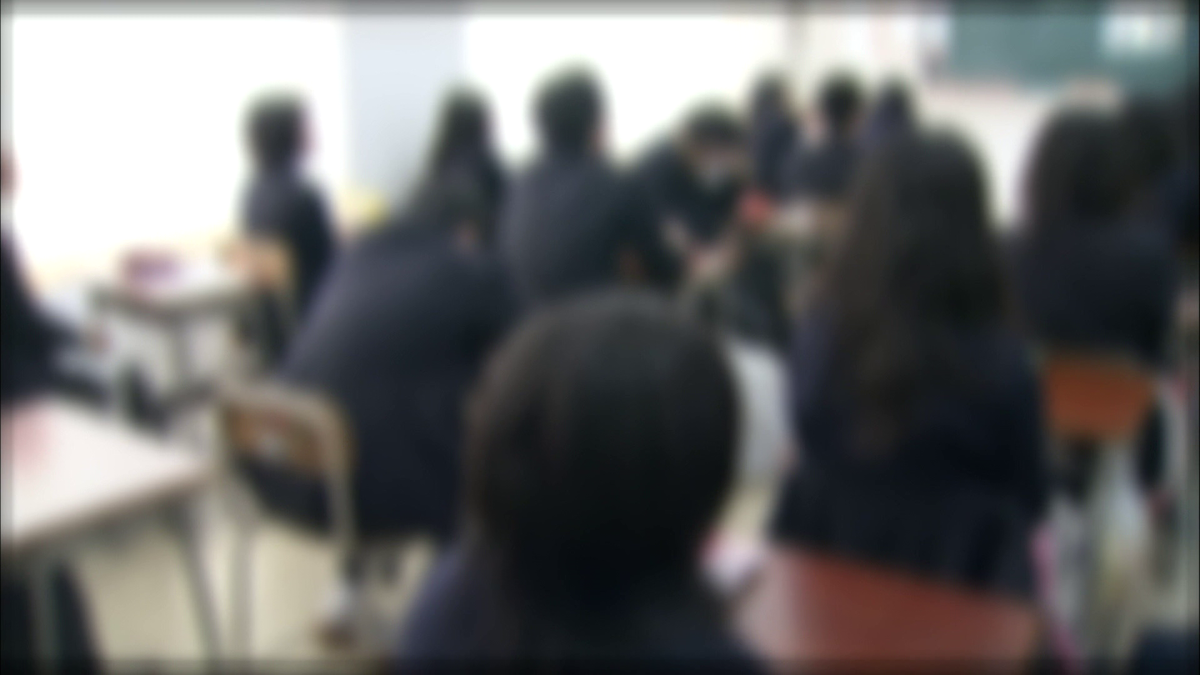
岸田政権の看板政策「異次元の少子化対策」。政策の中身や財源をめぐり子育て世帯から様々な批判が巻き起こる中、2023年末の決着までの過程を追った。
■少子化対策 「2つの不満」が噴出
少子化対策の強化に向けて、2028年度までに新たに確保するとした財源は3兆6000億円。対策の柱は所得制限を完全撤廃し、給付の対象も高校生世代にまで広げるとする「児童手当」などだ。2023年6月、「異次元の少子化対策」を掲げる政府に期待が高まる中、具体案が出てくるたびに国民の一部から不満が噴出した。
1つ目の不満は「扶養控除」だ。政府が示した案では、まず16歳から18歳までの高校生などに月1万円の児童手当を新たに支給する。これに伴って、現在16歳から18歳の親などに適用されている扶養控除(所得税38万円と住民税33万円)の取り扱いが焦点となったのだ。
児童手当を支給しながら、中学生以下に対しては適用されていない「扶養控除」を高校生世代にだけ維持すれば「二重取り」「不公平」になるのではないか。2023年5月下旬頃から、そんな議論が始まった。扶養控除の見直しによっては、実質負担増になる世帯が出かねないことに対し、子育て世帯からは不安と批判の声が上がった。
2つ目の不満は「財源」についてだ。政府は少子化対策集中期間の2024年度から予算を増額し、3年目には、およそ3兆円を追加することを検討していた。その財源は、歳出改革などで2兆円以上を捻出し、残りの1兆円弱は病気やケガのための医療保険を軸に社会保険料の仕組みで集める方針だった。
しかし、この「社会保険料の上乗せ」に対して批判が出たことから、岸田首相は「国民に実質的な追加負担を求めることなく、少子化対策を進めてまいります」と釈明した。政府は財源について、社会保険料は上乗せせずに、医療費などの「歳出改革」で賄う方針を示し、詳細な財源の決定は年末の予算編成に見送られた。
大まかな数字も出さなかった理由について、政府関係者は「社会保険料の値上げという案が炎上したからだろう」と解説した。







