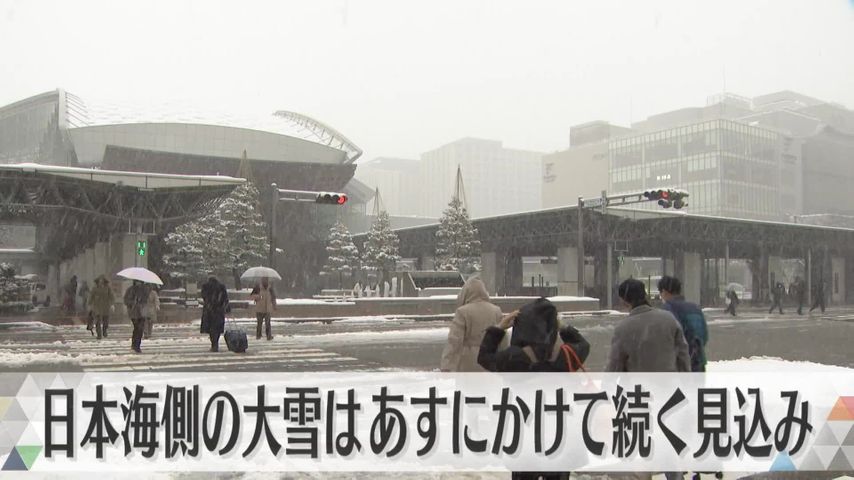【地方創生の現場】今、地方に何が必要か?50歳夫婦「東京にうんざり」愛媛移住で栗農家に!”ブランド化が全てじゃない”戦略の秘密

「東京は暑いし、人は多いし、うんざり。死ぬまでに移住しなきゃ.....と思っていた」。
北原幸子さんの言葉に迷いは全くない。北原さん夫婦はともに50歳という決して若くはない年齢でこの夏、栗農家”見習い”として新しい人生をスタートさせた。東京生まれ東京育ち、10年ほど前から移住セミナーに参加し、東京・有楽町で開かれていた愛媛の移住フェアで、ある町に心をつかまれた。愛媛の奥伊予と呼ばれる西予市城川町だ。
「松山には観光で行ったことがあるが、あそこは都会。コンビニとかない方がいい」(幸子さん)。移住先の城川町は人口約2,800人、市町村合併から20年間で人口が4割も減った。去年、生まれた赤ちゃんは2人.....というのが何より寂しい。
幸子さんは地域おこし協力隊員として『栗農家になる』というミッションを達成すべく活動している。期限は3年間。夫、篤志さんは「協力隊員の協力者」(幸子さん)だそうだ。愛媛県は全国3位の栗生産県で、城川町は県内有数の産地だ。しかし、なぜ今、栗農家なのか。『栗農家になる』というミッションを提示して移住募集したのは自治体だが、その背景は?さらに、地域の栗を”ブランド化しない”という「逆張り戦略」がみえてきた。地方創生の今を取材した。
【南海放送オピニオン室 三谷隆司】
ケーキをそのまま飲むような不思議な栗スイーツ
「むむっ!この濃さは一体.....」「モンブランケーキのスポンジ部分まで丸ごとシェイクして冷やした感じだ」。
城川町の道の駅「きなはい屋しろかわ」でこの秋、新発売された『飲むモンブラン』(600円)はボリューミーで濃い。
1年がかりで完成させたという西又美穂さんが「本当に試行錯誤の連続だったんです」と訴えるように説明する。「氷はガリガリでもフワフワでもダメで、シャリシャリに。牛乳は動物性の風味が、どうも栗とは合わず、豆乳を程よく混ぜました」。1年間の苦労話なのだが、なぜか表情は明るく楽しげだ。「このノリと陽気さは、もしかして.....」と出身地を聞くと、大阪からUターンして地元、城川町に帰ってきたそうだ。
収穫作業ではなく「栗でも拾いに行くか」
この栗スイーツの材料となる栗を収穫しているのが北原さん夫婦だ。幸子さんは「まだ仕事を始めたばかりで大変だけど、なんのストレスもない。豊かでのんびりしてて、楽しい」と笑顔で話す。2人も、とにかく明るい。写真撮影ではポーズまでとってくれた。
地元の農業関係者によると、城川町の栗農家は高齢化が進み、70歳台が主戦力だという。近年は猛暑続きで草刈りがキツく、荒れた園地が増え続け、「このままだと産地としては、あと5年もたない」(栗の生産農家)。栗の収穫というより、「栗が落ちとるけん、拾いにでも行くか」(地元の農業関係者))というのが現状で、栗の集まりも年々、悪くなっているという。
栗の収穫は”拾う”のが基本だ。ミカンのように摘み取るのではない。当然、腰にこたえる。幸子さんも「腰はもちろん、体のあちこちが痛い」と話す。
栽培面積は40%減り、価格は26%上昇
西予市によると、令和に入った2019年から4年間で、栗の栽培面積は4割以上減り、去年は93.6ヘクタール。一方、販売単価は同年から毎年、じわじわ上昇し、去年は26%以上アップしたキロ当たり788.2円だった。全国的にもこの10年間で、栗の栽培面積、出荷量ともに約2割も減少(農林水産省資料)しているが、一方で値段はしっかりだという。
栗には、栗にしか出せない風味と甘さがあり、茹でたり焼いてそのまま食べても、また、餡に混ぜて和風にも、『飲むモンブラン』のように洋風にもアレンジできる。用途が多様で根強い人気がある一方、供給は減少傾向にあるのだ。
「栗はいけるんじゃないか」(株式会社「西の栗」関係者)。そう考える人がいても不思議ではない。
完全民間資本の株式会社で産地を守り、しっかり売る
城川町で「栗はいけるんじゃないか」と考えた人は、実は”東京の人”だった。
去年、城川町に新たに『株式会社 西の栗』が設立された。主に栗の生産、加工や販売を手掛ける他、荒れた園地の整備も行う。社長に就任したのは村田博史さん(42)。もとは”東京の人”だ。28歳で地域おこし協力隊員として城川町に赴任し、7年間を城川町で過ごした。一旦、東京に戻ってサラリーマン生活を送ったものの、5年ぶりに再び城川町に帰ってきた。
「普通に人生を送ってもつまらないから、ちょっと城川町に行ってみようかなと思った」(村田博史さん)。協力隊員になった動機を、真顔でこう語る。実際に城川町で家族とともに生活し、地元の人と触れ合い、地元の気候風土を体感する中で、栗の持つ可能性に気づいたのだ。
地元の栗農家で、取締役として『株式会社 西の栗』の経営に加わった中越健二さんは「栗は基本、足りていない」と話す。「餡やクリームなど和洋どちらの菓子にも人気がある」、さらに「ペーストにして売れば、原材料としての需要にも期待が持てる」と、栗を取り巻く環境を分析する。
特に戦略の柱に位置付けるのが、3番目の「ペースト」の需要だ。全国的に地域の名産品のブランド化を目指す例が多い。しかし『株式会社 城川ファクトリー』の社長でもある村田さんは「ブランド化が全てではない」と断言する。ペーストに加工して栗の消費量が増えれば、産地が活気づき、園地の再生につながるとの考えだ。
北原さん夫婦は今、この『株式会社 西の栗』が受け入れ、栗農家としてのイロハを学んでいる。
地方創生に成功への共通のモデルはない
地方創生は難しい。
地元でも『株式会社 西の栗』について、「まぁ、やってみないと.....理想通りいくかどうかは、これからが勝負」(農業関係者)との声があるのも事実だ。
地方の住民は、これまで散々、国の政策としての地方創生に振り回された。古くはバブリーな「ふるさと創生1億円」にはじまり、最近では難解な「デジタル田園都市国家構想」だ。地方のデジタル化が重要なテーマであることに異論はないが、地方でこの構想が理解され、受け入れられたのか?私は疑問だ。今、私たちの身近な場所の切実な問題は、人口の激減であり、目の前で荒廃する栗の園地であり、草刈りを邪魔する夏の猛暑なのだ。
地方に行けば行くほど、自治体と住民の距離が近く、一体感が強い。これは地方の強みだ。北原さん夫婦を城川町に導いたきっかけは、地域の課題を住民のそばで感じ取った自治体が、東京で開催した移住フェアだ。『3年間で栗農家になる』というユニークなキャッチコピーを掲げ、地域おこし協力隊の制度を利用して、『株式会社 西の栗』のリクルート活動を実質的にバックアップしたことになる。
北原さん夫婦のように「すべてを処分して、ここに来た」(幸子さん)ほどの熱意を持った人材が現実にいて、それを受け入れる『株式会社 西の栗』という地域に根差したベンチャーも生まれている。現実の”芽”をいかにサポートするか。小さくても、目立たなくても、せっかく育とうとしている芽を大切にする地方創生であって欲しい。