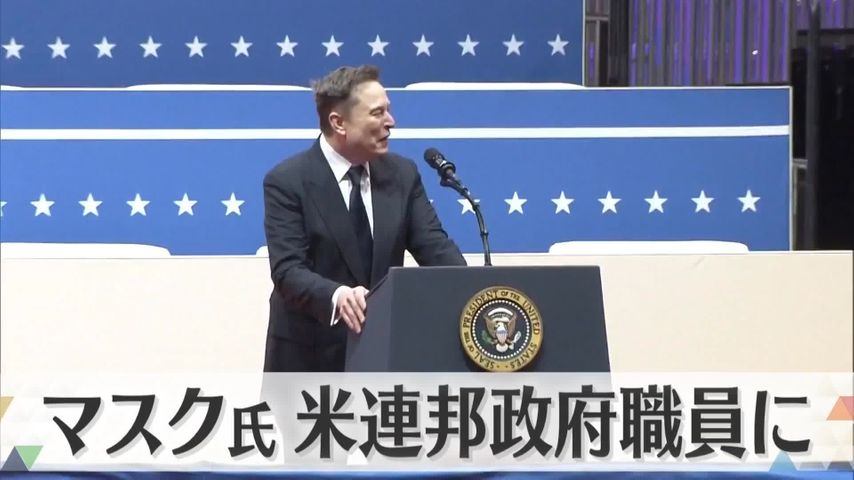気象庁 防災情報を5段階で表示の方針
今年7月の西日本豪雨を受け、気象庁は、危険をよりわかりやすく伝えるために、気象防災情報を5段階の「警戒レベル」で示す方針を決めた。今後、国の検討会で、具体的な議論が行われる予定。
内閣府などによると、今年7月の西日本豪雨では、洪水や土砂災害が起きる前から、危険を知らせる情報が気象庁や自治体から発信されていたものの、多くの住民が速やかに避難しないケースが相次ぎ、200人を超える死者が出た。
気象庁は、危険をよりわかりやすく住民に伝えるためにはどうするべきか検討を進め、気象防災情報を5段階の「警戒レベル」で整理する方針を決めた。
すでに火山の分野で導入されている「噴火警戒レベル」のように、危険度をレベルごとに整理し、住民の取るべき行動をあらかじめ決めておくことで、いざという時に、速やかな避難を促す狙いがある。
ただ、気象庁が出す「警報」や「特別警報」などの気象防災情報と、「避難勧告」や「避難指示」といった自治体が出す避難情報を、どう関連付け、どのレベルに位置づけるかまでは、議論が深まっておらず、今後、内閣府の検討会で、具体的な議論が行われる予定。
また気象庁は、住民が自分が住む地域の危険をよりわかりやすく知るための工夫として、土砂災害の警戒区域や、川の浸水想定などが地図で表示された「ハザードマップ」と、リアルタイムに危険度を予測する気象庁の「危険度分布」とを、重ね合わせて表示する考えを示した。今後、実現に向けて、内閣府や、川を管理する国交省などと具体的な調整を進める方針。