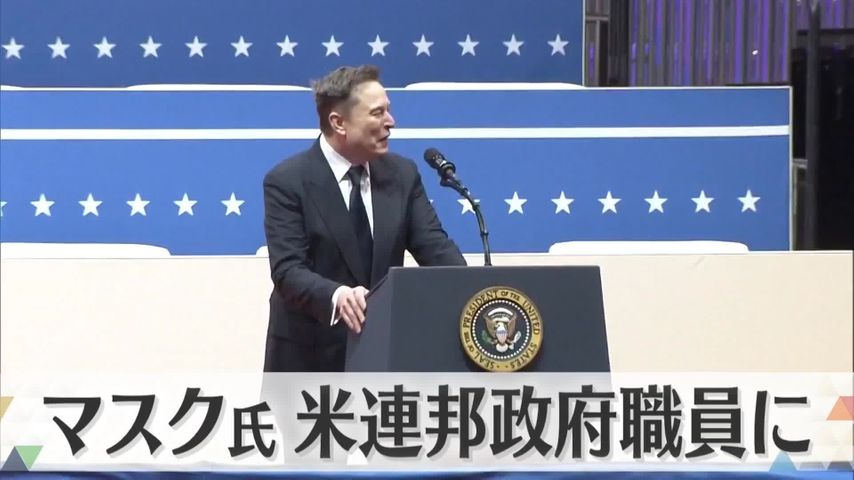進化する“介護食”お年寄りが劇的変化
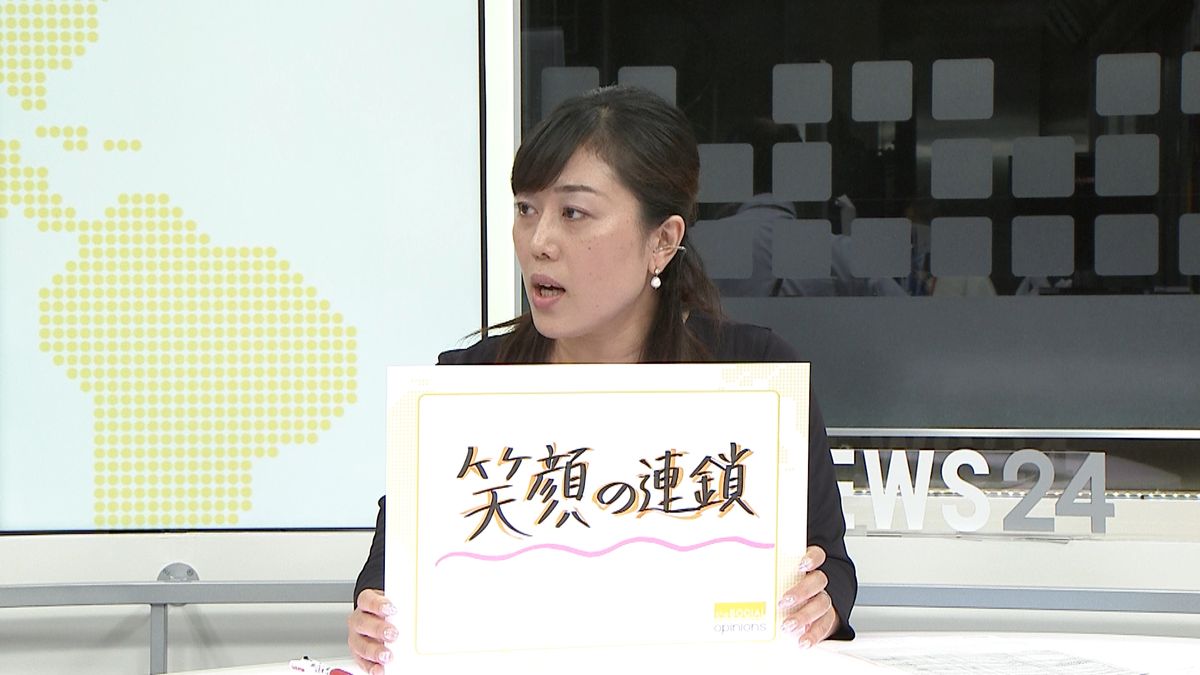
世の中で議論を呼んでいる話題について、ゲストに意見を聞く「opinions」。今回の話題は「進化する介護食」。日本テレビ社会部の野中祐美記者に聞いた。
新横浜のフレンチレストランで提供されたフルコース。西洋ゴボウをやわらかく仕上げたスープや、オマール海老のソースを添え低温で蒸した魚料理など。実は、これらは全て介護食だ。
このレストランでは、のみ込むことに障害がある高齢者などでも食べられる料理を提供している。
――本当においしそうですね!
従来の介護食のイメージとは違い、見た目も鮮やかです。味も本格的で介護食といわれなければ気づかないほどです。
――介護食はなぜこのような進化を遂げているのでしょうか。
理由は「笑顔の連鎖」です。
口から食べることは、生きる喜びにつながる行為です。お祝い事の日だけでも、家族や友人と同じ場所で、同じ食事をとることができれば皆がすごくハッピーな気持ちになり笑顔になれます。
街のレストランでも客からの要望も増えているそうで、プロの調理師が介護食も提供できるように学ぶ動きもあるそうです。
さらに、モニターに映し出された料理の写真ですが、これは神奈川のデイサービスで提供されたひな祭りの食事で、通常食と介護食です。違いはわかりにくいのですが、ご飯の部分を見ると通常の食事と同じように見せる工夫がされています。
――これにはどんな狙いがあるのですか?
のみ込む力が衰えても、こうした見た目の工夫で食べたいと思える料理があれば食も進みます。香りや味などで五感が刺激されたり、食べるために体を動かすことで体力回復につながるケースもあります。
モニターに映っている96歳の女性ですが、同じ神奈川のデイサービスに通い始めた3年前は、ほぼ寝たきりの状態でした。それが、徐々に車イスからの移動や自分で食事がとれるまで回復し体重も8キロ近く増えたということです。
もちろん使う食器の工夫や、利用者に合わせた介助があった上ですが、見た目も考えられた介護食が秘める可能性はすごいなと実感させられる実例です。
食べることは生きることの基本ですし、食べた人やその家族も友人も、作った人も介助した人も、結果、みんなが笑顔になれるものだからこそ、様々な工夫が凝らされた介護食が登場しているのだと思います。
現状、こうした介護食が提供される場所はまだ少ないのですが、必要としている人は多いと思いますので、今後広がりを見せる世界だと思います。
【the SOCIAL opinionsより】