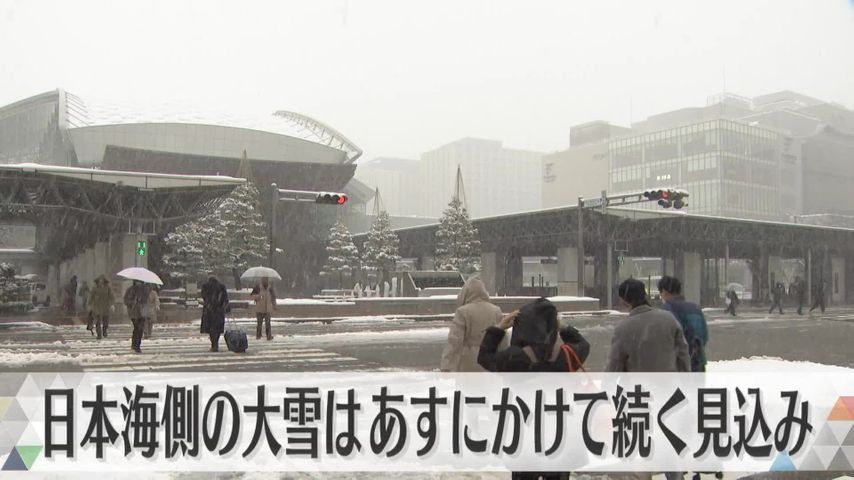解体される我が家をカメラに収めた記者 故郷は原発事故被災地・大熊町「何が起きたのか、知ってもらいたい」
【その強力打線は「アトム打線」と呼ばれていた】
「最後の夏の甲子園に向けて、みんな練習にも気合が入っていた。そうしたら、いきなり立っていられないくらい地面が揺れて、みんなパニックになって…」。
高校球児の鍛えた足腰でも立っていられないほどの激しい揺れが数分続いた。学校の周りの住宅などが地震で崩れていく。「止まってくれー!」。渡邉は恐怖のあまり地面に這いつくばり大声で叫んでいたという。
当時、学校には約200人の生徒がいた。グラウンドに避難してきた生徒たちから「津波が来るのかな…」と不安の声があがった。高校は海岸から3キロしか離れおらず、生徒たちはすぐに高台に走って向かった。幸いにも避難した高台には津波は到達せず、みんな無事だった。
【避難指示…持って行ったのは財布、携帯、毛布だけ】
車内でテレビを見ていると、画面は政府の緊急会見に切り替わり、当時の枝野官房長官がこう語った。
「落ち着いて対応頂きたい、21時23分、大熊、双葉に住民の避難の指示をした、3キロ以内の住民。これは念のためのもの、放射能は現在も炉の外には漏れていない、環境に危険は発生していない」。
渡邉の家は原発から約1.5キロ。財布や携帯電話と毛布を数枚だけを持って、原発から約5キロ離れた中学校に避難した。その晩は一睡もできなかったが、危機的な状況とは感じなかったという。
「翌朝には家に帰れると思ってたんです…」。
【「家に帰れない!」テレビが捉えた原発爆発の瞬間】
翌朝の午前6時、避難指示範囲が10キロに拡大され、町全域が避難の対象エリアとなった。渡邉たちは原発から約40キロ離れた避難所へ向かった。避難所の体育館に入ると、テレビの周りに住民たちが集まっていた。画面は見たこともない原発の姿だった。アナウンサーが上ずった声でリポートしていた。
「えー、さきほど1分前、福島第一原発1号機から…大きな煙が出ました。大きな煙が出まして、そのままその煙が北に向かって流れているのが分かるでしょうか。」
原子炉建屋の壁がはじけ飛び、煙が数百メートルほどたなびいていた。煙は原発の敷地を越えて、渡邉の家にも迫っているようだった。
「近くにいる人たちが死んでしまったと思いました。いずれにしても、家に帰れない!とハッと気づきました」。
血の気が引いていく感覚だった。渡邉の家の周りには大量の放射性物質が撒き散らされ、約1カ月後には立ち入りが制限された。
【名門・双葉高校野球部 廃部へ…】
双葉高校は避難先の高校の教室を間借りする形で授業を再開した。しかし、避難のため転校せざるを得ない生徒も少なくなかった。3分の1に減った野球部は、甲子園を目指し、諦めずに練習をした。しかし、渡邉たちの最後の夏は3回戦敗退だった。
本来のレギュラーメンバーだったらもっと上に勝ち上がっていたはず…そういう悔しさは今でもあります。ただ、避難先の周りの人たちからたくさんの支援を受けて、試合に出られたことは嬉しかった。ごちゃまぜの感情でした…」。
その後、高校は休校となり、野球部の歴史も途絶えてしまった。
【父と母が決断した故郷の家と土地の売却】
福島県内では、生活環境から放射性物質を取り除く「除染」が各地で進められていたが、その除染で出た土などを30年保管する施設だ。渡邉の家がある地区は、その建設エリアに入ってしまった。先祖代々受け継がれてきた故郷の土地を売るか売らないか、交渉にあたったのは渡邉の父だったが、この問題については何も語らなかったという。
渡邉の父は東京電力の社員でもあり、事故当時は第二原発の中で事故対応に奔走した。しかし、2017年、多発性骨髄腫で57歳の若さで亡くなった。病気のことも最期まで息子たちに話さなかったという。亡くなって10カ月後、渡邉も同席する中、母が国の契約書にサインをした。
「施設ができなければ、除染が思うように進まないから。復興のためには必要なことと、父と母が決めました。」
【解体されるわが家 被災者の一人として“伝える”】
いつか自宅に帰れるかもしれないという望みはなくなったが、渡邉は解体の様子をカメラで収めていた。
「原発事故によって何が起きて、何が奪われたのか。このことを広く知ってもらいたい」。
渡邉は今、地元のテレビ局の記者として原発事故の被災地を取材している。原発事故により、故郷の土地が奪われ、コミュニティが失われていくというかつてない現状を、当事者として伝えていくことが責務のように感じたという。
【またここで暮らせるか、“安全な土”に埋もれるか】
再利用が進めば、渡邉の故郷は埋め尽くされることなく、またここで暮らすことができるかもしれない。進まなければ、故郷は行き場をなくした「安全な土」に埋め尽くされることになる。
【“安全”だが不安…進まない除染土再利用】
しかし、この土を受け入れるところは福島県外では1つも存在しない。環境省が行ったアンケート(2022年度)では除染土の県外での最終処分について県内では、約6割が知っていると回答した。しかし、県外は2割ほどにとどまっていて、県外の候補地からは反対の声が根強いのが事実だ。住民や国の両者を取材する渡邉はもどかしさを感じていた。
「住民にもこれまでの生活があるし、家族もいるし、納得して受け入れるには時間をかけた丁寧な説明が必要だと思うけれど、自分の故郷はどうなっていくのか…」。
国は2024年度内には国際原子力機関(IAEA)の評価を得た上で、除染土の最終処分や再生利用の基準を策定したいとしている。
【「こういうことがあった」と後世へ伝えたい】
渡邉には今年の春に第二子が生まれる予定だ。子供たちは本当の故郷に立ち入ることもできず、知らないままこのまま大きくなっていくだろう。「子どもたちには余計な心配はさせたくない」と自宅と土地を息子たちの世代に引き継がなかった父の考えも分かる。しかし、本当にそれでよいのか、渡邉はずっと自問自答してきた。
「子供たちには重荷にはなってほしくないけど、『こういうことがあった』という事実は隠したくない」。
県外最終処分の期限まであと22年。中間貯蔵施設が整備されている渡邉たちの故郷には、人の営みが戻っているだろうか。それが僅かでも見通せる道筋は何も示されていない。