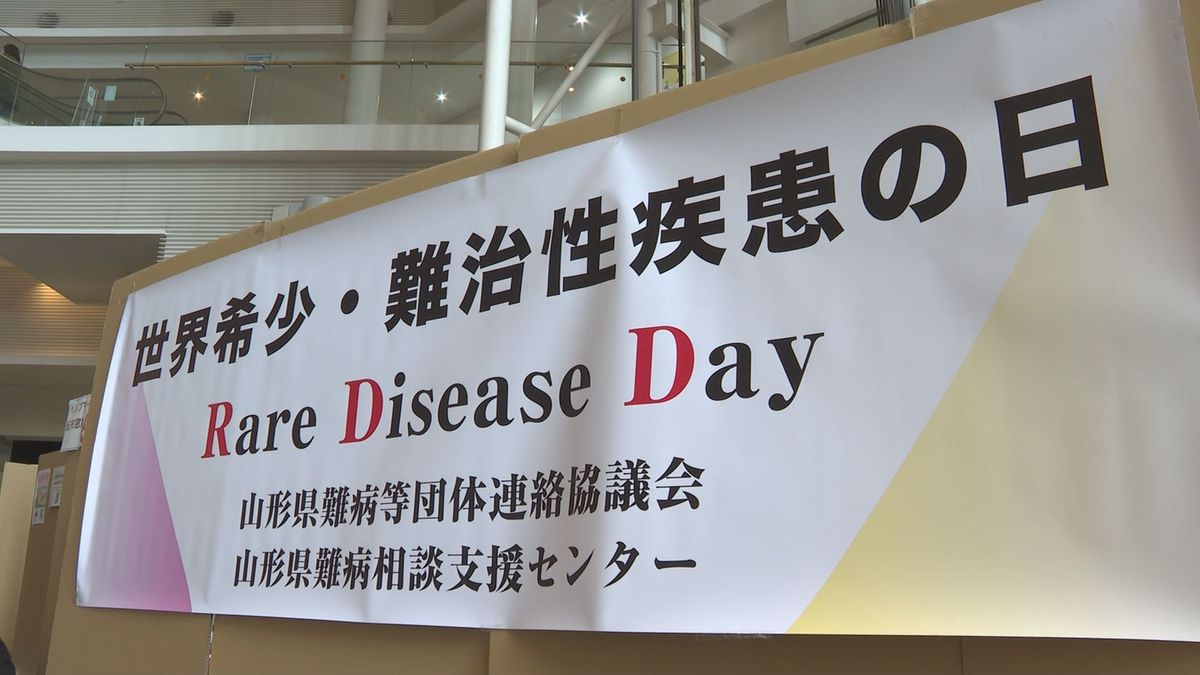山形県内に難病患者は8000人以上 「難病への理解を」山形市で啓発イベント
毎年2月の最終日は難病の患者や家族について考える「世界希少・難治性疾患の日」です。この日を前に山形市で24日、多くの人に難病への理解を深めてもらおうというイベントが行われました。
このイベントは難病患者やその家族などでつくる山形県難病等団体連絡協議会が難病の症状や患者の思いなどについて理解を深めてもらおうと毎年行っているものです。
会場には、筋肉が徐々に壊れ、筋力が衰えていく難病の「筋ジストロフィー」などについて12の団体がパネルを展示して症状や治療法などを紹介しました。
こちらは協議会の代表を務める鈴木省三さん(82)。鈴木さんは60歳で「筋無力症」と呼ばれる難病を発症し、およそ10年間、闘病生活を送りました。
山形県難病団体連絡協議会・鈴木省三代表「筋肉に力が入らなくなる病気で、 物が2つに見えるとか物を持てない、呼吸が苦しくなるなどの病気」
鈴木さんは自分と同じように難病を経験した人に治療法などについて相談できたことが心の支えになったと話します。
山形県難病団体連絡協議会・鈴木省三代表「(難病患者が)お互いに支え合う。そういう機会があれば安心して治療を受けられると思う」
会場には5万人から10万人に1人が発症するとされている「スタージ・ウェーバー症候群」という難病で生まれつき顔などに大きな赤いあざがある上山市の岩川雅治さん(20)の姿もありました。岩川さんは今回初めて運営スタッフとしてこのイベントに参加しました。
岩川雅治さん「希少疾患について一般の方はほとんど目にする機会は無いと思うので、少しでも希少疾患に対する理解が広まってくれれば意味のあることだと思う」
山形県内では難病認定者がおよそ8000人、このほかに子どもの難病患者がおよそ800人いるとされています。
協議会は今後も難病患者やその家族について理解を深めてもらう活動を続けていきたいとしています。