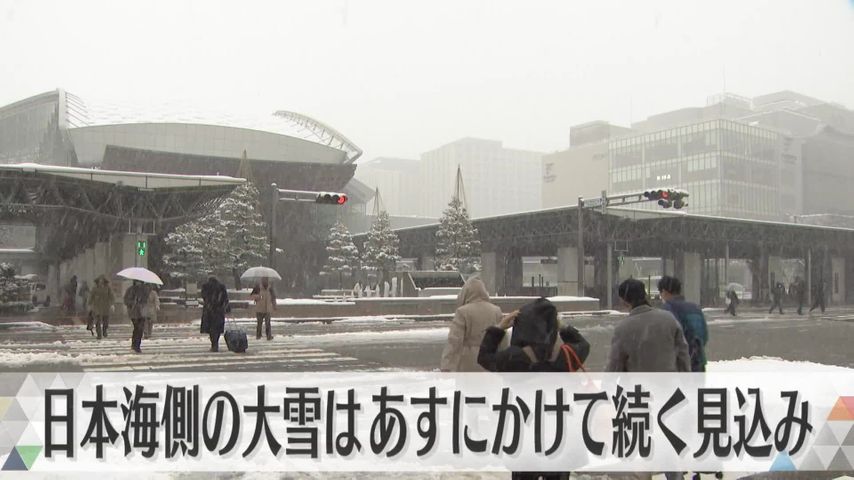「限界です」老老介護の末…85歳妻を殺害した罪に問われた夫(80)の裁判 夫が語った事件の“分岐点”とは【#司法記者の傍聴メモ】
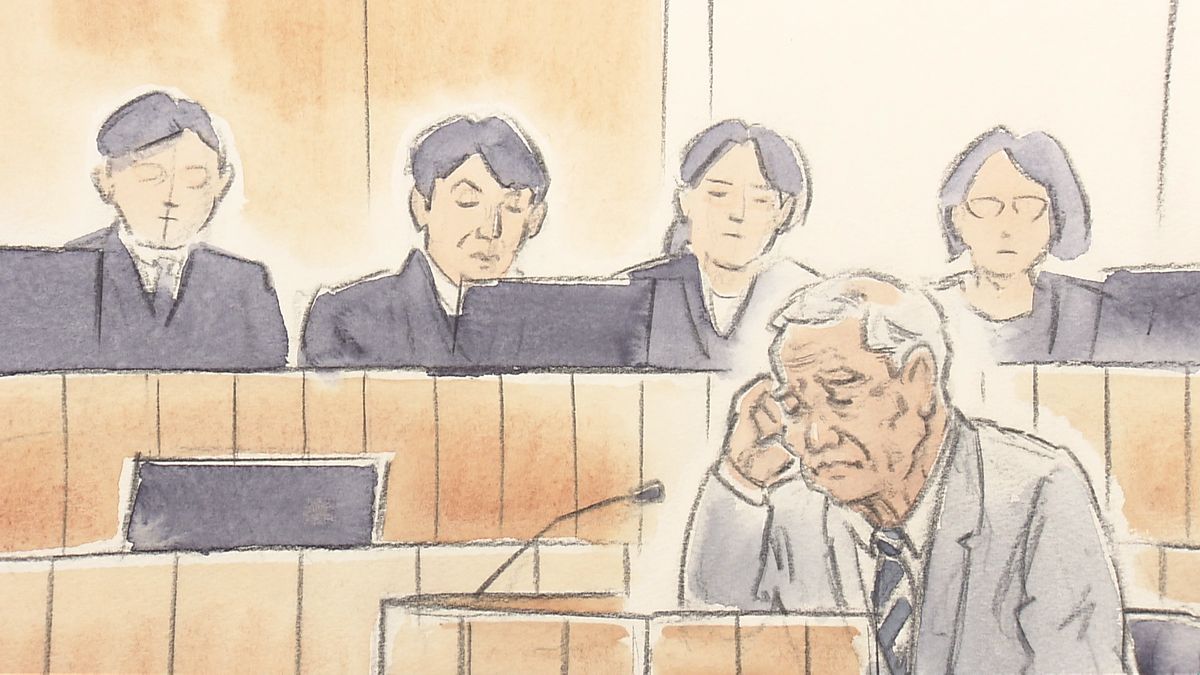
「刃物は傷をつけてかわいそうなので首を絞めようと思います」80歳の夫は携帯電話のメールにメッセージを残し、約30年間にわたり連れ添った85歳の妻の首に手をかけた。老老介護の末の事件。防ぐことはできなかったのか…夫が語った事件の”分岐点”とは。
■「間違いありません」起訴内容認める 結婚生活約30年の夫婦に何が
6月12日。東京地裁で行われた初公判。グレーのジャケットにネクタイをしめて法廷にいたのは夫の被告(80)。被告は、2023年、東京・世田谷区の自宅アパートで、妻(85)の首を手や電源コードで絞め殺害した罪に問われていた。
裁判長から起訴内容について聞かれると。
被告「間違いありません」
およそ30年にわたり生活を共にしてきた夫婦。2人の間に何があったのか。法廷で明らかになった証拠などから事件の経過をたどる。
被告は、勤めていた飲食店で妻と出会い、1994年、50歳の時に結婚した。2人は仲の良い夫婦だったという。しかし、妻は2016年ごろから目が見えなくなり始め、ヘルパーに外出を手伝ってもらうようになった。家の中での介護は被告が1人で行っていたという。
被告(被告人質問)「妻はだんだんと方向感覚がずれることがあり、トイレの中まで連れて行くようになりました」
に異変が見え始めたのは去年。1月に「要介護1」と認定され、被告が「浮気している」などと被害妄想を口にするように。
被告(被告人質問)「妻を1人にできない状況が増えた」
被告は定年退職後に始めたシルバー人材センターでの仕事を辞めて介護に専念するようになった。
被告にとって仕事は「仲間と会えることを楽しみにしていた。息抜きの1つ」だったという。
7月、妻は医師からうつ状態などと診断され、9月には被害妄想がさらに悪化。「財布を返せ」などと言って騒いだり、徘徊して近隣住民に支離滅裂なことを言ったりするようになったという。
手がつけられない時には救急車を呼ぶこともあったといい、被告は、妻の症状は深刻だと感じ始めていた。
そして10月1日の夜──。
「財布をなんで返さないんだ」
妻は再び被害妄想を口にし、騒ぎ始めた。興奮して外に出ようとしたため、被告はベッドに連れて行き、4時間以上にわたり妻をなだめていた。
“静かにしてほしい──”
被告は興奮し声が大きくなっていた妻の口を右手でおさえ、首を絞めたという。
■「限界です」携帯電話に残された“葛藤”
実は、被告は事件前後に当時の心情をつづったメッセージを携帯電話のメールに保存していた。そこには被告が感じていた“葛藤”が記されていた。
事件前日の9月30日。
午前1時2分「中々死ぬ踏ん切りができません。でも限界です。やってみます」
午前1時29分「死ねるかな?!できるかな?!わからないけど息苦しいです」
午前2時4分「刃物は傷をつけてかわいそうなので首を絞めようと思います。自分が死ねるか心配です」「まだ勇気が出ません」
そして10月2日。
午前1時4分「ついにやりました」「申し訳ありません。あとは自分のことです。頑張ります」
午前3時4分「首を絞めた自分とそれを見ている自分がいます。息苦しいです」
午前10時33分「○○(妻)は楽になったのかな。俺はまだ生きている」
■“介護ストレス”が殺害の原因?被告人質問では…
なぜ被告は妻を殺害したのか。被告は被告人質問で、当時の気持ちを振り返った。
被告「理路整然としてしっかりしている妻が、自分がやっていることがわからなくなってしまったことがすごいかわいそうに感じた」「殺せば妻が楽になると思った」
変わりゆく妻への思いを口にした一方で、介護へのストレスについては──
被告「自分ではストレスを感じていた認識はありません」
“2人きりの家族なので介護するのは当たり前”だと話し、殺害の動機は、介護ストレスが原因ではないと話した。
被告は妻を殺害した後、自殺しようとしたという。
被告「2人して死ぬよりほかないと考えていたと思う」「妻を送った以上、私が生きているのはあり得ないと思った」
検察側は懲役7年を求刑し弁護側は執行猶予付きの判決を求め結審した裁判員裁判。
6月20日、東京地裁は判決で、「被告人が自覚のないまま疲労や疲弊感を蓄積させ、解決のための選択肢を持ち合わせない中で、視野を狭くして、犯行に及んだことは想像に難くない」として被告に懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。
判決の後、取材に応じた被告は、「正直執行猶予が付くとは思っていなかった。本当にこれでいいのか。私だけが表で普通の生活をしていいのかなという複雑な気持ちがある」と涙ながらに話した。
■周囲に助けを求められなかったのか?語られた事件の“分岐点”
老老介護の末の事件…防ぐことはできなかったのか。被告は取材に対し“ある後悔”を口にした。
「やはり7月25日に断ったのが“分岐点”だと今でも思っている。 なんでああいう判断をしてしまったのか今でも悔やまれる」
被告が“分岐点”と語るのは、去年7月25日。裁判の中でも語られたこの日は、妻が医師から2回目の往診を受ける予定だった日だ。
しかし、1回目の往診で、うつ状態などと診断された妻が「私はおかしくない」と訴え、2回目の医師の往診を強く拒否。被告は、2回目の往診をキャンセルし、医師の力を借りることを自ら手放してしまったのだ。
法廷で被告は、「本人が嫌がっていても私自身が強く妻を引っ張るくらいの気持ちでやるべきだった」「妻が嫌がっていても専門家のアドバイスは聞くべきだった」と悔やんだ。
誰かを頼るきっかけを失ってしまった2人。
被告(被告人質問)「私も妻もよく言えばプライド、悪く言えば見栄っ張りで、人には弱みを見せたくなかった。 家族のことは家族でなんとかしなければというのがあったのかもしれない」「妹も後期高齢者で、きょうだいでたった1人の男である私が心配をかけるわけにはいかなかった」
親族や知人にも助けを求めることができなかったことを悔やみ、「今後は見栄を張らずに頼むことは頼む、お願いすることはお願いして素直になるべきだと思っている」とこれからの生き方についての思いを話した。
“豊かでなくても2人でなごやかな老後を送りたい”と考えていたが、その未来を自らの手で断ち切ってしまった被告。
今、妻に対し何を思うのか。
被告(被告人質問)「妻は一生懸命症状を治そうとしていた。その気持ちはもっと尊重してやらねばならなかった。妻はやっぱりまだ生きたかったんでしょうね…それを奪ったのは申し訳ない」「妻の願いを強引に取り上げたのだから一生懸命謝りながら供養していきたい」
(社会部司法クラブ記者・宇野佑一)
【司法記者の傍聴メモ】
法廷で語られる当事者の悲しみや怒り、そして後悔……。傍聴席で書き留めた取材ノートの言葉から裁判の背景にある社会の「いま」を見つめ、よりよい未来への「きっかけ」になる、事件の教訓を伝えます。