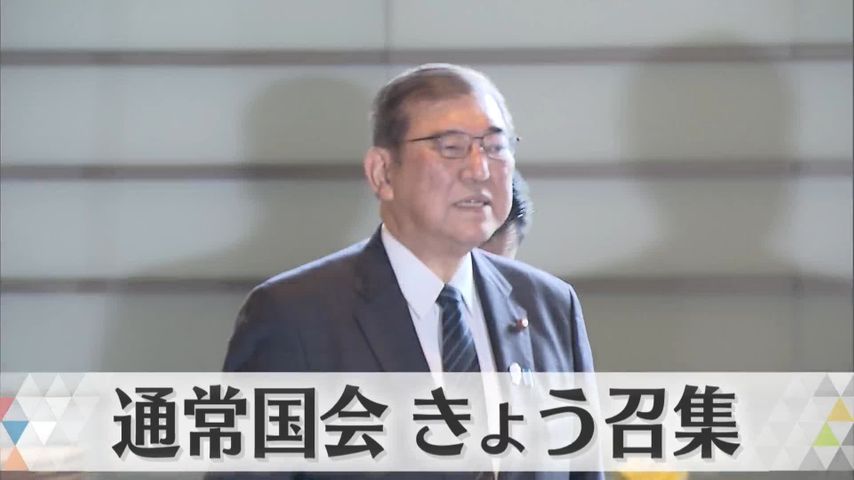「日本が目指す月面着陸」読売記者が解説
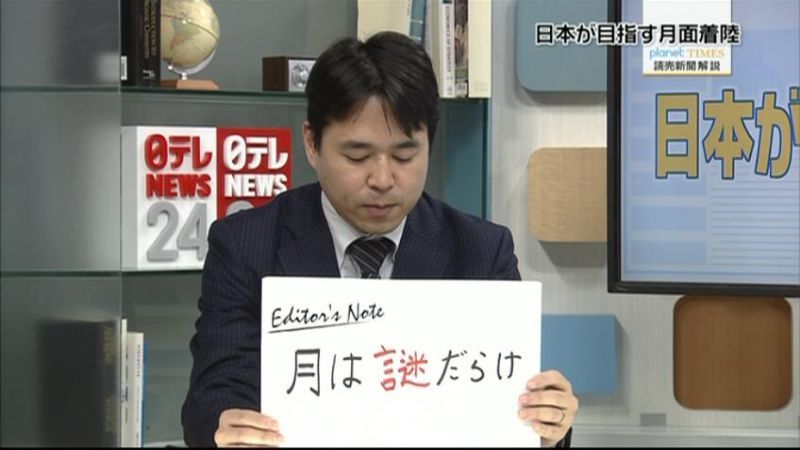
注目ニュースや話題を「読売新聞」の専門記者が解説する『デイリープラネット』「プラネット Times」。15日は「日本が目指す月面着陸」をテーマに、科学部・冨山優介記者が解説する。
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は先月、月面着陸を目指す国内初の小型無人探査機を2018年度にも打ち上げる計画を明らかにした。日本はこれまで、月の周りを回る探査機「かぐや」を打ち上げているが、月面へ探査機を着陸させるのは初めてで、成功すれば、旧ソ連、アメリカ、中国に続く4番目の国になる。
この計画は「SLIM計画」と命名され、SLIMは重さ約130キロの小型の無人着陸機、名前は「Smart Lander for Investigating Moon」のそれぞれの英単語の頭文字をつなげたもので、日本語に訳すと「賢い月面着陸機」というところだろうか。SLIMの特徴は、月の目標地点に高い精度で着陸する性能だ。これまでの他国の例では着陸の目標地点と実際に降りた場所の誤差は数キロメートルあったと言われているが、この誤差を100メートル程度で収めることを目指す。
100メートル程度の誤差で着陸させるために、どのような技術を使うのか。月には「クレーター」と呼ばれる隕石が衝突したくぼみが無数にある。これまでの探査で、こうしたクレーターの分布はデータとして集められている。SLIMは着陸する際、デジタルカメラでも使われている「顔認識技術」を活用、地形データを確認することで、その時点で月面上のどのあたりを飛んでいるのかを確認し、着陸の精度を高める。
すでに1969年のアメリカのアポロ計画で人類は月面に降り立っているが、なぜ今、改めて月面着陸を目指すのか。アポロ計画は初の人工衛星打ち上げや有人宇宙飛行で当時のソ連に遅れを取ったアメリカが、国の威信を懸けて挑んだ計画だった。計画に費やした事業費は現在の貨幣価値に換算すると10兆円を超えると言われていて、財政負担の重さからアポロ計画自体も1972年に打ち切られ、月探査はそれ以降、長い停滞の時代を迎えた。
しかし、1990年代半ばに入ってから、無人の探査機による調査で月には大きな利用価値があるということがわかってきた。月には鉱物資源や基地建設の候補となる地形があり、水が存在する可能性もある。人類が宇宙空間で活動する上での拠点として、火星へ向かう上での足がかりとしての役割に期待が高まっているのだ。
日本やアメリカ、ロシア、欧州など12の宇宙機関は2013年、国際宇宙探査のロードマップを作成し、宇宙での活動の舞台を現在の国際宇宙ステーションから月の周辺、月、やがては火星へと広げていく構想を掲げた。ロシアは2030年、中国は2025年に月の有人着陸を目指していて、宇宙開発の分野では新興国と言えるインドも数年内に無人機を送り込む計画。特に中国は2013年、旧ソ連、アメリカに続き、月面への軟着陸を成功させた3番目の国となり、宇宙関係者に衝撃を与えた。冷戦下に行われたアポロ計画の時代には月へ行くこと自体が目的だったと言えるが、現在、各国が月探査に力を入れるのは、もっと実用的な観点からだと言える。
こうした中で、日本が月への着陸を目指す意義は何か。それは、国際的な協力の下で行われる大きな宇宙探査のプロジェクトでは、日本も独自の存在感を発揮することが必要なためだ。日本が持つ強みは、小惑星「イトカワ」から試料を採取して持ち帰った探査機「はやぶさ」に代表されるような精密な制御による着陸技術で、JAXAの担当者は「降りたい場所に降りられる技術を実証し、付加価値を高める」と説明している。
「降りたい場所に降りられる」というのは、とても重要な事だ。探査などの活動を行う上で、有効活用できる場所は限られている。例えば、月面で電気などのエネルギーを生み出す手段は当面の間、太陽光発電が中心になると考えられ、日照はとても重要なポイントとなる。月の場合、自ら回る「自転」の周期は約27日で、夜は2週間も続き、場所によっては全く日の光が当たらない部分もある。月の南極や北極の付近では、比較的年間を通じても日照時間が多い場所があるが、数が限られている上に広さも数百メートルと言われていて、こうした「1等地」にピンポイントで着陸することは、とても大事なのだ。
また、月の周りを回っていた日本の別の探査機「かぐや」は、月面に直径約70メートル、深さ約90メートルの大きさの縦穴を発見した。この縦穴は、宇宙から降り注ぐ放射線を防ぎ、人が一定期間居住する基地として活用できるのではないかと期待されている。この縦穴付近はSLIMの着陸目標地点の候補の一つとなっていて、目的の場所に正確に降りることは、将来、月や火星など他の天体へ進出していく上でも欠かせない技術と言える。
ただ、今後の課題の一つとして精密な着陸技術を本当に実現できるかという点がある。日本は探査機「はやぶさ」が小惑星「イトカワ」へ着陸し、試料を持ち帰った実績がある。しかし、長さ540メートルほどの小さな「イトカワ」には、ほとんど重力がなく、直径が約3500キロで地球の6分の1の重力がかかる月面では異なる技術が必要となる。
もう一つの課題は、この計画が日本にとってどんな意義を持つかという点だ。SLIM計画の事業費は開発や打ち上げの費用を含めて100億円から150億円と言われている。日本では、商業用の衛星を打ち上げる大型ロケットの発射が1回につき100億円程度かかると言われている。
2014年12月に打ち上げられた「はやぶさ」の後継機「はやぶさ2」の事業費は約290億円で、先端の宇宙探査プロジェクトとしては比較的事業費は少ないと言えるが、それでも巨額の事業であることに変わりはなく、国のお金が使われる以上、半世紀近く前に人類が降り立った月に100億円を投じて無人の着陸機を送り込むことにどんな意義があるのかというのは、一般の人が抱く最もな疑問だと思う。「探査のための探査」というのではなく、計画を通じて、国民にとってはどんな恩恵をもたらすことができるのか、関係者はわかりやすく説明し、支持を得ていく必要があると思う。
雲のない夜空を見上げれば、明るく輝く月を肉眼で見ることができる。竹取物語のような昔話や、唱歌の題材にもなっていて、月は私たちにとって最も身近な天体と言えるのではないのだろうか。しかし、実は月について科学的にはわからないことだらけだ。月の内部の構造をはじめ、そもそもどうやって月が出来たのか、説は定まっていない。宇宙進出の足がかりという実用的な目的だけでなく、月の探査が進むことで、こうした謎も明らかになればと思う。