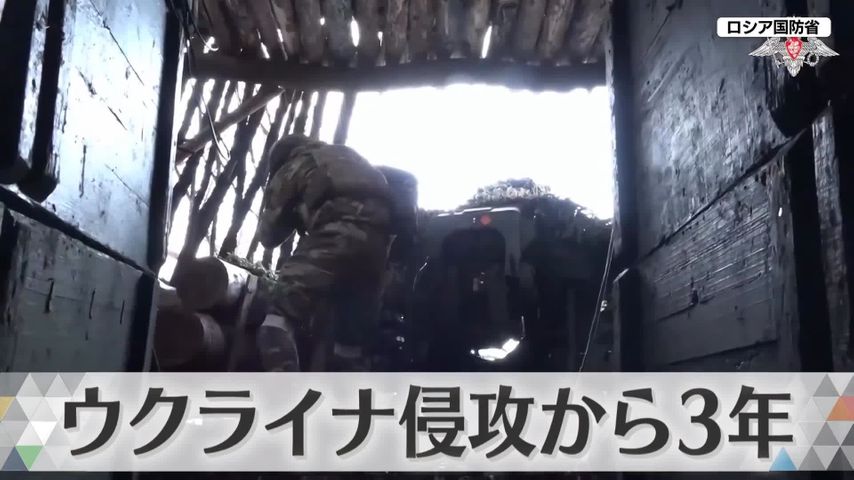サンマの“歴史的不漁”ポジティブに捉える
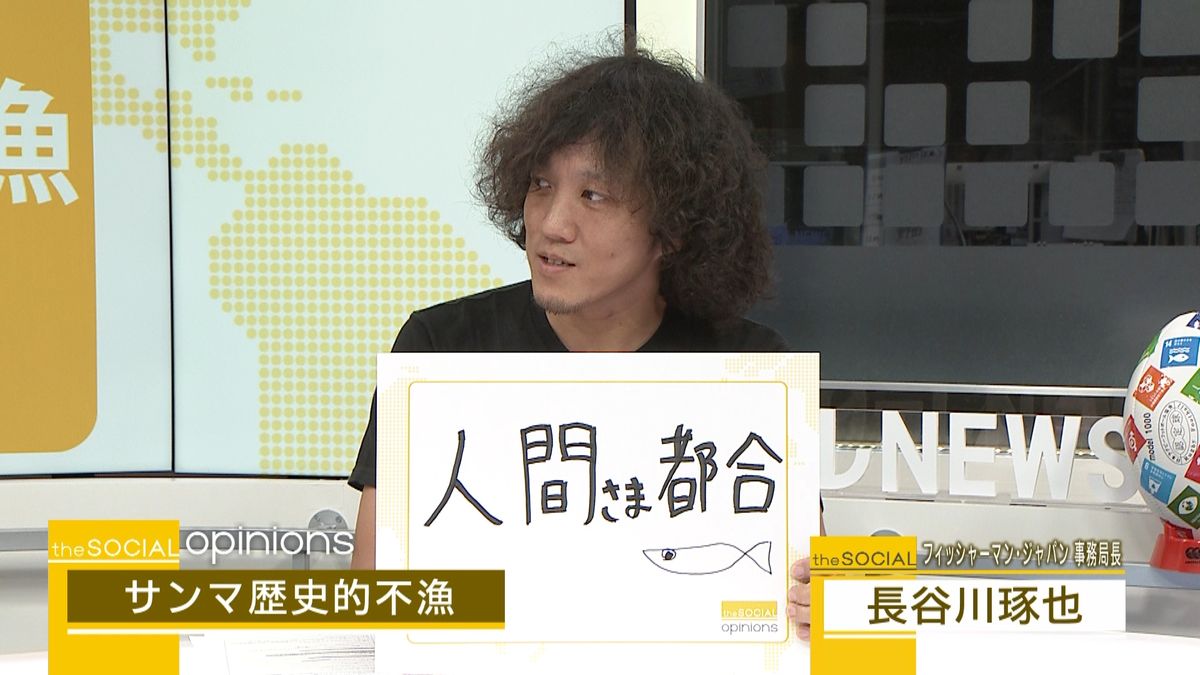
世の中で議論を呼んでいる話題について、ゲストに意見を聞く「opinions」。今回の話題は「サンマの歴史的な不漁」。フィッシャーマン・ジャパン事務局長の長谷川琢也氏に聞く。
秋の食卓を飾るサンマが記録的な不漁となっている。各港の水揚げは、例年のこの時期に比べて、北海道の花咲港で20%弱、岩手の大船渡港で約8%、宮城の気仙沼港では、約1%と歴史的な不漁となっている。この状況を受けて、食堂チェーンの大戸屋では、「生さんまの炭火焼き定食」の提供を見合わせる事態になっている。
――この現状をどう見ますか。
『人間さま都合』と書きました。この時期に比べて何%というのは、人間が思うようにサンマさんたちが動いてくれるかというと、そういうわけではありません。季節とか海の流れとか水温とか、人間がコントロールできないじゃないですか。だから、サンマがいつ来るか、どれくらい取れるかという「サンマ予報」というのを国や研究者がやっていて出ているんです。だから今年は9月はあまり来ないよというのは発表されていたんです。それ考えると、去年と比較してどうだったかというのは人間都合だなというのはあるかと思います。
――実際にこういうニュースが流れると、みなさんは、今年はサンマが減っているということで買い急ぐという現状もありますよね。そういうのはいかがでしょう。
例えば値段が数十円上がって、家計に大打撃という話がでますが、実際は日本人が食べるサンマの平均って「2本/1年」らしいんです。そうすると仮に100円のものが200円になっても年間200円しか増えないじゃないですか。だからそこで騒いでしまうと良くないというか。その結果、もっと安くしてくれみたいな話になってしまうと、スーパーや魚屋、漁師、いろんな人にしわ寄せがいくので、そういうことがないように良い漁業の流れがつくれたらなと思いますね。
――その捉え方次第で、持続可能にもつながるわけですね。
毎年地球の環境が、人間の思うとおりにいかないので、「今年のサンマは大きいよね」とか「高いけどおいしいよね」とか、そういうのを楽しみながら、未来にどうつないでいくかというのをみんなで前向きに議論できたらいいなと思います。
――サンマは、もちろん日本人は大好きですけど、海外でも好きな方は多いんですよね。
元々は日本人が好きな魚だったんですが、最近は海外でも人気になり始めています。そうなってくると、「もっと食べたい」となりがちなので、どうやってみんなでおいしく食べ続けるかを話し合えるといちばんいいなと思います。海はつながってますからね。国や地域の都合だけではなくて、みんなで考えていこうという流れを大事にしていきたいです。
――現場で、多くの漁師の方々と交流があると思いますが、こういう魚を食べる文化や現状をみなさんはどう思っていらっしゃるのでしょう。
日本人は元々、魚が大好きで、海とか漁業から文化が生まれているので、それを基本的には漁師が誇りをもって生きてきたんですが、世の中の流れがそうじゃなくなってきた中で、どうやって日本人として、魚、漁業、漁村を誇りに思うかというのを思い出してほしいよねということを話し合っています。そのためには、漁師をステキに見せたり、魚をおいしく見せたりということを、今、みんなで前向きに――漁師も取るだけの仕事でしたが、消費者のみなさんたちと一緒に良いことを考えていけるかということを一緒にがんばっています。
■長谷川琢也氏プロフィル
フィッシャーマン・ジャパン事務局長。東日本大震災をきっかけに、宮城県石巻市に移住。地元の若手漁師と共にフィッシャーマン・ジャパンを立ち上げ、次の世代に続く水産業の実現と地域活性化を目指している。
【the SOCIAL opinionsより】