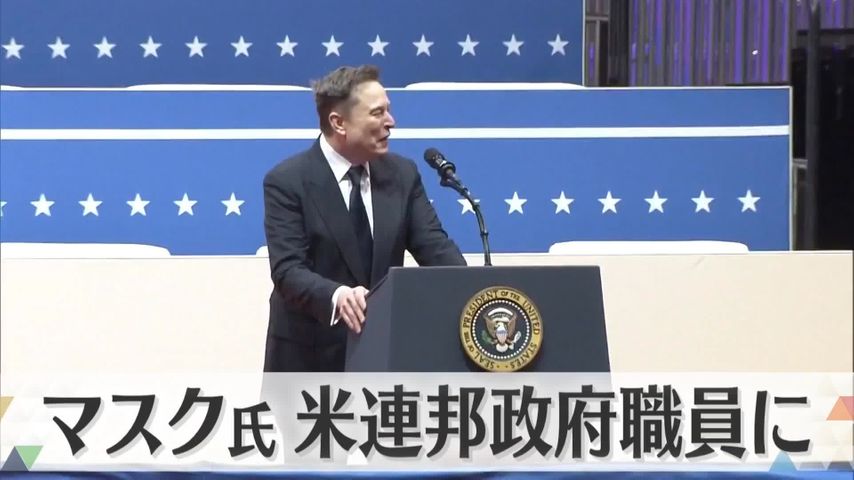「GoTo」は見直しを 和田教授に聞く
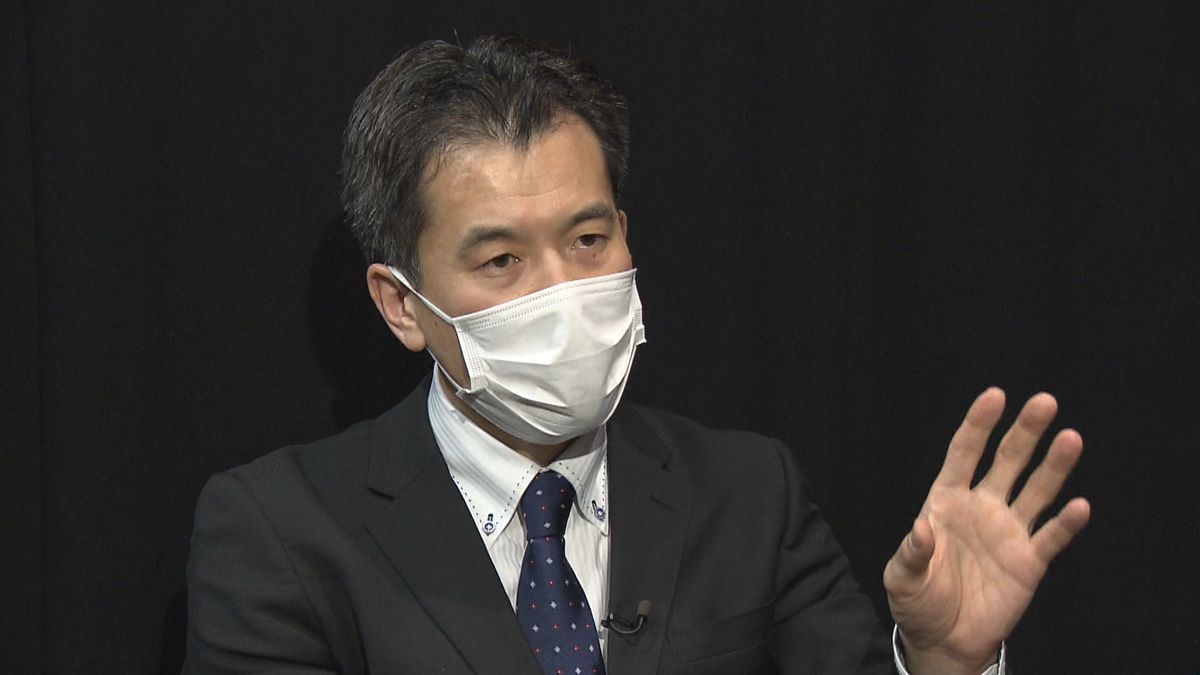
■重症者が減らないと解除はできない
――緊急事態宣言から2週間が経過しました。ここまでの効果と解除の見通しは?
この感染症の潜伏期間が大体5日だとすると(感染者数が)下がってくるのが見えるとすれば大体2週間後です。例えば、東京都をみると、確かにまだまだ多いんですけど、いわゆる指数関数的に増加する数字は少し収まってきている。ただ、減っていないというのが現状です。
緊急事態宣言の解除に向けて色々な指標がいわれていますけど、やはり重症の患者さんが減らないと解除はできません。
■地域によっては一部解除も?
――重症者が減るのはまだ先?
いま見えている姿としては、場所によって全然違うということです。東京を含めた1都3県は、まだまだ増える傾向が見えています。一方で、栃木県はかなり下がっている方向が見えてきている。
緊急事態宣言の期限は2月7日ですけど、そのときに解除される所もあるかもしれないです。
――東京は「500人を下回る」という目標もあるが?
感染者の1週間の平均をみるわけですけど、500人を切るというのは2月7日は、ちょっと難しいかなという感じです。特に重症者の数からすると、1都3県は「解除は厳しい」と、比較的、今の段階から想像できるかなと思います。
■「人の集まる機会」に対策強化?
――緊急事態宣言を延長するなら、2月末まで?3月末まで?
それはひとえに、どれくらい対策を(市民が)やっていただけるかになると思います。なるべく緊急事態宣言の期間を短くするのが理想だと思いますが、もう少し強いメッセージならびにお願いをするなら、来週(今週24日の週)あたりかなと。評価をした上で、場合によってはもう少し強い対策を。
例えば、特措法の中であげられるようなところでいうと、「人の集まる機会をどうするか」というようなお願いも選択としてはあるかなと思います。
これまでも、昨年3月末には、50人以上の集まりはやめて下さいというお願いをしています。海外でも、人の集まる時間、結婚式、葬式だったり、例えばオーストラリアなど10人とか20人までとか呼びかけている国もあります。「人の集まる機会」をより厳しくお願いすることも今後は必要になります。
■政府のメッセージ発信「共感」と「わかりやすさ」を
――政府のメッセージ発信が響かないとよく言われるが、どう感じるか?
やはり、リーダーである政治家が、きちんとメッセージを出すことはとても大事だと思います。
しかし、恐怖によって人を支配するというのは、昨年の4月5月はまだまだ新型コロナのことがわからなかったので、恐怖に頼って行動を変えてもらいましたが、1年経つ中で、今は、「共感」だったり、「わかりやすさ」だったり、「透明性」に力を入れて、「なぜこれをしなければいけないのか」というところを1人1人に理解してもらうことが大事だと思います。
――菅首相にどのようなメッセージ発信を期待?
そうですね・・うーん・・。やはり総理もいつかおっしゃったように、医療の専門家ではないですから、わからないことは専門家に頼るというのは致し方ないと思います。しかしながら、きちっと専門家に聞いた上で、自分なりにはこう解釈しているんだということで、ご自身の言葉で語っていただきたいなと思います。
100年に1回というピンチの中で、市民にどうしてほしいのか、きちんと丁寧に説明をすることはお願いしたいと思います。
そしてもう1つ、ワクチンについて。
ワクチンはやはり日本においては、これまでも非常に難しかったという背景があります。代表的なところでいうと、子宮頸がんのワクチンです。世界中で普通に使われているこのワクチンの推奨が十分にできておらず、接種が進んでいない。当然、今回のワクチンも、色々な批判がありえるんだと思います。ワクチンに対して、私は非常に期待しています。もちろん、効果や安全性を、我々は監視をしていく必要があります。その上で、重要になるのは、政府からのメッセージですし、人々がそれを信頼しているのかということが、一番重要になってくると思います。
■「GoToトラベル」は制度設計の見直しを
――旅行をしたりできるのはいつ?
今まさにやっていただきたいのは、「GoToトラベル」と「GoToイート」の制度設計です。
これは分科会でも昨年の8月9月に提言を出しているが、いわゆる小規模な分散化したものであれば、比較的感染リスクは抑えられるということがわかっています。東京から箱根だったりに家族で温泉に行ってほかの人にあまり会わずに帰る。その中で感染が広がるわけではない。
やっぱり、問題なのは、職員旅行や修学旅行に使える、ピークも連休も使える、ああいう制度設計だと感染リスクを高めることになる。
経済的な支援として非常に効果があるとわかっている制度なので、ぜひ一時停止している間に、制度設計を見直してほしい。
■「“黙食”は意義がある」
――感染対策で、お店を見分けるポイントは?
難しいですね。私が今どう判断しているかというと、やはり(店員や客が)話をされてる方が多い飲食店は、私自身は行かないようにしています。マスクをしていなかったら特にですが、お話をしているとマイクロ飛沫があるわけです。
最近、「黙食」といって黙って食べるトライをしているところがありますが、あれは非常に意義があると私は思っています。ラーメン店や牛丼のお店だったり、いわゆる1人でまわりも黙って食べる飲食店は、感染リスクは比較的少ないです。
■コロナの初期症状「多くの人が理解できていない」
――個人でできる感染対策は?
いま一番、家庭内でやっていただきたいのは自分の体調の確認です。新型コロナの症状について、やっぱり多くの方が理解されていないと我々は非常に課題に思っています。
新型コロナの、特に初期の症状は「少し咳が出る」、「喉が痛い」、場合によっては違和感程度。あと「熱が出る」。このいずれかがあった場合には、今の状況では、新型コロナかも、と思ってもらった方がいいです。
「鼻水」ももちろんないわけじゃないけど、逆にちょっと少ない。「倦怠感」は、睡眠の質などによって朝だるいときもあるのでなかなかわかりづらい。よく受診につながるのは、味覚と嗅覚の障害ですが、これは、発症してから数日経って出ます。
一方、人に一番感染させるのは、「咳が出る」「喉が痛い(または喉の違和感)」「発熱」この前後2日間です。ちょっと症状があるけど、約束しているし(人に会いに)行った、みたいな形で結構広めることもあります。
体調に敏感になっていただいて、喉が痛い、咳が出るなどという時には、約束をキャンセルできるように、ということはとても重要だと思います。
(2021年1月20日取材)
【イチからわかる 新型コロナ】
2年目に突入した新型コロナウイルスとの闘い。その最前線で奔走する専門家たちに、さまざまな疑問をぶつけた。政府の政策決定の舞台裏やワクチン開発、医療現場の現実とは。
【和田耕治:プロフィール】
国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授、厚生労働省の専門家の会議・アドバイザリーボードのメンバーとして新型コロナウイルス感染分析を担う1人。