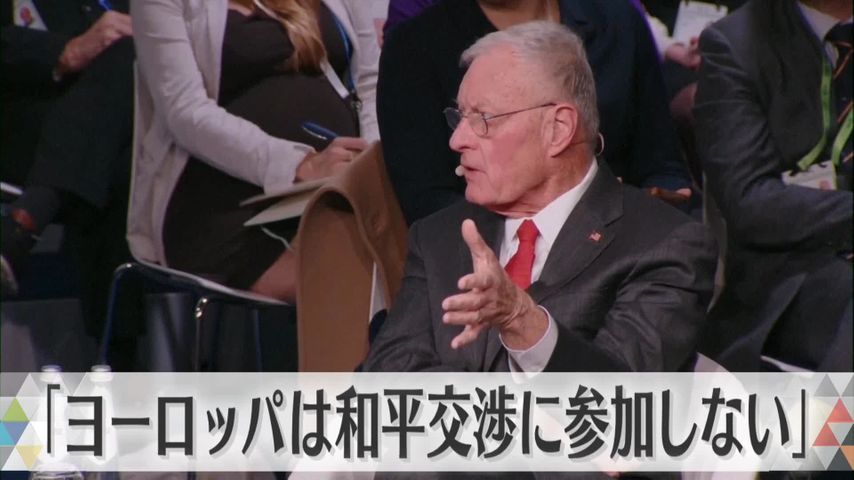福澤朗さん語る「あなた」に伝える震災報道

『真相報道バンキシャ!』のキャスターを務める福澤朗さん。まもなく発生から10年を迎える東日本大震災の瞬間は、番組の打ち合わせに向かう途中だった。テレビ報道に長く携わる中で感じた「災害報道」の変化とは。コロナ禍におけるメディアの役割は。福澤さんに聞いた。
■地下鉄のホームで地震に遭遇
2011年3月11日、地震発生当時は地下鉄銀座線のホームにいた。『真相報道バンキシャ!』の定例打ち合わせのため、日本テレビ本社に向かうところだった。
「電車が入線してきてドアが開いた瞬間に『ピー!ピー!ピー!』と、けたたましい警戒音が聞こえました。『誰かが非常ベルを押したのかな』と思って電車に乗ると、車両がぐわんぐわんと揺れはじめた。それですぐホームに戻って柱のそばにうずくまり、揺れが収まるのを待っていました」
メールや電話は不通で何が起きているのか正確にわからない。地下鉄も動かない。徒歩で日本テレビに向かうことにした。
「国道沿いを歩いていると、途中で何度も余震があって、ビルのガラスが割れて落ちてくることもありました。揺れるビルから女性が悲鳴を上げて道路に駆け出してくる。車がビュンビュン走っている中でした。人身事故になり得るな、危ないなと思いながら歩いていました」
到着するとスタッフが「福澤さんこんな状況なので(打ち合わせありません)」。スタッフルームのテレビで津波が各地を襲う中継映像を目の当たりにした。
「テレビに向かって『逃げてー!』と思わず声を出したことを覚えています」
■隠れた声を忘れてはいけない
これまで、キャスターとして被災地を何度も訪れてきた。印象深いのは発生から半年後の9月、宮城県女川町からの中継だという。中継先となった病院の一室の壁には、町民のメッセージが一面に張り出されていた。
「時間がある限り一つ一つ読んでいて、小学6年生の書いた詩のような文章に目が止まり、思わずメモしました。『女川は流されたのではない 新しい女川に生まれ変わるんだ』と。想像を絶する出来事のあとの、決意表明の言葉でした。その文章を書いた子も、もう大人になっているわけですね…」
2012年には、発災から1年後の中継で三陸鉄道の田老駅(岩手県宮古市)を訪れた。
「地元の子どもたちをホームに集めて、ぶっつけ本番で声を聞きました。この子どもたちがとても明るかったんです。この明るさの中には、いろいろな苦労やつらさがあって、明るさで打ち消している子もいるのだろうなと」
テレビで伝えられることには限りがある。それでも一面的でない伝え方を模索してきた。
「卓球が好きなので、雑誌の企画やボランティアで卓球のイベントを被災地で開くことがありました。『良かったら参加してください』なんて体育館で声をかけると、『うるさい』『静かにしてくれ』と言われることもあります」
「取材でもカメラが回っているときは、みなさん明るくしゃべるけれども、カメラが回っていないところで詳しく被害の状況などを伺うと『思い出したくない』という思いがあるのがわかる。報道では、取材に答えていただいた方の話をお伝えすることになるのですが、その裏には避難所のテントの中でじっとしている方がいい、答えたくないという人もたくさんいらっしゃるんです。その方々の声を僕たちは忘れちゃいけないなと思います」
■テレビの前の「あなた」に伝える
キャスターとしての長いキャリアの中で、災害報道の変化をどのように感じるのだろうか。
「テレビを見ている『あなた』に伝えるという意識が強くなったと思います。より一人ひとりの心に刺さるような問いかけ、語りかけを増やすようになりました。『すぐ逃げてください。身の安全を確保してください』。あなたに言っているんですよ、と。それだけ災害が相次いで危機意識が高くなったことの現れだと思います」
震災特別番組『NNN未来へのチカラ』(3月11日(木)午後1時55分~7時00分放送)に出演する。
「どうしても記憶が薄らいでくるという部分があります。『3.11』と呼ぶと歴史上の出来事のようになってしまう懸念がある。でも決して過去のものにしてはいけないし、記憶を残して。寄り添っていかないと」
震災発生当時の被災地と、新型コロナウイルスの影響で深刻な打撃を受ける各地の状況が重なって見えるという。
「ボランティアに来てほしいけれども、受け入れ体制が整わない状況で大挙して押しかけても不都合が起きるので断るという状況がありました。いまも、観光客に来てほしいけれども、それでコロナ感染が広がってしまっては困る。複雑な心境は似ているものがあるのではないでしょうか。そういう状況だからこそ、僕らは、メディアは、試されているなと思いますね」
「ソーシャルディスタンスの時代ですが、オンラインで繋がることもできる。現地のものをオンラインやアンテナショップで購入することで、現地の方の仕事の応援ができるといいですね。やはり応援するっていうのはお金を落とすことですから。東北の魅力は海産物やお酒、枚挙にいとまがないですよ。とりわけ福島の日本酒はレベルが高い。僕もよく買って家で飲んでいます。いま、飲食店の需要が減って日本酒業界がダメージを受けていますから、家飲みされる方は、ぜひ東北のお酒を買ってほしいなと思いますね」