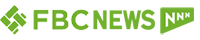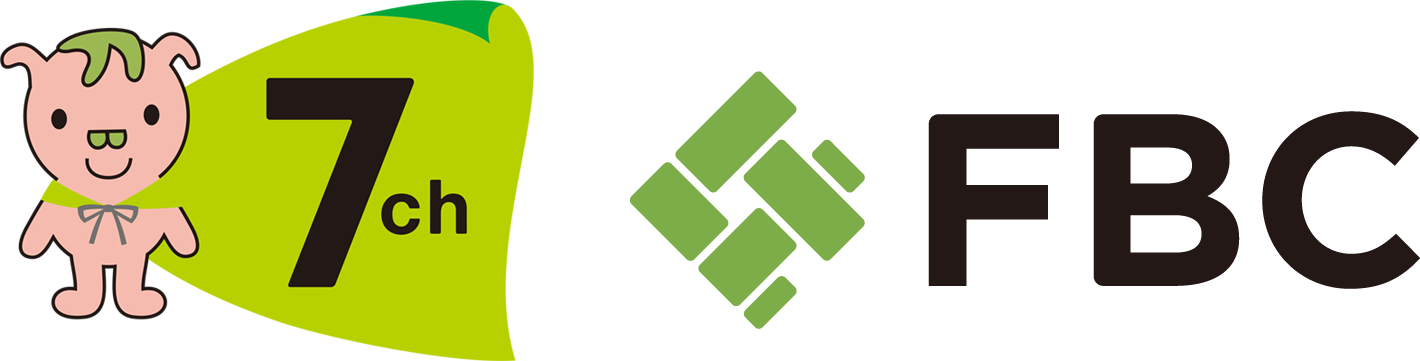【特集】使用済み核燃料の乾式貯蔵施設とは 関西電力が県内全ての原発に設置方針 原子力規制委員会が現地調査
関西電力が県内全ての原発に設置する方針の使用済み核燃料の乾式貯蔵施設を巡って、おおい町の大飯原発で3日、原子力規制委員会による現地調査が行われ、建設予定地の安全性に問題がないか確認しました。
現地調査では規制委員会のメンバーが2か所の予定地を見て回りました。このうち、周辺の山を切り崩して平らに造成した地点は、広さおよそ6000平方メートル、海抜88メートルで、4号機から西側に140メートル離れています。メンバーは図面と照らし合わせながら、斜面が崩れる恐れがないかなど、安全性を確認しました。
■原子力規制委員会 山岡耕春委員
「少し標高の高い所にキャスクを設置するにあたって、すぐそばの斜面が影響するかどうかというところをかなり重点的に調査した」
関西電力はこれまでに、県内全ての原発の乾式貯蔵施設の設置を原子力規制委員会に申請していて、審査が進められています。
そもそも乾式貯蔵施設とはどういうものなのでしょうか。
原発から出る使用済み核燃料は、原発内の燃料プールで冷やしながら保管しています。一方、原発の敷地内に設ける乾式貯蔵施設は、十分に冷却した使用済み核燃料を金属製の専用容器に入れて空気冷却で保管するもので、茨城県の東海第二原発で導入されています。また他の原発でも導入の動きがあります。
関西電力は、この施設を使用済み核燃料を県外にスムーズに搬出するための"準備施設"と位置付けています。すぐに運びだせるよう、荷造りをしておくイメージです。
■関西電力 高畠勇人原子力事業本部長代理
「置けるようになったから、ずっと置いておくことは一切考えていない」
一方、使用済み核燃料の県外搬出計画が予定通りに進まない中で、なし崩し的な長期保管も懸念されています。
■杉本達治知事
「(設置の)事前了解をするかどうかといえば、当然のことながら今回の話に決着ついてなければ事前了解はない」
乾式貯蔵施設のように、原発の敷地内に新しい設備を作る際には、原子力規制委員会の審査を受ける必要があります。県は審査を受けることは認めているものの、審査をパスしたとしても、設置を認めるかどうかは2月中に示される搬出計画の内容を見極めて判断する方針を示しています。