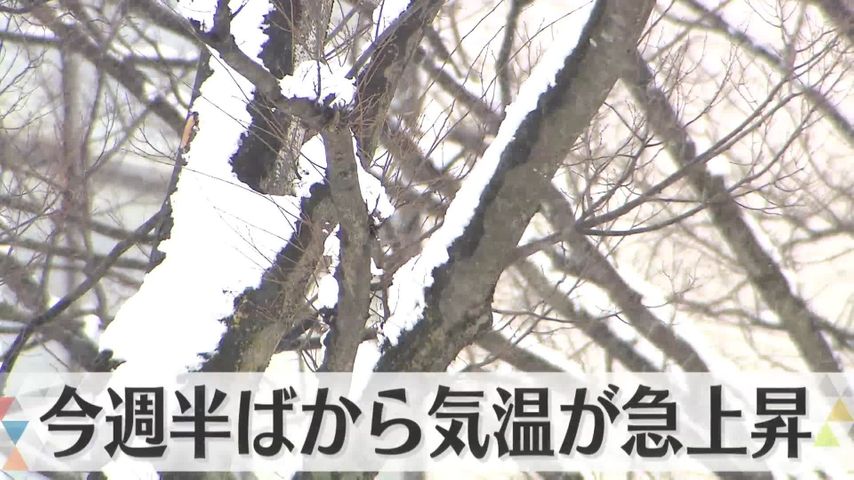【沖縄戦と首里城】大嶺直子さん証言 前編

去年10月、火災に見舞われた沖縄の首里城。75年前の沖縄戦でも焼失し、再建まで半世紀近くかかったこともあり、去年の火災は沖縄の人々に大きな衝撃を与えた。
その地下に巨大な地下壕(ごう)が存在する。この壕は、沖縄戦で、アメリカ軍と対峙(たいじ)した旧日本軍の第32軍が、一時、司令部を置いた場所で、一帯は激戦で焼け野原となり首里城も焼失した。
戦後は、崩落の危険があることなどから立ち入りが禁止されていましたが、去年10月の首里城火災をきっかけに、戦争の記憶を次世代に伝える場所として壕の保存と公開を求める声がいまあがっている。
75年前、いったい何があったのか。私たちは首里城の沖縄戦を知る方々から数々の証言を伺った。戦争を知らない世代にいま伝えたい、知られざる地下壕に秘められた戦争の歴史とは。
◇
大嶺直子さん、94歳。
沖縄戦がはじまる1年前、沖縄県立第二高等女学校を卒業し、校長の推薦で第32軍司令部に事務員として従軍。
司令部の初期段階からを知り、第32軍を率いた牛島司令官や参謀など軍のトップの様子を知る、数少ない証言者。
◇
■高校卒業から司令部へ
昭和19年に高校を卒業した大嶺さん。なぜ司令部に従軍することになったのかーー。
【大嶺直子さん】
(高校卒業後)私、行きたい学校があったんです、本土の方に。それは気象関係の勉強ができる学校、今でいえば気象台(のような)。私、理数科が好きだったし、私たちが卒業する年から女子が受けられるようになるって聞いたもんですから、受けたわけよ。そしたら合格したもんだから、それを校長先生に報告して「受かりましたので向こう行きます」って言ったときに、稲福全栄校長が「沖縄は戦争が来る」と。それまではもう浮かれてるから、戦争のことなんか、戦争がくるってことなんか考えてもなかったね。それが、校長先生が「沖縄が戦争になるんだよ。いま本土行ったら家族がバラバラなって会えなくなるし、今ちょうど32軍司令部が学校に推薦を頼まれているから、おまえ本土に行かないで、ここに行きなさい」って。それが最初ですね。
◇
■初期の司令部へ そして首里城の地下壕へ
事務員として従軍した大嶺さん。1年ほどたった昭和20年4月ごろ、首里城の地下につくられた第32軍司令部壕へ移動したというーー。
【大嶺直子さん】
軍司令部は、最初、首里じゃなくて、坂下っていう、いまいったら松川ってところですけど、そこにあった養蚕試験場に軍司令部が入った。首里の準備の段階で。そこに最初行きましてね、そこで1年くらいいましたかね。最初の準備の段階から、私ずっと軍司令部に入っています。
事務的なもの、軍隊の名称で言ったら「筆生」それが私の仕事。それから1年くらいしてからでしょうね、首里城の近くにあった師範学校だったかな…男子の学校があった。そこに一時、壕に入る前ちょっとだけだけど仕事をしていて、いよいよ首里城の地下に壕が出来上がったから、壕に入った。
◇
■劣悪な環境も「お国のため」と懸命に 司令官たちが見せた意外な姿
壕に入ってからは、事務の仕事はほとんど無くなり、炊事など司令官たちの身の回りの世話が中心となった。
流れるほど水がしたたる壕の中は、湿気がひどく換気も悪い過酷な環境だったが、当時は全く気にならなかったというーー。
【大嶺直子さん】
(壕の中で爆撃は)感じなかったです。堅固でしたよ。別に揺れたりとかはなかったです。壕の中の階段降りていった所に炊事場があるので、その炊事場から飯を運んでというのが、壕に入ってからの主だった仕事ですね。端遣いと炊事…食事のこととかですね。
Q.壕の中は部屋のように分かれていたのか?
【大嶺直子さん】
報道の新聞社の人がいる場所があるし、いろいろあったと思いますよ。私たち女子はちょっとくぼんでいた、区切られたところにおりました。当時は、暑いとか、湿っぽいとかこれっぽっちも考えずに、とにかく一生懸命やろうという気持ちしかなかったです。もう「お国のために」っていうか、務めっていうか、責務だと思って入ってますから。今思えばですけど、あれでよく我慢できたなと思いますよ。
◇
沖縄戦において、日本軍は住民を守るどころか、避難場所から追い出し、食べ物を奪い、虐殺するなど、冷酷非情であったと言われることが多い。しかし、大嶺さんが接した軍のトップたちはそうではなかったというーー。
【大嶺直子さん】
本当に牛島閣下はお優しい方でしたよ。自分よがりのことかもしれないけど、本当に司令部の方々は、命をささげて本土の防波堤として沖縄に死ぬのを覚悟でいらしてるんでしょ。そして、一生懸命頑張ったんですよ。本当にね、死に物狂いでみんな頑張っておられました。私たちも、そういう気概というものを…やっぱり一緒になってやろうっていう気分で(いた)。
◇
特に大嶺さんの直属だったのが広報担当の木村参謀。東京に大嶺さんほどの年頃の一人娘を残してきたため、「戦争が終わったらお姉さんとして娘と一緒に仲良くしてちょうだいね」と語り、かわいがってくれたという。
(後編へ続く)