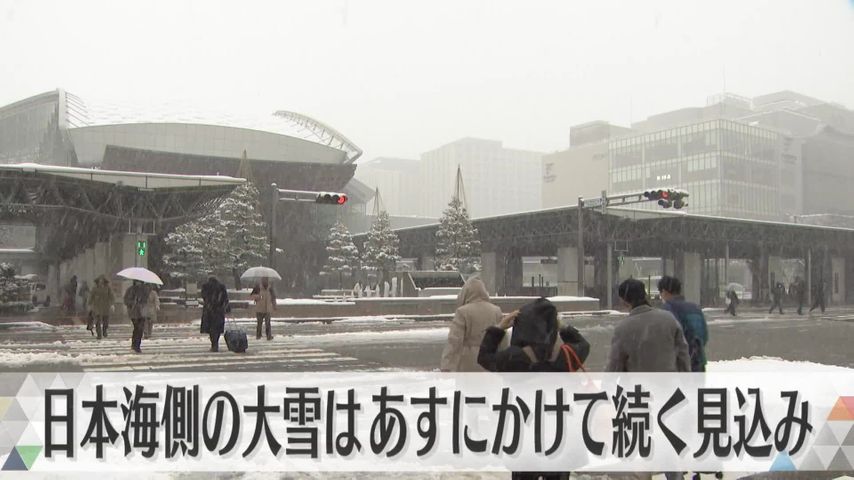ごみ収集車“やりがい”高めて物流の循環を

ごみ収集をデジタルの力で効率化する、座間市と小田急電鉄。なぜごみ問題の中でも「ごみ収集」に特化して取り組むのか。その先に目指す、循環型社会とは。
■デジタル化で職員のやりがいを生む
神奈川県・座間市では、以前よりごみ問題に取り組んできた。市民への啓発や、ごみ収集車を市のキャラクター「ざまりん」でデコレーション。収集員が10日に1度ワックスをかけて磨くことで、子どもたちにも愛されるごみ収集車を保ってきたという。
2019年からは、ごみ収集の問題に着目して、小田急電鉄と連携して「ごみ収集のデジタル化と効率化」にも取り組み始めた。米国ベンチャー企業ルビコン・グローバルの技術を活用したものだ。
従来のごみ収集では、紙の地図を用いて行っていたが、座間市直営のごみ収集用トラックすべてにタブレット端末を搭載。端末上の地図やシステムを利用する効率的な業務が可能となった。
このシステムは、以下4つの業務をサポートする。
(1)「ルート・サポート」 あらかじめ集積場を登録することで、ルート案内やルート変更がスムーズになる
(2)「ワーク・サポート」 車の位置情報や収集状況の管理がリアルタイムに把握可能なうえ、収集量を入力すれば自動的に管理・集計ができる
(3)「ドライブ・サポート」 急ハンドル、速度状況、急発進などのドライバーの運転記録や、車両の点検情報の管理ができる
(4)「スマートシティ」 不法投棄や道路の劣化などを撮影し、管理者に送信できる
一つひとつの効率化は、地味に見えるかもしれない。しかし、業務の効率化や見える化に加えて、“仕事のやりがいを生む”ことに大きな価値があるという。不足するごみ収集の担い手を増やすこともこの取り組みの重要な要素だと、座間市環境経済部資源対策課の依田玄基さんは話す。
「今回デジタルを導入したことで、『やりがいのある仕事をしている』という意識が職員に生まれました。これは大きな効果です。廃棄物処理の現場に、小田急電鉄さんのような外部の方が入り、最新の機材を渡されて。自分たちが最先端のことをやっているという意識の変化があります。かっこいいとか、単純ですけど大事だと考えています」
■ごみ収集事業者が見つからない現実
「ごみ収集には、きつい、きたない、きびしいの3Kのイメージも根強い。こうしたイメージを変えていきたい。その課題感が一致して、座間市と小田急電鉄で取り組むことにしました」
こう話すのは、小田急電鉄サーキュラーエコノミーPJ統括リーダーの正木弾さん。小田急電鉄では、沿線都市の課題解決を目指し、新規事業を検討。その中でごみの問題に注目したという。
「ごみを極力減らして、資源として循環させていくことが大切と考えていますが、お恥ずかしいことに、地域で一番ごみを排出している事業者のひとつが、私たち小田急電鉄です。リサイクル率をもっと高めたいと考えていますが、経済的に見合わないこともあります」
背景には、廃棄物処理費用の高騰がある。日本は世界で第3位の廃プラスチック輸出国(※2017年時点 ジェトロ調査)で、以前はその主な輸出先が中国だった。しかし、2017年末、中国は主に生活由来の廃プラスチックの輸入を禁止。日本の廃プラは東南アジアや台湾へ輸出されるようになったが、これらの国・地域も次々に輸入規制を導入した結果、国内での処理率を高めなければならなくなっている。
その一方で、廃棄物の回収・運搬・処理に関わる事業者は、人手不足が慢性化している。また、通販市場の成長により、人手不足には拍車がかかっているという。商品を届ける物流とごみ収集は、働き手からすると近い仕事だ。物流業界の人材ニーズ増加による影響も少なくないのでは、と正木さんは推察する。
「リサイクル技術があっても、遠い場所にあったり、そこまで持っていってくれる収集事業者が見つからなかったり、リサイクル率を高められない現状があります。そもそも、法人が排出するごみを処理してくれる収集事業者が見つからないこともあると聞きます」
ごみを排出する量が多い事業者として、収集事業者を探せないことに大きな課題を感じている。このままでは自治体のごみ収集も難しくなるのではないか。そんな危機感から、今回の企画が生まれたという。
「循環型の社会を作る上で、ごみや資源が、適切な処理場まで運ばれることが大事になります。その収集、運搬の人手が不足していると、道が閉ざされてしまうのと同じです。これまで、鉄道や不動産など“見えるインフラ”を整えてきた私たちが、街の“見えないインフラ”に役立てたらと考えています」
■「リバースロジスティクス」を街のインフラに
テクノロジーで効率化をはかり、よりよいアイデアを出したり、市民を巻き込む活動にしたりするのが、人間の仕事と考える依田さん。すべては、子どもの未来のために。
「身近なことから始めて、一人ひとりが行動変容を起こすことが大事です。SDGsが流行りだから取り組むわけではありません。これまで我々先進国は、海外の負担の上に成り立ってきた。このままの状態が続いたら、私たちの生活も成り立ちません。だからSDGsが必要で。地球の裏側にまで思いを馳せて、偏りのないユニバーサルな解決策を掲げなければ、子どもの暮らす未来はないんです」
目指すのは、消費者や利用者から生産者へと向かう物流「リバースロジスティクス」を確立して、循環の血流をつなぐこと。
「ものが生産されて消費者に届くまでの流れを血液でいうと動脈と捉えた時、発生したごみを適切な形で運び、再度使える形に戻す流れを静脈と考えています。この静脈を『リバースロジスティクス』と呼んでいます。使い終わったら、また使えるように戻す。適切な処理場に運搬して再生する。そしてまた人々の生活の中で紹介する。このサイクルを自治体主導で作れたら、多くの企業が循環の取り組みに入りやすくなると考えています」
市民は「ごみを出さない」「資源を残す」「食べ物は残さない」といった身近なことを。その裏の、社会に還元される仕組みを自治体や企業がつくることで、循環型社会は完成するのかもしれない。
※写真は「ざまりん」でデコレーションされたごみ収集車
◇
この記事は、日テレのキャンペーン「Good For the Planet」の一環で取材しました。
■「Good For the Planet」とは
SDGsの17項目を中心に、「地球にいいこと」を発見・発信していく日本テレビのキャンペーンです。
今年のテーマは「#今からスイッチ」。
地上波放送では2021年5月31日から6月6日、日テレ系の40番組以上が参加する予定です。
これにあわせて、日本テレビ報道局は様々な「地球にいいこと」や実践者を取材し、6月末まで記事を発信していきます。