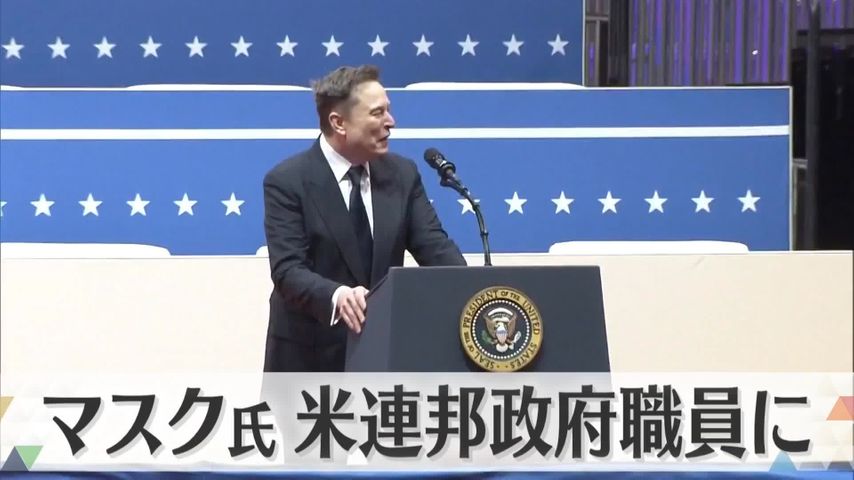手作り漬物がピンチ 6月から衛生面の対応強化で
今、農家などの手作りの漬物が、ピンチを迎えています。助田記者のリポートです。
助田記者「こちらにずらりと並んだ漬物。皆さんにもお気に入りのものがあるのではないでしょうか。その漬物、もしかしたら食卓から無くなってしまうかもしれません」
富山市総曲輪にある地場もん屋総本店。40から50の農家や生産グループが漬物を出品しています。しかし。
地場もん屋総本店 田近寛充店長「こちらの赤カブの漬物なんですけども、八尾の大長谷で作られている漬物なんですが、実はこれなくなっちゃうんですけど」
6月から一部の生産者が手作りの漬物の出品をやめてしまうのです。
田近寛充店長「確実にやめると聞いている生産者さんは8名、今のところいらっしゃいますね」
その理由は漬物の製造に関わる法律の改正です。
2012年に発生した集団食中毒で北海道札幌市などで8人が亡くなりました。原因は食品会社が製造した白菜の浅漬け。これをきっかけに2021年、改正食品衛生法が施行され、漬物の製造は届け出制から許可制に変わりました。
現在は経過措置期間で猶予されていますが、6月以降は許可がないと販売できません。
県内で漬物製造の許可をとるには、県が条例で定める設備を満たす必要があります。自宅の台所と分けて専用の調理場が必要、手洗い設備はレバー式やセンサー式などにするといった内容で、これまで家の台所や納屋の片隅などで手作りの漬物を作っていた生産者にとっては設備改修が大きなハードルとなっているのです。
田近寛充店長「工事をしなきゃいけないので、その費用面、費用対効果のことを考えられて、ちょっとこれではなかなか厳しいなというのでやめられる方が多いということですね。素朴な商品というか手作り感あふれるものが多かったんですが、そういうものが入ってこなくなるので、直売所らしい商品がなくなるということに関しては、ちょっと寂しい側面もあるかなと思ってます」
一方で、6月以降も漬物の製造・販売を続ける生産者も。富山市細入地域の有志で特産の「らっきょう漬け」を作る「やるまいけらっきょう作り会」は、加工場の流しや包装機などを改修し、5月24日、富山市保健所から営業許可を受けました。
やるまいけらっきょう作り会 森坂義孝さん「特産品であるらっきょうを何とかして維持していきたいというみんなの思いで、継続する決断に至ったんですね。お客様、普通の方々が口になさる食品ですので、やはり衛生的にも十分気をつけてやるというのは当然のことだと思ってます」
しかし改修費用の総額は100万円近くになるとみられ、会では地域の人にも協力を求めたいと考えています。
森坂義孝さん「今まで先輩たちが頑張ってこられたことに対して、私らの世代でやめるというのは心苦しいということで、細々でもいいからなんとか頑張って継続して後の世代につなげていくようなことができればなという思いです」
生産者によって判断が分かれた漬物作り。法改正でより安心して漬物を味わえるという側面もあるだけに、関係者は複雑な思いをにじませます。
地場もん屋総本店 田近寛充店長「営業許可を必ず取って出すという側面から言うと、本当に安心感はすごく大きいので、寂しい部分もあるが安心感もすごく大きくなったなというので、ちょっと複雑なところは正直ありますね」