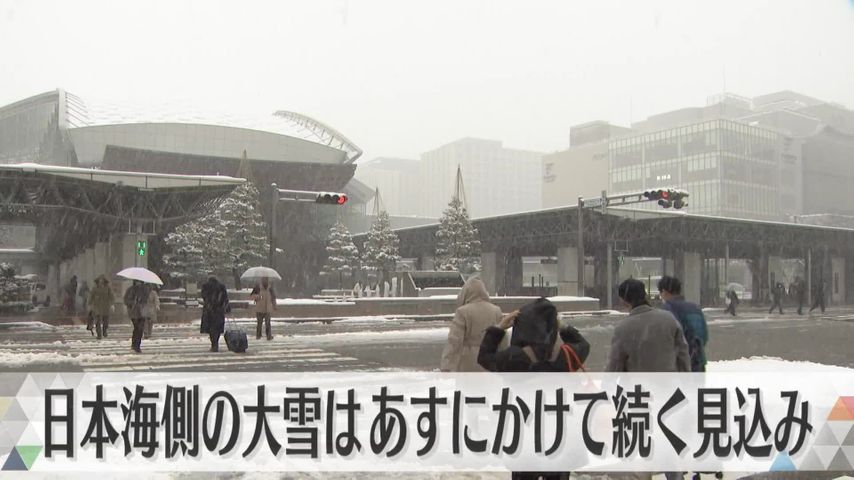男女賃金格差 総理補佐官に聞く なぜ格差?なぜ是正?

女性の賃金が男性の7割程度だという男女賃金格差を解消するため、政府のプロジェクトチームが中間取りまとめを、公表しました。金融や食品製造業など男女格差が大きい業界には、今年中に具体的な対応策を作り始めるよう業界に要請しました。
このプロジェクトの座長で、総理大臣補佐官の矢田稚子さんに話を聞きました。
──矢田さんはパナソニックの人事部や労働組合で賃金や働き方などの課題に取り組んだ経歴をお持ちです
長く企業で働く中で男女の賃金格差は大きいと感じ、政府が掲げる構造的な賃上げを進めるためには、この問題を解決しなくてはという課題意識を持ってきました。
春闘で(賃上げの)いい数字が出てはいますが、男女間や正規と非正規労働者の間の格差を縮めることで、底上げを図ることも大変大事です。また、副産物と言ったらいいでしょうか、女性が労働市場に出ることは、働く人がいない中、ありがたいなと、なります。かつ今まで女性があまりいなかった業界、職種にも入っていくことで、新しい価値観が入り、イノベーションが生まれ、生産性が上がるのではというデータもあります。所得が増えると、少し贅沢してみようかと消費にもつながります。
また老後の支え(年金)の増加にもつながります。需給の面で、どちらにとってもプラスになるという(調査)結果が示されています。
──老後の年金も増えるわけですね
年収の壁(注:年金制度などで配偶者の扶養の範囲となる年収制限)の中で働く場合に比べ、年収の壁を越えると、生涯の所得も大きく向上するというデータがあります。年収100万円以内と150万円まで上げる場合で試算すると、1200万円程度、生涯年収で差があることも今回プロジェクトで報告されました。
──若い頃は男女賃金格差を実感しない人もいます
入社3年目ぐらいから男女の賃金格差が出てきているというデータも明らかになりました。そして勤続年数が延びるほど、管理職に登用される割合も男性の方が高い。かつ女性の場合、退職し、復帰しても非正規を選ぶことが多く、賃金の差が広がる結果になっているかと思います。
私は(男女雇用機会)均等法ができる前に入社し、同期の女性はみんな辞めていらっしゃるんですね。長い人生、何が起こるのか予測できない中で、いろいろなライフプランがあると思いますが、働き続けることも選択肢の一つとして、今回お示しできたと思っています。
日本の一人親世帯の貧困率は高いんです。なぜかというとシングルで子育てしている多くの方が非正規労働に就かれているということです。どんな変化が起こるかわからない中、しっかりと経済的にも稼げることが、必要かと思います。
──専業主婦の方も、独身で家にいる女性もいる。誰もがありたい形で認められる、かつ働けば、男性と同じ対価を得られる。そういう社会であればと思います
そうですね、よく専業主婦の方々からも地域や子供のPTAの活動をなさっているとおうかがいし、残念なんですけど、対価のない労働と言われてますよね。そこも男性にも分かち合っていただいて、今「共育て」というフレーズを政府が出しておりますけど、家庭も子育ても支え合いながら、一緒に社会でも活躍していくことが必要なんだろうなと思っています。
──男性は24時間いつでも働ける、女性はそれができず、賃金が低めという分析もあります
「24時間戦えますか」的な、いつまでこれ続けるんだろうかと。女性が子育てや介護だけを担う労働力ではなくて、男性とも一緒にそこを分かち合い、社会の中でもしっかりと対価を得る労働の方にも参画をしていただきたいなという思いはあります。働き方改革も同時に進めていかなければいけない。
──プロジェクトで業界ごとの課題や対応策が明らかにされました
産業に関係なくある課題は、女性の勤続年数が男性に比べて短い、管理職への登用率が低い、管理職にも本人にも、アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)があって、それが妨げとなり活躍できてないんじゃないかということです。
産業別では、航空業界のパイロットは99%男性で客室乗務員の99%は女性という配置の差がある。金融・保険業界だと、総合職・一般職といういわゆるコース別人事制度、人事管理、これが元々一般的で、それが賃金格差につながっているんじゃないかと。こうした男女賃金格差が大きい5つの業界には、今年中にアクションプラン策定に着手してもらい、早期に公表も、と思います。
──残る課題は
企業だけでなく、社会全体の意識変容が求められています。今回のプロジェクトでも地域の問題がクローズアップされました。「女性は家にいて、結婚して子どもを産むことが幸せだ」というふうなことを、例えば自治会に参加した女性たちが言われて、「いや、もうここにはいられないな」と地方から首都圏に出たというふうなことがあると。データ的にも、男女賃金格差が大きい地域ほど女性が他の地域に流出している。
また、女性は非正規労働者が多いのですが、正規との間で賃金格差があるならその理由、要因分析を進めなければいけない。同一労働同一賃金という当然の考え方があり、労基署の調査なども行われています。非正規から希望すれば正職員になれる道も、特に民間で考えていかなければいけないと思っています。
さらに、民間でなく公務の場でも、非正規社員、正規社員、どちらもですが、同じ仕事、同じ年代であれば、性別にかかわらず同じ賃金なのか、調べる必要があります。
また各都道府県で、ハローワークや事務職には「会計年度任用職員」がいます。(注:自治体によるが、1年契約が原則。契約を更新しても別の部署への異動を繰り返し、昇給があまりない可能性が指摘されている。)自治体の非正規職員も女性が多いというデータなどもあります。
実は、非正規で働く女性が研修を受けると大変効果があるというデータもあります。スキルを身につけ、飛躍的に賃金の高い職種に変わっていると。自分の限界をこれぐらいの仕事かなと抑える側面が女性にはあるかもしれないが、スキルアップに挑戦していただきたいなと思います。男女で進学率にはあまり差がなくて、女性が勉強してきたものを社会で発揮する場面が少ないのが、すごくもったいないなと思うんです。
──1980年代に働き始めた矢田さんや私(記者)は、当時、男性の中に入れてもらう、いさせてもらうのに必死でしたが、振り返ってみれば男女の格差がありました
そうですね。その違和感、朝の連続ドラマではないですけど「はて?」と思うことを提起し、取り組む。先人の女性たちも積み重ねてこられた歴史があると思うんです。そういうことを口に出して改善を求め続けなければと思います。