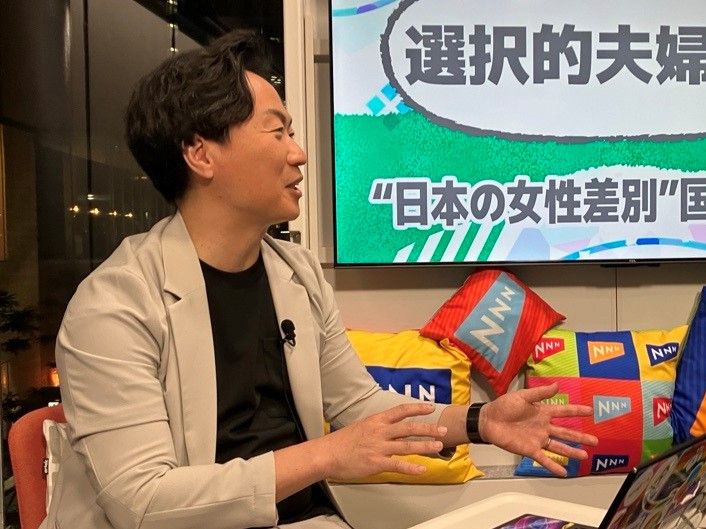「名字選ぶ自由与えないのか?」国連委の問いに“チグハグ答弁”…選択的夫婦別姓が求められる“日本ならではのワケ”
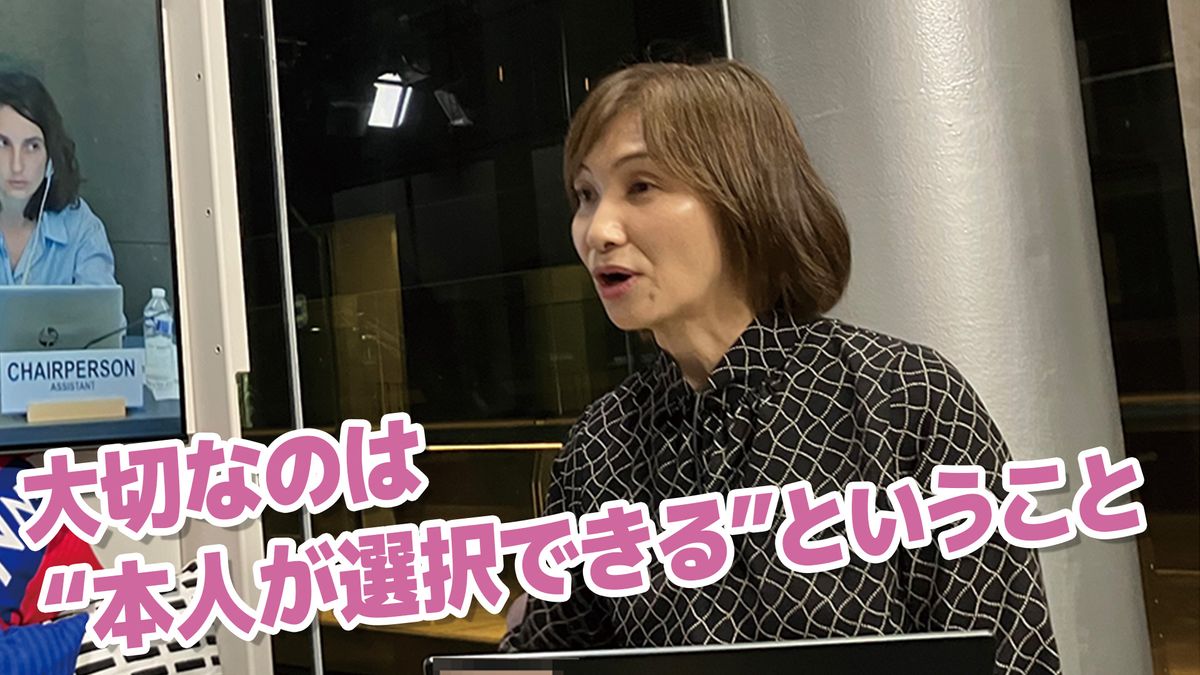
■“国民の理解を得る必要が…” 繰り返さざるを得なかった?
報道局ジェンダー班 白川大介プロデューサー :
今回、議論の場となった女性差別撤廃委員会というのはどういうものですか?
報道局ジェンダー班 庭野めぐみ解説委員 :
女性に対するあらゆる女性差別を撤廃するため、日本も批准している条約の実効の状況を議論します。扱うテーマは、沖縄の米軍による少女への暴力や、賃金格差など幅広い。締結国は、国ごとに報告書を出して、順番に審査が行われていく…というものなので、日本だけ取り上げられて指摘されたということではないです。
白川:ただ、日本はいろんな面で遅れているという指摘は、随分前からあった印象ですが。
庭野:選択的夫婦別姓だけでも、実は21年前の2003年には“民法を変える必要があるのではないか”と指摘をされています。さらに2009年、2016年と合計3回指摘されています。今回も、「日本では結婚で姓を変えるのは女性が多いという現実があり、負の影響が出ている。名字を選ぶ自由を与えることを考えていないのか」という質問が出ました。
白川:日本に暮らしていると色んな自由があるし、自分も大切にしてきたつもりですが、“名字を選ぶ自由”という発想を考えたことはありませんでした。
庭野:私も結婚で名字が変わっています。(庭野という)旧姓で仕事をしているため、戸籍上違う名前なんですが、私はその時に“ものすごく選びたい”と思って吟味をしたかというと、あまり深くは考えていませんでした。
白川:庭野さんは、“私は名字を選ぶ自由を奪われている”と感じていましたか?
庭野:あまり認識はなくて、通称で今も“庭野”を続けていますし、 友達の間でもそう呼ばれているので、“それでいいか”と思ってしまっている部分もあります。地域では違う名前で呼ばれていて、使い分けていることが当たり前だと思わされていた部分もあります。
白川:僕の周りにもそういう女性の方が多いです。今回の“名字を選ぶ自由”という質問に対して、日本政府の出席者はどう答えたんですか?
庭野:「国民の意見が分かれている」「社会全体における家族のあり方に関する重要な問題で、幅広い国民の理解を得る必要がある」と法務省の担当者が答えました。ただこの表現は、政府が必ず言ってきた答弁なんですね。
国連の委員は、伝統的なテーマであることは分かっていると踏まえたうえで、「多くの女性が職場やプライベートでも大きな影響を受けている。今後何らかの決定が出るのか?」と追加の質問をしました。
ところが、政府は「不利益を感じないように、旧姓を通称として使うことの拡大に取り組んでいる」とか、「パスポートとかマイナンバーカードなどに旧姓を併記できるようにした」などと、直接的でない答えで終わってしまいました。
白川:何百回も聞いた表現で僕自身マヒしている部分もありますが、国際的にはどう見られたんでしょうね。
庭野:逆に「議論しない」「導入しない」ということも言わない。曖昧な表現で、判断を先送りしたような感じに聞こえました。法律の規定を読み上げる感じでした。傍聴した日本の(選択的夫婦別姓を望む)NGOの人たちからは「建設的対話をしてほしい」という声があがっていました。
白川:印象的には国会の防御答弁のような…。
庭野:ただ、代表団は各省庁の担当者で、フリーハンドの判断を与えられているわけではないんです。仮に“2025年までに”と個人的に思っていても、当然国会なりを通っていないものを勝手に言うわけにはいかない。手持ちの資料にある文言を繰り返すしかなかったわけです。
■“考え方は国で異なる” 国連で議論する意味は?
白川:選択的夫婦別姓の議論以外では、どんな話題が出てきましたか?
庭野:例えば、女性の健康の問題。中絶手術をする場合には、今の法律では、女性の意思だけではなくて、原則パートナー・配偶者の同意が必要なんですが、こういった規定があるのは、世界でも11カ国のみ。G7では日本だけです。この要件を撤廃する可能性について聞かれましたが、これも法律を読み上げることを繰り返し、特に方針は示しませんでした。
社会や経済のシステムにも質問が出ました。裁判官や大学の先生、企業の管理職に女性がとても少ないことについて「なぜなのか?対策を具体的にどうか」と質問されました。政府も「2019年は何%だったのが、23年は何%になった」などと数字を用意して、「今後幹部を増やしていく」などと言いましたが、抜本的な対策というのはなかなか難しいようでした。
白川:休憩を挟んで、議論は5時間行われたと聞きました。庭野さんは全部見た、ということなんですけど…。
庭野:複数の委員があらゆるところで、日本には、性別による固定的な役割分担意識があると指摘していました。“男はこう、女はこう”という役割意識とか、“アンコンシャスバイアス”とされる無意識な思い込みがある、と。日本政府もこれを認めて、「どう改善するのか?」と何度も質問が出ましたが、「セミナーを行っている」とか、「(啓発用の)動画を出している」と答えるだけで、なぜこの状況が続いているのか、背景に関する言及はありませんでした。
白川:いろいろなところで要望が出ている、包括的性教育の問題に対しても議論が出たんですよね?
庭野:尊厳や性的同意などの権利などの幅広い学びについて、学校教育に導入しないのかという問いでした。ただ大体は「学習指導要領に基づいて、発達段階に応じた適切なことを教える」と、いつもの答弁。最後には「性に対する考え方は国によって異なる」として、終わってしまいました。
白川:包括的性教育は、性に対するいろんな知識を持つことで、自分たちの人生を計画的に、より幸せに生きていくために必要だと私は思っています。国連の委員会でこの話が出るのも、これが人権に関することだから。それが「国によって異なる」となると、委員会の存在意義自体を否定しているようにも思えてしまいましたが…。
■委員長の姿に見た“インクルーシブ”な社会
庭野:今後、日本には、勧告を含む最終見解が委員会から出されます。これも日本だけではなくて、各国それぞれに出されるもので、10月中にも出るとされています。差別撤廃の取り組みについて委員長は「是正の期日を盛り込むので、注目してください」と、あえてクギをさしていました。
その場面で、委員長の手元には資料というか、白いものがあって、それが“点字”だったことに気がつきました。視覚に障害がある方でした。その方が国連の女性差別撤廃委員会の委員長であるということが、誰もが平等な社会、インクルーシブや多様性ということを体現しているなと実感しました。
白川:リーダーといったときに、男性だけじゃなく女性を想像するということは、少しずつ我々も癖づいてきたとは思いますけど、障害がある方というのは正直、想像していなかった部分もある。これも“アンコンシャスバイアス”かもしれないですね。点字で資料が用意されるっていうことがあれば、全く同じようにバリアフリーに働けるはずなんですよね。
■名字で呼び合う日本 変えたくない姓…海外よりも“深刻”
庭野:委員会の翌日、日本への選択的夫婦別姓の導入を求めるNGOの方々などが会見を開いたんですが、「政府の回答がいつものものであり、とても建設的対話とは言えなかった」と失望していました。
日本は、海外よりも名字で呼び合うことが多い。個人を名字で呼び合うなかで、やはり名字を変えたくないという気持ちを持っていて、「大変ささやかな願いではあるけれども、それを私たちは求めてきた」という部分は、なるほど、と思わされました。
白川:確かに!海外の人よりも深刻なんですね。
庭野:いまは“強制的夫婦同姓”で、結婚すれば、全ての夫婦が同姓になる状況。そんな中、「選択する余地をくれないか」と訴えているんです。同姓に納得している人や、これから同じ姓になることで幸せを感じる人たちを、どうこうしようという話ではないと制度導入を求める人たちは説明しています 。
中絶やジェンダーの取材を通じても思いますが、大切なのは、本人が選択できるということ。昔は方法もなく、泣き寝入りした人もいるかもしれませんが、今はいろんな選択肢があります。選ぶかどうかは別として、選択できるかどうかが、本当に豊かな社会につながると改めて思います。
日テレ報道局ジェンダー班のメンバーが、ジェンダーに関するニュースを起点に記者やゲストとあれこれ話すPodcastプログラム。MCは、報道一筋35年以上、子育てや健康を専門とする庭野めぐみ解説委員と、カルチャーニュースやnews zeroを担当し、ゲイを公表して働く白川大介プロデューサー。
“話す”はインクルーシブな未来のきっかけ。あなたも輪に入りませんか?
番組ハッシュタグ:#talkgender