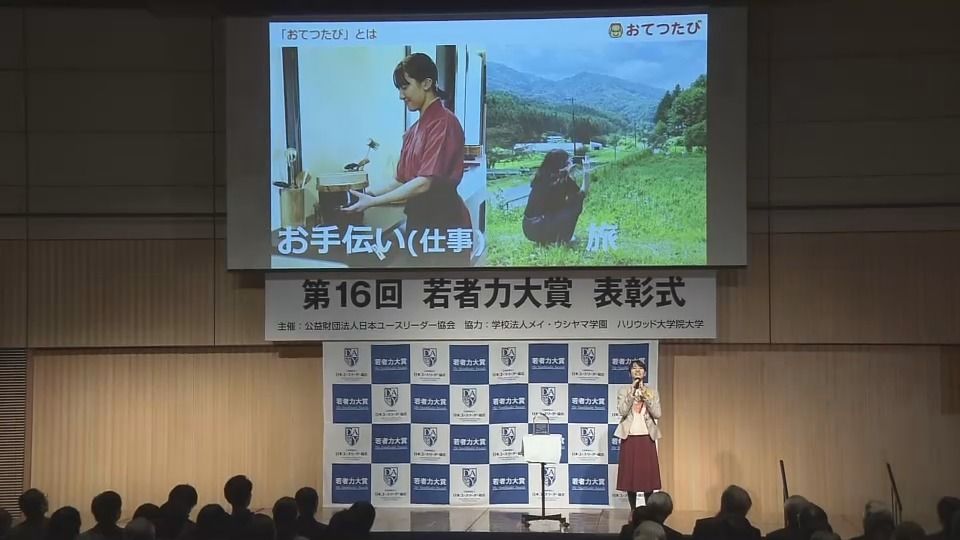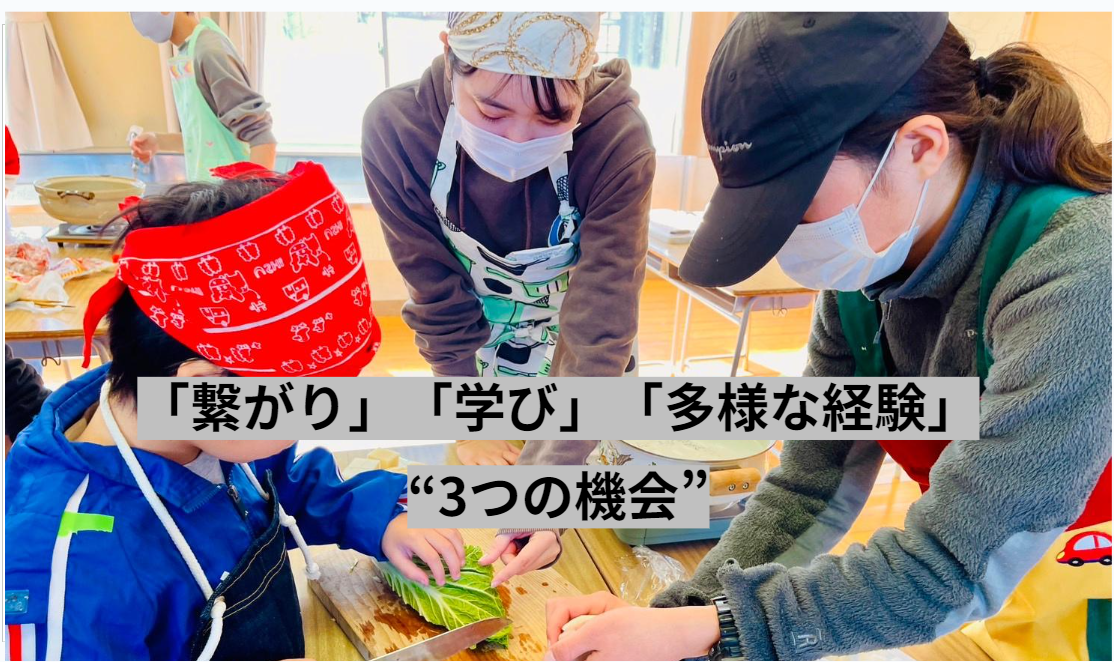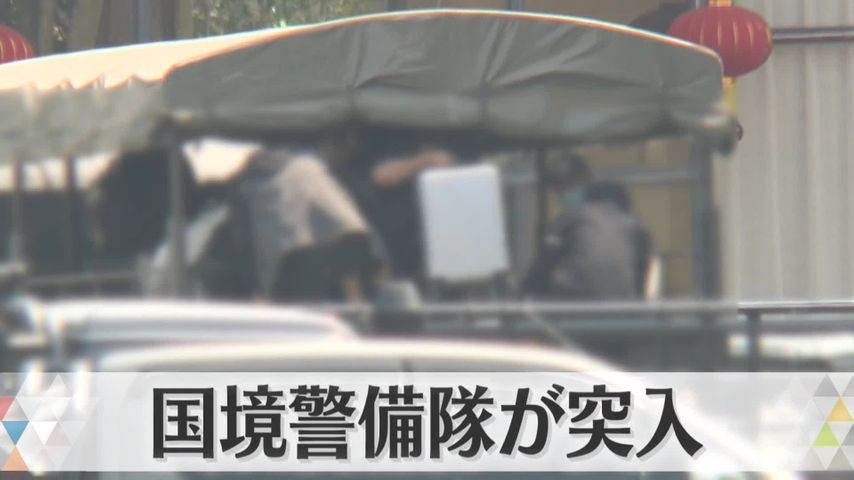「生きている意味ある?そう言わせる社会はおかしい」と若者は立ち上がった
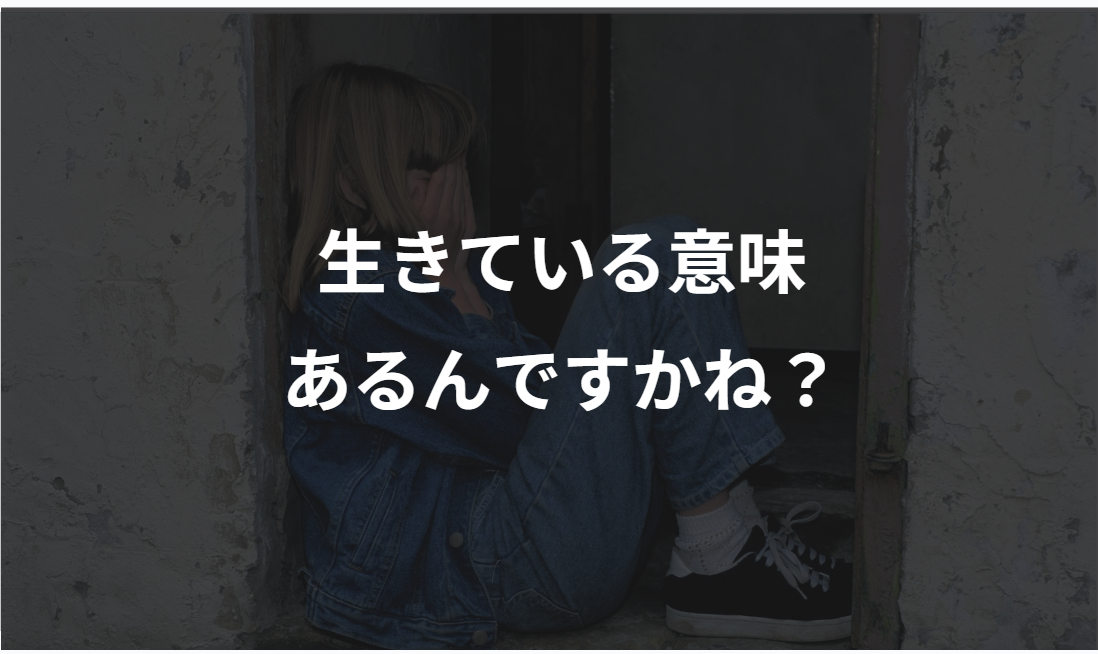
「福島の震災から5年後に、こどもが激減していて、もう避難指示を解除してもしなくても同じなんじゃないの? いずれ消滅するシナリオに変わりないんじゃないのと言われ…」。(和田智行さん)
「日本全体、人が減っていく事実は避けられない。現実を目の当たりにしたときに一番最初にしわ寄せが来てしまうのは(自分が育った)尾鷲のような地域だと思っている」。(永岡里菜さん)──日本社会が抱える闇に気づいた彼らは、あきらめるでも逃げ出すでもなく、解決に向けたプロジェクトに踏み切りました。彼らの思いと取り組みを紹介します。(解説委員・安藤佐和子)
■「人の奪い合い」ではない人手不足の解消法 ~「どこそこ?」という地域にも人は訪れる
2月14日、東京・六本木で行われた「若者力大賞」表彰式。社会課題の解決に取り組む若者たちをたたえ、応援するプロジェクトだ。
大賞に選ばれたのは、「お手伝い」と「旅」を掛け合わせた造語「おてつたび」を創業した永岡里菜さん。地域の人手不足を「おてつだいをきっかけに足を運ぶ“旅行者”」で解消するプラットフォームだ。ポイントは、「どこそこ?」と言われるような地域にファンを作ること。
ホームページを見ると、例えば「花の収穫」(和歌山県御坊市)や「パンの訪問販売」(北海道広尾郡)などのお手伝い募集があがっていて、どの期間、どんな“お手伝いの内容”でいくらもらえるなどの情報が載っている。
永岡さん自身、高齢化率45%の三重県尾鷲市出身で、「人口減少で、日本全体で人を取り合って行く現実を避けられないなら、そこに住んでいなくても、人・モノ・金が日本各地を巡っていく仕組みができないか」という発想から創業した。
ただ、「人手不足解消だけのためにやっているサービスではない」と言い、人手不足をきっかけに、地域を知り、ファンになって帰るという循環をつくりたいと話す。
実際、この「おてつたび」をきっかけに東京と愛媛の2拠点で料理人の仕事を始めた人や、鳥取県の地域おこしを始めた人、さらには「おてつたび先」に嫁いだ人もいて、人手不足解消だけでない、人と人、人と地域の出会いのきっかけをつくっているようだ。
永岡さんは、誰もが居住地と出身地以外にも「好きな地域」を持ち、複数の地域と関わる「関係人口」を増やすことで、地域を支える仕組みをつくることを目指している。
■「ぼくらの地域、課題がたくさんある。裏を返せば全てビジネスの種になり得る」
一方、「誰もいなくなった地域」に人を呼び込み、27件の事業を実現させてきた人物もいる。福島県南相馬市出身の和田智行さんだ。
「人が住まなくなると、町は自然に飲み込まれていく」。和田さんは福島第一原発事故後の南相馬市の様子をそう表現した。
震災から5年後に「避難指示」は解除されたものの、子どもの数は激減。「いずれ消滅するシナリオに変わりないんじゃないの? だったらここに金を投じる必要ないんじゃないの?」と言われ、「切り捨てられても仕方ない状況になってしまった」と感じたという。
しかし、和田さんは「課題はビジネスの種だ」と考え創業。町に人が戻ってくるかどうかの決め手となるのは「子育て中のお母さんたち」と狙いを定め、「彼女たちにとって魅力的な仕事をつくろう」と、人が住んでいない町にアクセサリー工房をつくった。それがきっかけで、女性たちが南相馬に戻って来て働き始めただけでなく、ガラス職人になりたくて移住してくる若者も出てきたという。
これまでに27の事業を立ち上げ、廃炉が完了すると言われている2050年頃までに100のビジネスを創出し、自立した地域にするのが目標だ。
■過疎地では、子どもが不登校でも相談する場所もない~個に寄り添う事業を…
川邊笑さんは徳島県の海部郡出身。人口3400人の町で生まれ育った。小学校も中学校も一校だけ。一クラスだけ。クラスメイトもずっと一緒、という環境だった。良い面もあったが、生きづらさも感じていた。
筑波大学に進学し、学習支援のボランティアの場で出会った10歳の男の子の言葉が人生を変えたという。「生きている意味あるんですかね。やりたいことない」。男児は、両親も亡くなっていて、学校にも行かれていない状況で、川邊さんは「こういうことを言わせる社会が日本にあるんだ」と憤りを感じたという。
その後、地元徳島に一時帰省した時にも川邊さんはやるせない経験をする。こどもが不登校になっているある女性から、「私たちの声って誰が聞いてくれますか?」と言われた。不登校支援の場にすがろうと思っても、車で1時間かけて行かなくてはならない。病院や療育(発達支援)は親が仕事を休まなければ通えない場所にある。
こうした経験から、川邊さんは、「過疎地でも、地域の中で支えていく仕組みを作りたい」と決意した。まず公民館を借り、退職した先生達の協力を得て、「居場所」をつくった。「繋がり」「学び」「多様な経験」をこどもたちに提供しようと、廃校を借りたり、家から出られないこどもたちには出張型にも挑戦している。
「地方に生まれても、家庭がしんどくても、学校に行けなくても、自分らしく人生を描ける日本になったら良いな」と、徳島から過疎地の子どもの未来をみんなで照らしていきたいという。今後は、オンラインも使いながらこどもたちの友だちの範囲をもう少し増やしていくことも目指す。
■「大人もそない、元気ちゃうな」~当たり前に大人が中高に出入りする世の中に…
小澤悠さんの起業のきっかけは「中学、高校にキラキラした元気な大人を派遣し、中高生を元気にしたい」と思ったことだった。3年間で1000人の大人を送り込んだ。ところが、「ふたを開けたらわかったことがありまして。大人もそない、元気ちゃうなと(笑)」。
それで「まずは大人を元気にしなきゃ」と「NEXT SENSEI」という取り組みを開始。
大企業の社員たちに、講師になるための研修を実施。社員達が中高生に、「人生や実体験をベースにしたオリジナルのストーリー」を教材とした講義を行えるよう、キャリアの棚卸しなどを手伝う。
この作業を通じて、社員たちは「なぜ働いているのか」「自分はどういう価値観を持っているのか」を再認識し、自信を取り戻すという。中高生にとっては、働く大人から講義を受けて「職業選択」に向き合う授業だが、教える側の大人にとっても成長の機会となる事業だ。
小澤さんは、「ボランティア休暇のように、(今後)『先生休暇』もできて、当たり前のように、大人が中学・高校に出入りする世の中をつくっていきたいと思う」と、さらに拡大を目指す。
■大事なところに回っていない「お金」と「関心」
「過疎地の存続のため」「困難を抱えるこどもの支援のため」「被災地の自立再生のため」「大人に自信を取り戻してもらうため」…それぞれの問題意識と解決に向けた取り組み。事業化に至るまでに、傷ついたり挫折しそうになったこともあったかもしれないが、信念を持って突き進んでいる。
彼らに「若者力大賞」の賞を与えた団体(日本ユースリーダー協会)は、会場でこう呼びかけた。
「社会で重要なことがたくさんある。もっとお金が回らなきゃいけないけど、回っていない。そして、お金よりももっと大事なことがある。それは『人々の関心』。人々の関心を、大事なことに回さなくてはいけない」。(永野毅会長)
日本にあふれる課題に、がっつりでも、できる範囲でも、まず関心を持って欲しい。何かできないか、考えてほしい。そんな呼びかけに聞こえた。