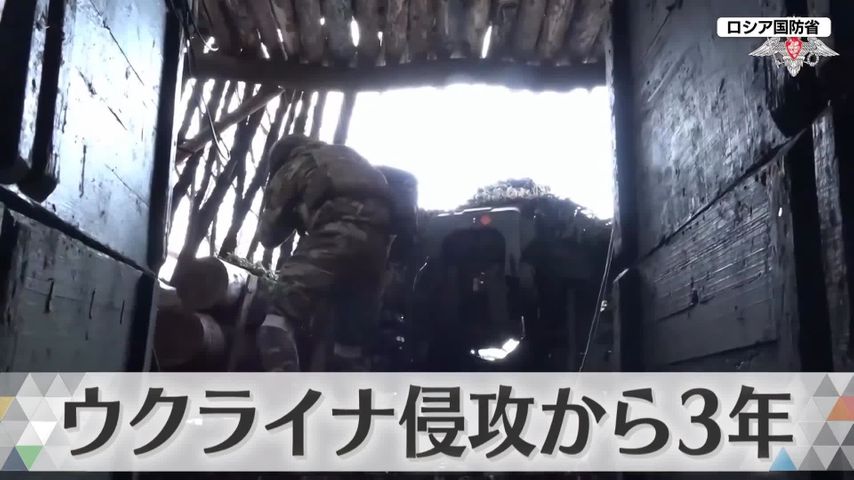バイデン大統領の米国(8)イラン核合意は

アメリカ・トランプ前政権が「イラン核合意」から一方的に離脱して以降、イランではウランの濃縮活動が加速し、周辺国の懸念が高まっている。イラン核合意の行方とバイデン政権の中東政策は? アメリカに詳しい識者4人に聞いた最終回。
■イラン核合意復帰に向けてアメリカは動くか
――藤崎一郎元駐米大使は、トランプ政権時、イランに対する強硬姿勢の反射的利益を受けたのがイスラエルだと指摘したうえで、「バイデン政権では、その路線は修正されるだろう」と言う。
(藤崎氏)
「(バイデン政権の中東政策は)もっと中道的な路線に戻ると思います。イスラエルについては、一旦動かしたアメリカ大使館を戻すようなことはできないと思いますが、パレスチナ問題は、「イスラエルと将来の独立したパレスチナ国家が平和かつ安全に共存する」ことを目指す和平の原則に『コミットしない』としてきたトランプ政権の姿勢から、元へ戻して、和平の原則である「2国家解決」の方に戻るのだろうと思います。ですから、次から次へとイスラエルとアラブ諸国の国交回復を促していたような動きは当面、スローダウンするんじゃないかと思います」
「そのうえで、イランとの交渉ですね。核合意について、アメリカは『元へ戻ることを検討する』と言っていますから。ただイランがきちんと対応せずに、どんどん核の濃縮能力を上げてく場合には、アメリカも『復帰』はできませんが、それでも、私はひそかな…ひそかかどうかは分かりませんが、何らかの話し合いが始まるだろうと思っています」
■脅威はイスラエルではなくイラン
――キヤノングローバル戦略研究所の宮家邦彦氏は、中東におけるパレスチナ問題の比重が変わってしまった点を指摘する。
(宮家氏)
「アラブ諸国が、もうパレスチナ問題についてそれほど関心を持たなくなってしまった。これまで中東和平に相当のエネルギーをかけてアラブ諸国も支援したんですよ。けれども、パレスチナが極めて強い非妥協的な態度を繰り返すことによって、実質的に2国解決策――独立したイスラエルと独立したパレスチナ国家という中東和平プロセスの根幹の部分について、アラファトさん以下アッバスさんまで妥協できなかった。それが2000年以降も続いていて、そのうち過激派勢力ハマスが台頭して、事実上、パレスチナ自体が当事者能力を失ってしまったわけです」
「そうすると、もうイスラエルは交渉の相手はいないのだから、どうにもならないと言って、どんどんどん既成事実化を進めていった…。これが過去20年間に起きたことです。その間、ほかのアラブ諸国は『パレスチナ問題? それは大事だけどね。我々にとってイスラエルはもう脅威じゃない、脅威はイランだ』という状況に変わってきたわけです」
――宮家氏は「イスラエルのみならず、アラブ諸国にとってもイランの核開発は脅威となっている」という。では、そのイラン核合意にアメリカは復帰するのか?
(宮家氏)
「元々はイランが問題だからこそ、オバマ政権は核合意を結んだわけです。それをトランプさんがひっくり返した…これを元に戻さなきゃいけないわけですよ。だけど、戻るか?といわれると、戻らないのでは…と私は思います。考えてみてください、穏健派といわれるロウハニ大統領は、うまくいったと思って『経済制裁がなくなるよ』『これでバラ色だ』と言ったのに、それがひっくり返ったわけですから。もちろんイラン国内の強硬派は黙っていません。『アメリカ、けしからん!』となる」
「結局、イランもウランの濃縮を再開しましたし、『アメリカが相当譲歩しない限り、イランも元には戻さない』と意地を張る。そのうちに6月のイランの大統領選挙がやってくる。そしたらロウハニさんはもう終わって、選挙で強硬派がやってくる可能性がある。その前になんとかアメリカとイランが手を握らなければいけないが、時間がない。イラン大統領選のキャンペーンが4月ごろから始まるわけですから、実質的には3月までの間に、今までの問題を全部ご破算に…というわけにはいかないでしょう。となるとイランの問題も大して動かない」
――イラン核合意は、アメリカにとってヨーロッパの同盟国との関係の上でも重要だと笹川平和財団の渡部恒雄氏は言う。
(渡部氏)
「イランの核合意というのは、ヨーロッパの同盟国との足並みを揃えるうえで非常に重要なので、アメリカは『復帰』と言っていますが、イスラエルは嫌でしょ。イスラエルもアメリカの大事な同盟国なんですよ。加えて、これはトランプ氏のせいなんですけども、イランの態度の強硬化が進んでいて、なぜかというと、あのイラン核合意を決めたのはイランの国際派だったんですが、アメリカが約束を守らなかったから立場が弱まっているわけです。だから、強行に出ないとイランの中でも持たない。そうなってくると、(イランの側も)実はそう簡単に元に戻すことができる状況ではないんです。だから中東というのは、やはり難しいと思います」
■イランを封じ込めるための核合意
――上智大学の前嶋和弘教授は、アメリカのイラン核合意への復帰について、国内の反対派を再び説得できるかもカギになるといいます。
(前嶋教授)
「このイランの対応――実際、イランが平和裡核のコントロールをしてくれるかどうか、それを見ながら(アメリカは)核合意に戻っていくことを、うまく進めることができるのか。逆に言うと、アメリカ国内でもイラン核合意に対して、かなりの反発があります。トランプ政権が一旦、離脱した核合意から、バイデン政権は、国民を(説得して)『離脱ではなくて、イランを封じ込めるんだ。そのためには外交が必要なんだ』とつてのイラン核合意をやったあの段階まで戻れるかどうかというところが、ポイントになるかと思います」
「イラン核合意に関しては、成立時、ちょうど(バイデン氏が副大統領だった)オバマ政権でしたが、あの時もかなり議会の中でも割れました。今回も割れるのかもしれません。なかなか難しいところです。一方でイランは核の濃縮をしていて、やはり危険度は高まるわけですし、瀬戸際で動くということかと思います。このイランの動きに対して、どうやって外交でまとめていくことができるのか、なかなか難しいところだと思います」
4人の識者に、バイデン政権が今後、直面する課題について話を聞いてわかったことは、トランプ路線からの軌道修正が、いかに困難かということでだ。新型コロナの蔓延する中、内政外交をどうハンドリングするのか? 政治経験豊かなバイデン大統領の手腕の見せ所となる。
■4人の識者
藤崎一郎氏(中曽根康弘世界平和研究所理事長、元駐米大使)
※崎は右上が立のサキ
前嶋和弘氏(上智大学教授)
宮家邦彦氏(キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹)
渡部恒雄氏(笹川平和財団 上席研究員)
*この記事は、4人の識者に個別にインタビューしたものを再構成したものです。
(写真向かって左から、藤崎一郎氏・前嶋和弘氏・宮家邦彦氏・渡部恒雄氏)