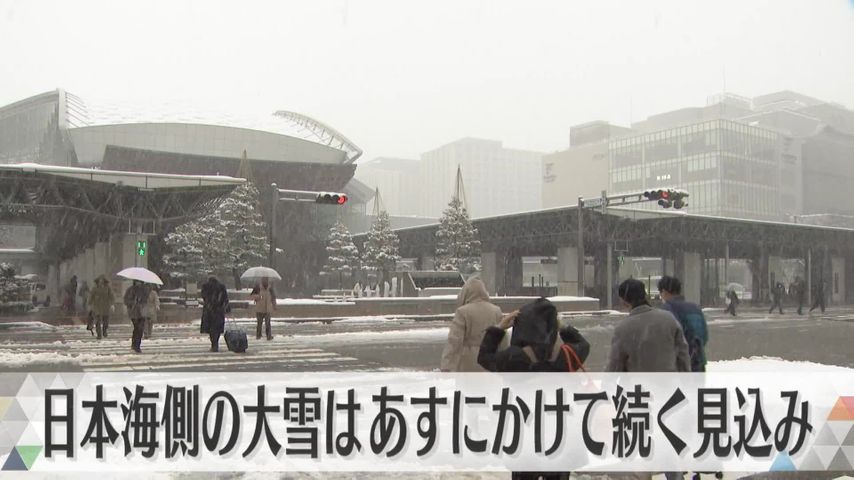【子宮けいがんとワクチン】キャッチアップ接種 20代でも打つべき?──イギリス在住専門医に聞く

子宮けいがんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)に感染するのを防ぐワクチンについて、イギリス在住の江川長靖氏(ケンブリッジ大学病理学部)への取材シリーズ第2回は、日本で来年(2025年)3月まで17歳から27歳の女性を対象に行われている、無料の接種=キャッチアップ接種についてや、過去に報告された接種後の体調不良をどう考えるかなどをお伝えします。
■25歳女性が接種して効果があるのか?
子宮けいがんの原因となるような高リスクのHPV(ヒトパピローマウイルス)は15種類程あります。日本でキャッチアップ接種(注:2024年度に17歳から27歳になる女性も無料で接種できる)の対象の人で、すでに一部の型のHPVに感染していても、ワクチンが対象としている型(7種ある)でまだ感染していないものがあるならば、今後それらに感染する可能性を予防することができますので、一定の利益、効果があるだろうと推定できます。(注:どの型に感染していないかわかる検査はありません)
例えば25歳の人が今接種しても、その前に(性行為などを通じて)感染していた場合には、ワクチンを接種しても、それを治せる・感染をなくしてしまうわけではないので、ワクチン接種前に感染したものから高度異形成(がんの前段階)やがんが発症してきます。
ワクチンはあくまでも、接種後の新しい感染に対してのみ有効です。つまり、キャッチアップ接種をした場合も、15年くらい・特に40歳くらいまでは、接種しなかった場合と比べてがんが大きく減ることはないと考えられます。ワクチンを接種しなかった時と同様に定期的な検診が重要です。集団で見た場合、キャッチアップ接種対象者は定期接種で(小5から高1相当の女性が)接種した時と比べて、半分くらいの効果があると考えていいでしょう。
■ワクチン接種が進むと検診が変わる?
WHO=世界保健機関は、15歳までにワクチンを接種した集団の初回検診年齢は30歳でよいだろうとしています。なぜなら、ワクチンだけで20代で発症する子宮けいがんの罹患(りかん)率が9割減るからです。
実際にイタリアなど検診の推奨を30歳以降に切り替えた国も出始めました。日本は、検診率はさておき、20歳から(他国より頻度の短い2年に1度の)検診を推奨するなど、膨大な医療リソースを検診に使っていますが、将来はワクチンでかなりの部分を置き換えることができるはずです。
ワクチン接種によって、検診の手間や負担、そこでがんの前段階の高度異形成が見つかり、治療しようか悩むことも減らせる。検診システムが変わり、負担が小さくなる可能性がある。議論されることは少ないのですが、これも重要なことだと思います。
■世界は子宮けいがん撲滅に向かっている
HPVワクチンを接種した場合も、ほかのワクチンと同様に、腕の痛みや発熱などワクチン接種に関係した体調悪化が起こることはあります。ワクチン接種に関連した一般的な体調悪化です。これらは普通、時間の経過と共に軽快します。そのようなものとは別に、ワクチン接種前後に何か深刻な疾患や体調不良や病態がみられた場合、どういうことでしょうか?
HPVワクチンの接種によって、HPVへの感染や子宮けいがんは減ることが期待できますが、それ以外の病気については、ワクチンを打った人でも、打っていない人でも同じように発症するでしょう。
例えば、15歳で3回HPVワクチンを接種した場合、ワクチン接種後1か月間に限ったとしても、15歳で発症するあらゆる病気の4分の1(12か月のうち3か月がワクチン接種後1か月にあたる)はワクチン接種後1か月以内に発症します。つまり、このワクチン接種後に、何らかの病気になって、体調不良がみられる人は一定数必ずいるということです。それが「ワクチンが原因である」ととらえられたのではないかと考えられます。
厚生労働省や専門家たちも「ワクチンが原因とは確定していない症状をワクチンが原因であるととらえられていた」と説明しています。そうした中、世界中からデータを集めてきて、HPVワクチン接種後にどんな病気が増えているのか調べてみても、特別増えてきている病気が存在しない。そのようなデータを根拠に、各国や日本の厚労省、専門家は「HPVワクチンが原因とはされない」と説明しているわけです。
ここで重要なのは、ワクチン接種後に体調不良の訴えがあること自体は本当であり、否定されるものではないことです。理由がなんであれ、体調不良があったこと自体は疑いようがありません。
HPVワクチンが導入された時から現在まで、接種に際して緊張や不安が大きかったり、実際に接種時の痛みが強かったりする、と指摘されています。そのような時、何か体調不良があるとワクチンのせいではないかと思ってしまうのは自然です。
目の前に体調不良を訴える人がいるときに、そこでワクチンが原因かどうか白黒つけるのは臨床的には益がなく、その症状に対して、どう治療、対応するか、医学的に、本人にとって最適のアプローチは何かということをやるべきです。そのために「HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関」が各都道府県ごとに指定されているわけですね。
一方、その体調悪化がワクチンのせいなのかどうかは、科学的なエビデンスとしては、疫学的に評価する必要、方法があります。国によっては、ある病院とか国民全体でいろいろな病気にどれだけかかっているかを記録するシステムを導入しているところがあります。その記録を調べて、何かある病気、例えば自己免疫疾患が実際に増えたかどうか、HPVワクチンの接種歴と関連させて解析すれば、接種した人だけに特に増えているかどうかが定量的に言えるわけです。
ワクチン接種の副反応としてある懸念が提起された場合、その様な評価システムがあれば『少なくともその病気が、接種した人10万例に1例以上は起こっておらず』『ワクチンを接種していない時と同じくらいの発生率である』とデータで言える。
つまり、HPVワクチンが安全である、特に懸念するような副反応ではないと言える。このように、一定の根拠を持って言えることが大事です。
一方、行政・運用の観点からいうと、HPVワクチン接種後に、ある一定の症状を訴えた場合、その人たちと厳密な因果関係を巡って争うのではなく、補償や救済が行われるのも、それによってワクチンを受ける人の不安や負担が減るのであれば、補償制度は行政の仕組みとしてあっていいし、あるべきでしょう。
例えば、接種後に、ギランバレー症候群(正しいかは別としてワクチンの副反応としてよく懸念が示される)が発症する、手足の脱力などがある一定の期間内に起こった場合『因果関係が否定できない』として補償するというのはあってもよく、実際なされているでしょう。ただ、疫学的に見た場合に、ギランバレー症候群のリスクがHPVワクチン接種にあるのかと言えば、100万例に1例以上ではないと言え、実質的には、自然発症率と区別がつかないと言えます。
疫学的にワクチンが原因で体調不良が起こったかどうかと、補償されるかどうかは別だし、別であるべきだということです。そして、それは安全性の議論とは別の話だということです。
■接種すべきか迷っている人には
子宮けいがんの原因となるようなHPVに感染するリスクは、性的な新しいパートナーを持つ場合に必ず発生します。
ワクチンを接種せずに、新しいパートナーを持つことは本来予防できるリスクに対して無防備だと言えます。接種が1年遅れたらその1年間分、HPVに感染してしまう人が出ます。特に性的な行動をすることがあるキャッチアップ対象集団ではそう言えるでしょう。
HPVワクチンは他のワクチンと同じくらいかそれ以上に安全で、効果があると言えます。来年3月までと期限が迫る中、キャッチアップ接種の対象になっている人たちがどれだけ接種するのか、どう呼びかけるかが課題だと思います。そしてそのことはそのまま、定期接種対象者(小6から高1相当の女性)たちにも言えることです。
▶ 【子宮けいがんとワクチン】各国では男性も接種──イギリス在住研究者に聞く(https://news.ntv.co.jp/category/society/c1ed961648194df5967f2c104026591b )に続く